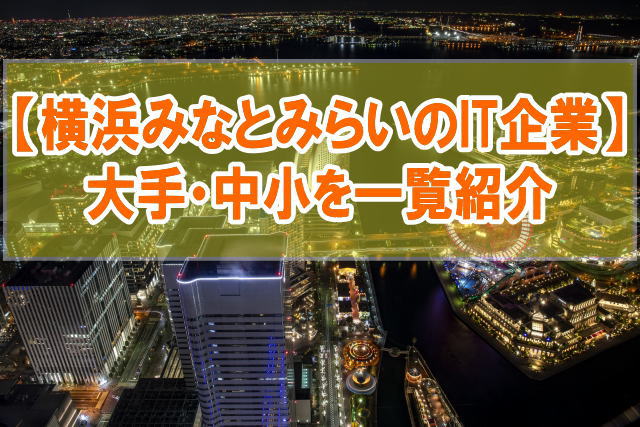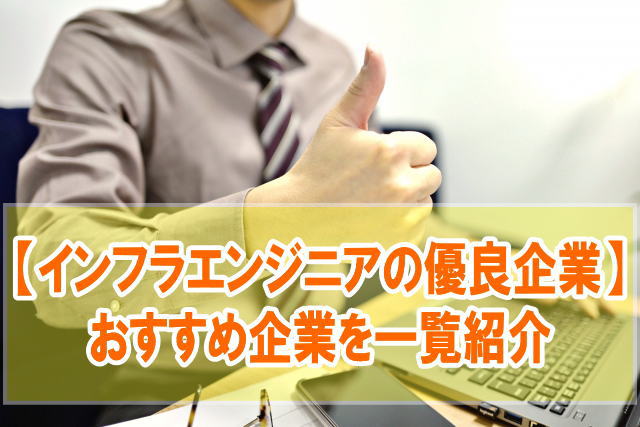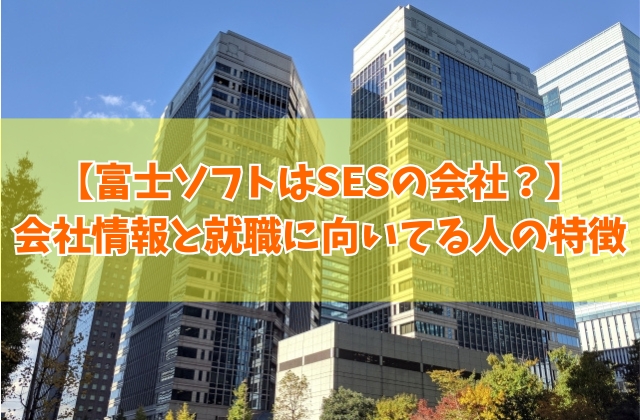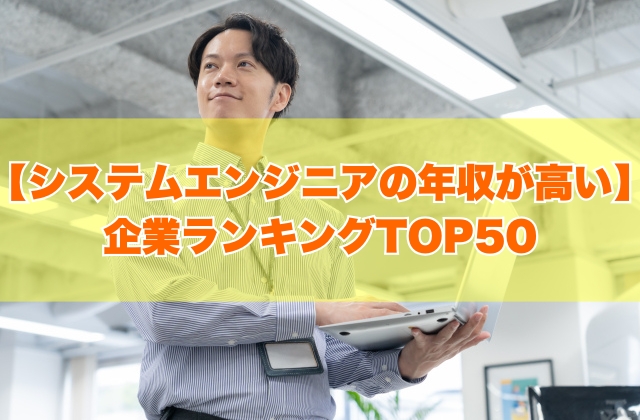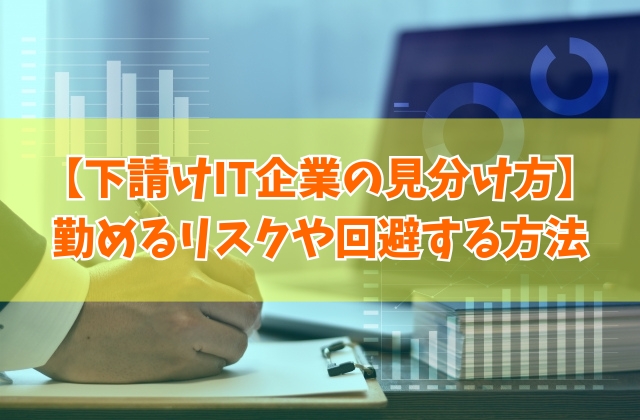
「下請けIT企業の見分け方は?どうすれば回避できる?」
「下請けIT企業に勤めるリスクって?元請け企業がどんな会社かも教えてほしい!」
IT企業への就職・転職を目指す人にとって、「気づかないうちに下請け企業へ入社してしまうのでは」という不安はつきものです。
働き方や将来のキャリアに大きく影響するからこそ、企業選びは慎重に進めたいもの。
とはいえ、求人票だけでは企業の立ち位置がわかりづらいこともあります。
そこでこの記事では、現場経験や業界構造に基づいた「下請けIT企業の見分け方」の具体的なポイントとそれら企業を回避する方法を紹介しています。
納得のいく転職を実現するための第一歩として、見分け方や対処法を参考にお役立てください。
- 求人票に「客先常駐」や「SES」などの記載があれば下請けの可能性が高い
- 勤務地や勤務時間が曖昧な企業は受託や常駐前提の下請けであるケースが多い
- 元請け企業の特徴や実績を把握し、それ以外の企業と比較して見分けをつける
IT業界で働く上で、自分が所属する企業の立ち位置はキャリアに直結します。
求人票や業務内容、取引先などの情報を丁寧に確認することで、下請けIT企業の見分け方の精度が格段に高まります。自分の未来を守るためにも、企業選びの段階からしっかりと見極める視点を持つことが重要です。
とはいえ、求人票の情報だけで「下請けかどうか」や「キャリアが伸びる環境かどうか」を正確に判断するのは簡単ではありません。
そんなときは、IT業界に精通した専門の転職エージェントに相談してみましょう。
業界構造や企業の立ち位置に精通した専門アドバイザーが、あなたの希望に合った“元請け・上流工程の企業”を厳選して紹介してくれます。
自分一人では見抜けない部分をプロにサポートしてもらうことで、後悔のないキャリア選択が実現します。
✅【無料】年収アップも実現!IT専門の転職エージェントおすすめ3選
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営『マイナビIT AGENT』|一人ひとりのニーズにマッチした転職を提案するIT・Web業界に強い転職エージェント(※マイナビのプロモーションを含みます。)
- 希望企業への転職成功率96%を誇る『レバテックキャリア』|圧倒的な内定率!5人に4人が年収UPを実現するIT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが内定獲得まで徹底サポートするIT特化型転職エージェント。
- 社内SEの転職支援に特化した『社内SE転職ナビ』|社内SE求人は10,000件以上&入社後の定着率96.5%!専任アドバイザーが経歴や希望を丁寧にヒアリングし、該当する自社開発・情シス求人を提案。
下請けIT企業の見分け方8選
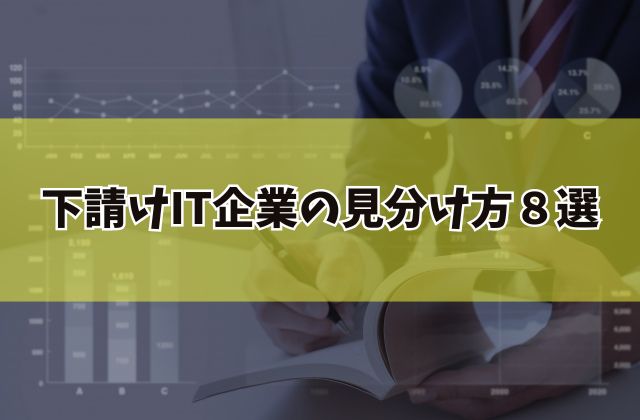
IT業界で就職・転職を考えている方にとって、「どの企業が下請けIT企業なのか」を見分けることは、キャリアを左右する重要な判断材料になります。
下請け企業に入社すると、思っていた働き方ができなかったり、成長の機会が限られたりするリスクもあるため、事前の見極めが大切です。
この「下請けIT企業の見分け方8選」では、求人票や企業情報から判断できる具体的なポイントを順番にわかりやすく紹介します。
- 求人票に客先常駐と記載がないか調べる
- 契約形態(請負/準委任)の記載を確認する
- 事業内容にSESやアウトソーシングがあるか調べる
- 取引先企業に偏りはないか業種と会社名を調べる
- 社内サービスや自社システムの有無を確認する
- 勤務地や勤務時間が未確定かチェックする
- オフィス規模と社員数のバランスを見る
- 帰社日や社内イベントの頻度を探す
理想的な職場環境を手に入れるために、ぜひ参考にしてください。
【見分け方1】求人票に客先常駐と記載がないか調べる
まず最初に確認しておきたいのは、求人票に「客先常駐」という言葉があるかどうか。ここ、かなり大事なポイントです。なぜなら、それが書かれている時点で、その企業はおそらく自社で働くのではなく、別の会社、つまりクライアント企業に常駐する前提で人を募集しているからです。
たとえば「勤務地:都内クライアント先」「プロジェクト先に常駐」といった記載を見かけたことはありませんか?これは、その企業の社員でありながら、日々通うのは他社のオフィスという働き方を意味します(出典:参考資料)。
もちろん、このスタイルがすべて悪いわけではありません。ただ、SESや多重下請けの構造の中で働くとなると、裁量が限られたり、キャリアの伸びしろが見えにくかったりするのは避けられない現実です。
一方、「勤務地:本社」「自社サービス開発」「自社勤務」などと書かれている求人なら、開発や運用の現場が自社内で完結しているケースが多く、元請けに近い立場で働ける可能性があります。
求人を眺めているとき、つい仕事内容や給与ばかりに目が行きがちですが、「どこで働くのか」という視点を忘れてしまうと、入社後にギャップを感じるかもしれません。小さな一文の中に、企業の実態がにじんでいる。そんなつもりで、一つ一つの表現を丁寧に読み取っていくことが、後悔しない転職の第一歩です。
【見分け方2】契約形態(請負/準委任)の記載を確認する
求人票を見て、仕事内容や勤務地だけをサッとチェックして終わっていませんか?もしIT業界で「下請けを避けたい」と思っているなら、契約形態の欄にもきちんと目を通すべきです。そこに書かれている「請負」や「準委任」という言葉が、あなたの働き方を大きく左右します。
「請負」は、成果物の納品がゴール。つまり“完成品を納めてナンボ”の契約です(出典:請負に関する契約書)。一方、「準委任」は、成果ではなく“稼働時間そのもの”に対して報酬が発生する仕組み。いわば“時間を切り売りする働き方”といえるでしょう(出典:参考資料)。
そして、この準委任をベースにした働き方として広く知られているのが「SES(システムエンジニアリングサービス)」です(出典:参考資料)。
実際、「SES」「準委任契約」「客先常駐」などのキーワードが求人票に並んでいれば、その会社は限りなく“下請け”に近い立ち位置だと見て間違いありません。厚労省の配布資料でも、こうした契約形態が明示されている企業は、クライアント企業の下で働く構造になりがちだと明言されています(出典:ITエンジニアが働く職場の現状)。
だからこそ、契約形態は軽視できないポイントです。「成果物を納める請負なのか」「時間単位で動く準委任なのか」「裁量はどこにあるのか」──求人票に書かれた一言一言を丁寧に読み取ることで、企業の“本当の姿”が見えてきます。求人情報の中に散りばめられたヒントを見逃さず、働き方の選択を自分の手に取り戻していきましょう。
【見分け方3】事業内容にSESやアウトソーシングがあるか調べる
IT企業の実態って、求人票の「事業内容」にけっこうハッキリ表れていたりします。特に注意して見てほしいのが、「SES」や「アウトソーシング」という言葉が使われているかどうか。この2つが並んでいる場合、かなりの確率で“下請け寄り”の働き方になると思って間違いありません。
SESは、自社のエンジニアをクライアント先に派遣して、指示された業務をこなすスタイル。業界では“準委任契約”って呼ばれているものですね。アウトソーシングは、運用や保守、テスト業務などを丸ごと外部に任せる形ですが、それがメイン事業の会社だと、自社開発のチャンスはほぼゼロということも。求人票で「SESを中心とした人材ビジネス」「ITアウトソーシングの受託業務」なんて書かれていたら、もう警戒しておいた方がいいです。
反対に「自社サービスの開発運営」や「自社内のプロダクト開発」といった表現があれば、元請けや自社完結型の働き方が期待できます。こうした違いって、なかなか見逃されがちなんですが、実際の職場環境を分ける大きな境目です。
結局のところ、「どんなプロジェクトに関われるか」は、その企業がどこから仕事を請けているのか、どこに主導権があるのかに直結します。求人票の“たった一文”に、未来の働き方が詰まっていること、意外と多いんですよ。
そして、事業内容にSESやアウトソーシングがあるか調べるための情報収集には転職エージェントの「レバテックキャリア」が特に有効です。
結局、理想の会社、希望する働き方にマッチした求人に出会えるかは「タイミング次第」です。
欲しい求人が、永続的に掲載されていることはあり得ませんので、常にアンテナを張る意味でも転職エージェントに事前に登録しておいて、情報収集しておくことをおすすめします。
【見分け方4】取引先企業に偏りはないか業種と会社名を調べる
「この会社、本当に幅広く取引してるのかな?」
求人票や企業サイトを見ながら、そんな目で“取引先一覧”を眺めてみるのは、意外と見落とされがちな見分けポイントです。取引先の業種や社名に偏りがある場合、それはその会社が下請け気質に寄っているサインかもしれません。
たとえば、金融系の名前しか出てこないとか、特定の親会社グループばかりに依存しているように見えるとき。これは、元請けの指示に従って動く構造になっている可能性が高いです。実際、フリーランス協会の調査などでも、多重下請け構造による中抜きの問題が指摘されていて、特定の大手企業としか取引していないIT企業は“末端”で動く傾向が強いとされています。
逆に「流通・医療・官公庁・製造・教育」など、異なる業種の取引先がずらりと並んでいる場合、その企業は受託開発やソリューション提案を自社でリードしているケースが多く、比較的自立した業態である可能性が高いです。
だからこそ、求人票を読むときは、年収や休日数に気を取られすぎず、「誰と仕事をしているのか」にも目を向けてみてください。取引先のラインナップには、会社の“立ち位置”が滲み出ます。企業名が少ない、業種が偏っている、あるいはそもそも非公開──その違和感は、無視しない方がいいと思います。
とはいえ、求人票や企業サイトの情報だけで「元請けか」「下請けか」を正確に見抜くのは簡単ではありません。
そんなときは、IT業界に精通した専門の転職エージェントに相談してみましょう。
取引構造や案件の実態を把握しているキャリアアドバイザーが、元請け・自社開発・上流工程の企業など、あなたの希望に合った環境を提案してくれます。
一人で判断するより、プロと一緒に企業を選ぶことで、後悔のないキャリアを築けます。
✅【無料】年収アップも実現!IT専門の転職エージェントおすすめ3選
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営『マイナビIT AGENT』|一人ひとりのニーズにマッチした転職を提案するIT・Web業界に強い転職エージェント(※マイナビのプロモーションを含みます。)
- 希望企業への転職成功率96%を誇る『レバテックキャリア』|圧倒的な内定率!5人に4人が年収UPを実現するIT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが内定獲得まで徹底サポートするIT特化型転職エージェント。
- 社内SEの転職支援に特化した『社内SE転職ナビ』|社内SE求人は10,000件以上&入社後の定着率96.5%!専任アドバイザーが経歴や希望を丁寧にヒアリングし、該当する自社開発・情シス求人を提案。
【見分け方5】社内サービスや自社システムの有無を確認する
IT企業を見分けるうえで意外と重要なのが、「その会社に“自分たちのサービス”があるかどうか」。これは本当に大きな分かれ道です。
もし企業サイトや求人票に「自社プロダクトを開発・運用中」といった記載があれば、かなりの確率で“元請け”に近い体質。逆に何も書かれておらず、受託開発や客先常駐ばかりが目立つなら、下請け色が強いと見ていいでしょう。
なぜそこが重要なのかというと、「自社サービスを持つ=企画から運用まで社内で完結する」からです。つまり、どの案件に誰が関わるかを自分たちで決められる立場にあるわけです。一方、他社から仕事をもらって動くスタイルの場合、働き方もスケジュールも、すべて“外部の都合”に左右されがちになります。
たとえば「クラウド会計ソフトを自社で展開」「教育機関向けのLMS(学習管理システム)を開発中」といった記載があれば、その会社は自分たちの力で事業をつくっている証拠。一方で、こういった記述がまったく見当たらない場合、「SESや受託開発が主軸」の可能性が高いと考えておきましょう。
働く場所や待遇も大切ですが、エンジニアとしてどう成長できるかを考えたとき、自社サービスの有無は見逃せないポイントです。求人票の端っこに書かれた数行が、将来のキャリアの明暗を分けるかもしれません。
【見分け方6】勤務地や勤務時間が未確定かチェックする
求人票を読むとき、「勤務地:都内各所」「勤務時間:配属先に準ずる」──こんな表記に出くわしたことはないでしょうか。パッと見ではよくある書き方に見えますが、実はここ、下請け体質のIT企業を見分けるうえで、かなり重要なヒントになります。
なぜかというと、SESや客先常駐を前提とする企業では、プロジェクトごとに現場が変わるため、勤務地も勤務時間も“確定できない”のが当たり前(出典:参考資料)。つまり、最初から「明記できない事情」があるということです。たとえば、エンジニア向け求人サービス「doda」のコラムでも、「勤務時間や勤務地があいまいな求人は、客先常駐型の可能性が高い」とはっきり書かれています。
たとえば「勤務地:首都圏プロジェクト先」「時間:9:00~18:00(※常駐先に準ずる)」などの表記があるなら、実際には複数現場を転々とする前提かもしれません。逆に「本社勤務」「社内開発」「勤務時間:フレックス制度あり」などと明記されている場合、自社内完結の働き方が期待できます。
表面的には似たような表現でも、その“濁されている情報”の裏にある現実はまったく違います。求人票の片隅にある小さな違和感が、入社後の働き方そのものにつながっている。そう考えると、曖昧な表現ほど丁寧に読み解くべきポイントなのかもしれません。
【見分け方7】オフィス規模と社員数のバランスを見る
会社を見極めるとき、「オフィスの広さ」と「社員数」があまりにもかけ離れていないか、一度冷静に見直してみてください。地味なポイントに見えて、実はここ、意外とその企業の実態がにじみ出る部分なんです。
たとえば、社員が20人しかいないのに都心の大型ビルにフロアを構えているとか、300人近くいるはずなのに、写真を見るとオフィスがワンルームに毛が生えたような感じだったり。こういうギャップ、よく探すと案外出てきます。
実際、リスクモンスターの業界レポートでも、ソフトウェア業界の企業のうち約半数が社員100人未満、500人以上はわずか25%程度にとどまっているというデータがあります。つまり、社員数とオフィスの規模感が極端にズレている場合、「そのオフィスは飾りで、実際の働き場所は客先」なんてことも珍しくないということです。
「オフィスが豪華だから安定してそう」と思っていたら、入社後にほぼ全日外勤──そんなミスマッチを避けるためにも、会社紹介ページや採用サイトに出ている写真や数字を鵜呑みにせず、全体像で“違和感”を感じてほしいんです。数字と現場が一致しているか。それは、下請け体質かどうかを読み解く、静かだけど確かな手がかりになります。
【見分け方8】帰社日や社内イベントの頻度を探す
会社の雰囲気や社員のつながりが見える一つのポイントが、帰社日や社内イベントの有無です。頻度や開催状況を見れば、その会社が現場任せなのか、社員を大切にしているのかがなんとなく伝わってきます。
たとえば、SESや客先常駐がメインの企業の場合、社員は普段、取引先で働くことが多いため、意識して交流の機会を設けないと社内で孤立しやすくなります。その対策として、月に1度の帰社日や、年に数回の社内イベントを行う企業が少なくありません。
実際、リヴェル社のインタビュー記事でも「毎月の帰社日や研修は、社員のつながりを維持する上で重要な場」として紹介されていました。また、HISが行った“社内行事に関する意識調査”では、社内イベントを定期的に開催することで「エンゲージメント向上」が図られていることもわかります。
こうした背景を踏まえると、「帰社日が定期的にある」「イベントが年に数回開催されている」といった情報は、求人票や企業ページ、社員インタビューなどから読み取れます。もし何も触れられていなかったら、それは少し気になるポイントです。
面接時に「帰社日はどのくらいありますか?」「社内イベントの雰囲気はどんな感じですか?」と自然に聞いてみるのも、会社の空気を感じ取るひとつの手でしょう。
下請けIT企業に勤める5つのリスクとは
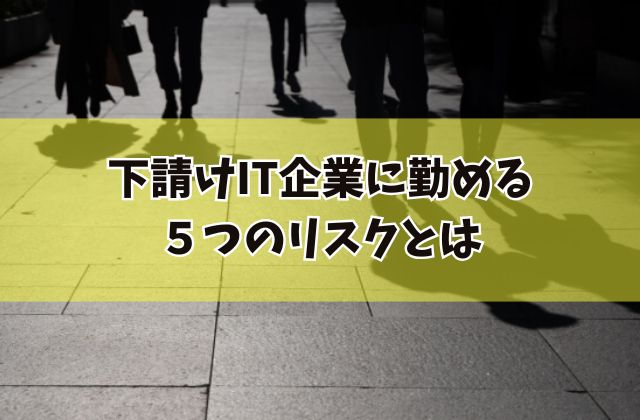
下請けIT企業に就職すると、一見安定しているように見えても、思わぬ落とし穴が潜んでいることがあります。
給与やキャリアの伸び方、働く環境など、元請け企業とは違う現実が待っている場合も少なくありません。
特に客先常駐型の働き方では、自社の文化が感じにくく、孤立感を覚える人も多いです。
ここでは、実際に働く上で知っておくべき「下請けIT企業に勤める5つのリスク」について、具体的な事例を交えながら解説します。
IT企業への転職や就職を考えている方は、後悔しないための判断材料として、ぜひ参考にしてみてください。
【リスク1】年収が元請けより低くなる
下請けIT企業に勤めると、同じような仕事をしていても「なぜか給料が伸びない」と感じる人が多いです。これは気のせいではなく、実際に数字で見ても差が出ています。
たとえばTech総研が公開したデータでは、元請けの平均年収が約603万円に対し、1次下請けは577万円、2次下請けは518万円、3次下請けでは496万円と、階層が下がるほど報酬が下がる傾向がはっきりしています。
| 階層・立場 | 平均年収(万円) | 元請け比(%) | 元請けとの差額(万円) |
|---|---|---|---|
| 元請け | 603万円 | 100.0 | – |
| 1次下請け | 577万円 | 95.6 | ▲26万円 |
| 2次下請け | 518万円 | 85.9 | ▲85万円 |
| 3次下請け | 496万円 | 82.2 | ▲107万円 |
理由は単純で、案件が流れるたびに中間マージンが発生するからです。エンドクライアントから支払われた金額の一部が、上位の企業を経由するごとに削られていく構造になっているのです。特に中小の下請け企業は価格交渉の余地が少なく、元請け企業と比べて給与水準が上がりづらい現実があります。
例えば同じ30代前半のエンジニアでも、元請けに所属していれば年収600万円前後を狙える一方、三次請けになると500万円を切るケースも珍しくありません。数字だけを見ても、100万円近い差が生まれている計算です。キャリアの段階でどこに身を置くかは、今後の年収にも直結します。
求人選びの際は、仕事内容だけでなく、自分がどの立ち位置の企業で働くのかも意識して確認しておくことが大切です。
とはいえ、求人票の情報だけで「元請け企業なのか」「下請け構造に巻き込まれないか」を見抜くのは簡単ではありません。
そんなときは、IT業界に精通した専門の転職エージェントに相談してみましょう。
業界構造や内情を熟知したキャリアアドバイザーが、年収アップが狙える元請け・自社開発企業を厳選して紹介してくれます。
自分だけで求人を探すより、プロと一緒に動くことで“年収が下がるリスク”を防ぎ、理想のキャリアを築く近道になります。
✅【無料】年収アップも実現!IT専門の転職エージェントおすすめ3選
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営『マイナビIT AGENT』|一人ひとりのニーズにマッチした転職を提案するIT・Web業界に強い転職エージェント(※マイナビのプロモーションを含みます。)
- 希望企業への転職成功率96%を誇る『レバテックキャリア』|圧倒的な内定率!5人に4人が年収UPを実現するIT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが内定獲得まで徹底サポートするIT特化型転職エージェント。
- 社内SEの転職支援に特化した『社内SE転職ナビ』|社内SE求人は10,000件以上&入社後の定着率96.5%!専任アドバイザーが経歴や希望を丁寧にヒアリングし、該当する自社開発・情シス求人を提案。
【リスク2】キャリアアップ機会が限られる
「このまま、ずっと同じ作業だけで終わってしまうのかもしれない」、下請けのIT企業に入った人が、ふと漏らすこんな言葉には、深い現実がにじんでいます。
実際、SES(システムエンジニアリングサービス)や多重下請け構造の中で働くエンジニアの多くが、設計や要件定義といった“上流工程”に関わるチャンスがほとんど与えられない状況に置かれています(出典:IT産業における下請の現状・課題について)。LEVTECHの業界ガイドでも、「技術や成果が適切に評価されにくく、キャリアの選択肢が狭まりやすい」と明言されています。
なぜかと言えば、業務のほとんどが指示待ち型で完結してしまうからです。たとえば、他社のプロジェクトに常駐して、言われた通りにコードを書くだけ、テストを繰り返すだけ。そんな現場に長くいればいるほど、経験が「広がらない」のです。
もちろん、どんな仕事にも価値はあります。ただ、「5年後、10年後に自分はどうなっていたいか?」という視点で見たとき、やはり成長の場が用意されている環境かどうかは大きな分かれ道になります。
求人を見る際は、「自社サービスの開発に関われるか?」「要件定義や設計のフェーズに触れられるか?」というポイントに注目してみてください。面接で「どんな業務割合で案件を担当しますか?」と深堀りするのも、企業の実像を見極める手がかりになります。
【リスク3】客先常駐や現場移動の頻度が高い
IT業界で「下請け企業かもしれない」と疑ったほうがいいサインのひとつが、客先常駐が前提となっている働き方です。とくにSESや準委任契約で動いている企業の場合、プロジェクトごとに常駐先が変わるため、現場移動が多くなる傾向があります。
実際、ICT業界の労働環境に関する調査(ICTジャーナル)では、常駐が2年以上に及ぶケースが半数以上。しかも、自社に出社するのは月1回以下という声も多く、名ばかりの「自社勤務」に近い実態が浮かび上がっています。
こうした働き方は、体力的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。毎回異なる会社に適応しなければならず、人間関係の構築も一からスタート。所属している企業への帰属意識は薄れやすく、「自分は誰のために働いているのか」が曖昧になることも珍しくありません。
もし求人情報に「勤務先はプロジェクトにより異なる」「客先常駐あり」などの記載があれば、注意が必要です。逆に「社内開発中心」「自社サービスあり」などと明記されていれば、現場移動の頻度は少ない可能性が高いでしょう。
【リスク4】裁量が少なく作業が単調になりやすい
IT業界に入って、「手に職をつけて成長したい」と思っていたのに、いざ働いてみたら、毎日ひたすら同じような作業の繰り返し──そんな声を、下請け企業で働く人からよく耳にします。
なぜこうなるかというと、下請けの立場では、上流の設計や企画といった“頭を使う部分”はすでに決まっており、現場には「言われた通りに動く」ことが求められるからです。実際、業界構造としても、下流の工程にいくほど裁量が小さくなっていくのは避けられません(出典:参考資料)。
たとえば、複数の求人を見比べてみると、「テストのみ担当」「仕様変更には対応のみ」といった表現がある企業では、仕事における意思決定の余地が極端に少ない傾向が見られます。一方で「技術選定に参加可」「要件定義から携われる」といった文言がある企業では、自分の意見や工夫が反映されやすい環境だと推察できます。
毎日がマニュアル通りの作業で終わる職場では、3年経ってもスキルが変わらないということも珍しくありません。転職時には「どこまでの工程に関われるか」「自分の裁量はあるか」という点に、ぜひ目を向けてみてください。
【リスク5】長時間労働や休日出勤が常態化する可能性
「気がついたら深夜、気がつけば休日出勤」。下請けのIT企業に身を置くと、そんな日常が珍しくありません。現場では納期がすべて。元請けからの突然の仕様変更や急なスケジュール調整に振り回されることも多く、結果として、残業や土日の対応が“当たり前”になってしまうのです(出典:参考資料)。
実際、厚生労働省の調査によれば、IT業界は他業種と比べて月の平均残業時間が長く(所定外労働時間が全産業の129時間に対して198時間。出典:IT業界の長時間労働対策について)、とくにSESなどの契約形態で働くエンジニアはその傾向が顕著とされています。現場が変わればやり方も人も変わり、慣れるまでに時間もかかる。そんな状態で生産性を求められれば、労働時間が伸びていくのは当然のことです。
求人票に「残業あり」と書かれていなくても、客先常駐やSESといったワードがあれば注意が必要です。実態として、管理が行き届かず、法定外の労働時間が常態化しているケースもあります。過酷な環境を避けるには、面接時に労働時間の実情をしっかり確認し、口コミサイトなどで現場の評判を調べておくことが欠かせません。
自分の時間を犠牲にして働き続ける環境で、本当に納得のいくキャリアが築けるのか。そう問い直すことから、理想の転職は始まります。
見分け方を踏まえて下請けIT企業に就職・転職を回避する方法

下請けIT企業にありがちな特徴を理解したら、次に考えるべきは「どう選ぶか」です。
求人内容や面接時のやり取りを通じて、下請け構造に巻き込まれにくい企業を見極めることが重要です。
ここでは、見分け方を踏まえて下請けIT企業に就職・転職を回避する方法を紹介します。
理想のキャリアを築くための具体的な行動指針として役立ててください。
【方法1】大手または上流工程を扱う求人に絞る
「下請け企業かどうか見極めたい」──そう考えているなら、まずは求人に出てくる“仕事内容”に目を光らせてみてください。特に注目したいのは「上流工程に関われるかどうか」です。
IT業界では、システムの企画や要件定義といった“上流工程”を担っているのは、たいていが元請け企業。逆に、実装やテストといった下流工程を担当するのが下請け企業の役割です。実際、マイナビIT AGENTが特集している「上流工程に強い求人」では、プロジェクト全体の75%が要件定義~基本設計から始まる案件と紹介されています。
求人票の中で「企画から携われる」「要件定義の段階から参画」などと書かれていれば、下請けではなく元請けに近い立場で働ける可能性が高いでしょう。一方で、「設計書に基づいた開発」「テスト業務中心」などと書かれている場合は、すでに仕事が細分化されている=裁量の少ない下請け工程である可能性が高いです。
なお、求人票だけでは見えない部分も多いため、面接時には「プロジェクトのどのフェーズを担当しますか?」「要件定義や基本設計から関われますか?」といった具体的な質問を投げかけるのがおすすめです。遠慮せずに聞いてこそ、本当の“立ち位置”が見えてきます。
そして、大手または上流工程を扱う求人に絞りたいなら転職エージェント「マイナビIT AGENT」の利用がおすすめです。
マイナビIT AGENTは、国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営のサービス。
全国の大手上場企業から人気ベンチャーまで、幅広い求人紹介が可能で、IT業界出身のキャリアコンサルタントがニーズにマッチした転職を提案してくれます。
【方法2】求人票で客先常駐記載のない企業を選ぶ
転職活動で求人票をチェックするとき、真っ先に注目してほしいのが「客先常駐」というワードです。この一言があるかどうかで、働く環境やキャリアの自由度が大きく変わってきます。
IT業界では、「自社の社員がクライアント先で作業する」スタイルがまだまだ一般的です。これは、いわゆる“客先常駐”という働き方。確かに案件数は多いものの、職場が毎回変わったり、社内メンバーとほとんど関われなかったりと、孤立感を抱えがちです。実際、Indeedでも客先常駐について「会社とのつながりが希薄になる」といった懸念が紹介されています。
では、どう見極めるべきか。求人票に「常駐あり」「プロジェクト先勤務」などとあれば要注意です。逆に「自社開発」「自社内勤務」「社内SE」といった表現がある企業は、下請け色の薄い可能性が高いです。もちろん、100%の判断は難しいですが、疑わしければ面接の場で「現場配属の割合」や「勤務地の固定性」について具体的に確認してみてください。
求人票は、企業からの最初のラブレターです(出典:参考資料)。書かれている言葉の裏にある“前提”を、冷静に読み解く力が求められます。
そして、求人票で客先常駐記載のない企業を選ぶための情報収集には転職エージェントの「レバテックキャリア」が特に有効です。
結局、理想の会社、希望する働き方にマッチした求人に出会えるかは「タイミング次第」です。
欲しい求人が、永続的に掲載されていることはあり得ませんので、常にアンテナを張る意味でも転職エージェントに事前に登録しておいて、情報収集しておくことをおすすめします。
【方法3】面接時に発注元・下請け構造を質問する
IT企業への転職を考える際、求人情報だけでは企業の実態が見えないこともあります。とくに下請け体質かどうかを見極めるには、面接の場で直接質問することが非常に重要です。
というのも、IT業界では多重下請け構造が当たり前のように存在し、「名のある企業に入ったと思ったら、実際は三次請けで現場を転々とするだけだった」という声も少なくありません。『レバテックキャリア』などでもこの点はしっかり取り上げられており、階層構造の中で働くことがキャリア形成に与える影響は大きいと指摘されています。
では、どうやって見抜くか。たとえば、以下のような質問を面接時に投げかけるだけでも、企業のスタンスはある程度読み取れます。
- 「主要な発注元企業名を教えていただけますか?」
- 「案件の多くは一次請けですか? それとも二次請け、三次請けでしょうか?」
- 「自社がプロジェクト全体のどのポジションを担っているか教えていただけますか?」
これらの質問に対して、曖昧な答えが返ってくる、あるいは「情報は開示できません」といった返答ばかりが続く企業は要注意です。もちろん守秘義務の都合で答えづらいこともあるでしょうが、誠実な企業であれば、可能な範囲で実情を説明しようとする姿勢が見えるはずです。
遠慮して聞けずにいると、後から「思っていた仕事とまるで違った」と後悔する可能性もあります。やんわりとした聞き方でも構いません。「どのようなクライアントとお取引されていますか?」といった表現で十分です。面接は一方的に選ばれる場ではなく、あなたが働く環境を見極める場でもあるという意識を忘れないでください。
とはいえ、面接の場で企業の実態を正確に見抜くのは、経験がないと難しいものです。
そんなときは、IT業界に精通した専門の転職エージェントに相談してみましょう。
業界構造や取引形態を熟知したキャリアアドバイザーが、元請けや自社開発など、安定した環境の企業を厳選して紹介してくれます。
面接対策や質問内容のアドバイスも受けられるので、安心して次の一歩を踏み出せます。
✅【無料】年収アップも実現!IT専門の転職エージェントおすすめ3選
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営『マイナビIT AGENT』|一人ひとりのニーズにマッチした転職を提案するIT・Web業界に強い転職エージェント(※マイナビのプロモーションを含みます。)
- 希望企業への転職成功率96%を誇る『レバテックキャリア』|圧倒的な内定率!5人に4人が年収UPを実現するIT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが内定獲得まで徹底サポートするIT特化型転職エージェント。
- 社内SEの転職支援に特化した『社内SE転職ナビ』|社内SE求人は10,000件以上&入社後の定着率96.5%!専任アドバイザーが経歴や希望を丁寧にヒアリングし、該当する自社開発・情シス求人を提案。
【方法4】社内SEに特化した転職エージェントに相談する
「もう客先常駐は避けたい」「下請け構造に巻き込まれたくない」──そんな悩みを抱えているなら、転職活動のスタート地点から見直すことが肝心です。とくに、社内SEに絞って求人を探したいなら、IT全般を扱う総合型の転職エージェントよりも、社内SEに特化したエージェントに頼るのが近道になります。
たとえば『社内SE転職ナビ』は、名前の通り社内SE職に限定した求人を取り扱っており、紹介される企業の多くが自社内勤務、かつ一次請け以上の立ち位置にあるケースが多く見受けられます。
実際、サイト内の公開求人を覗くと、受託開発や常駐SESといった案件はほとんど見当たりません(※2025年10月時点)。この傾向は、下請け企業を意図的に避けたい転職者にとって、非常に安心できる材料ではないでしょうか。
もちろん、100%の正解はありません。ただ、こうした「社内SE専門」のサービスを選ぶことで、無駄な選択肢を最初から除外できる点は大きなメリットです。求人票の文言に惑わされず、エージェント経由で企業の内部事情を聞き出せるのも強みです。
客先常駐かどうか、元請けか下請けか、こうした判断の難しい部分をプロの視点で読み解いてくれるのは、自力での転職活動では得られない安心感に繋がります。
【方法5】自社開発の求人を豊富に扱う転職支援サービスを利用する
もし「下請けっぽい会社にはもう入りたくない」と思うなら、最初の段階で“どんな求人を扱っているか”を見極めることが大切です。特におすすめなのが、自社開発案件を多く扱う転職支援サービスを使うこと。実際、こうしたサービスは常駐型のSES企業を避け、自社でサービスを作る会社の求人を中心に紹介しています。
たとえば『レバテックキャリア』には、自社内開発や上流工程を担う求人がまとまって掲載されています。エンジニアが社内で腰を据えて働ける環境を重視する人にとっては、かなり頼りになる存在です。
また『マイナビIT AGENT』も、事業会社の求人に強く、開発工程に深く関わりたい人に向いています。実際、各サイトの公開案件を見ても、いわゆる“客先常駐”タイプの求人はほとんど目にしません。
チェックすべきポイントは、求人票に「社内開発」「自社サービス」「企画・設計から関与」といったキーワードがあるかどうか。これらがあれば、ほぼ確実に下請け構造ではないと判断できます。
転職活動では、ただ多くの求人を見るよりも、“どんな求人を扱うエージェントか”を選ぶほうがよほど重要です。結局のところ、転職の成否は最初の選択で決まります。
そして、自社開発の求人を探したい方は、転職エージェント「レバテックキャリア」を利用するのがおすすめです。
ITエンジニアが利用したい転職エージェントNo.1。
IT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが、内定率を上げる企業別の面接対策などで徹底サポートしてくれます。
【参考情報】下請けIT企業の見分け方にも役立つ元請け企業一覧

ここまで、「下請けIT企業の見分け方」と「下請けIT企業に就職・転職を回避する方法」を詳しく解説してきました。
さらに踏み込んで下請け企業を見抜きたいなら、まずは「元請け」となる企業を知ることが近道です。というのも、プロジェクトの全体像を設計し、予算を管理するのは常に元請けの役割。つまり、そのポジションにいるかどうかで、企業の立ち位置がはっきり分かれるからです。
その具体的な「下請けIT企業の見分け方にも役立つ元請け企業一覧」をご覧ください。
| 【元請け企業一覧】企業名 | 企業の特徴 | 売上高(2024年度) |
|---|---|---|
| NTTデータ | SI・コンサル最大手、グローバル展開 | 46,387億円(2025年3月期 連結) |
| 富士通 | 総合ITベンダー、社会・産業に強み | 35,501億円(2024年度 連結・IFRS) |
| 日立製作所 | 産業×ITの巨大企業、SIも中核 | 97,833億円(2024年度 連結・IFRS) |
| NEC | 官公庁・社会インフラに強い | 34,234億円(2024年度 連結・IFRS) |
| 日本IBM | 外資系大手、エンタープライズ特化 | 8,537億円(日本法人・2024年通期) |
| 野村総合研究所(NRI) | 金融に強いコンサル/SIの大手 | 7,648億円(2024年度 連結) |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 商社系SI、マルチベンダー | 7,282億円(2024年度 連結) |
| TIS | 決済・金融SIに強み | 5,717億円(2025年3月期 連結) |
| SCSK | 住友商事系SI、クラウド・基盤に強み | 5,961億円(2025年3月期 連結) |
| BIPROGY(旧:日本ユニシス) | 金融・流通向けに強いSI | 4,040億円(2025年3月期 連結・IFRS) |
| 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 製造・社会基盤のSIに強み | 5,070億円(2025年3月期 連結・IFRS) |
| 日立ソリューションズ | 日立系SI、ERP/CRMなど | – |
| NECソリューションイノベータ | NEC中核のSI会社 | 3,138億円(2025年 会社公表数値) |
| 東芝デジタルソリューションズ | 東芝のデジタル領域中核 | 1,685億円(2025年3月期 単体) |
| NTTドコモソリューションズ(旧NTTコムウェア) | ドコモグループのSI中核 | 2,510億円(2024/4~2025/3 単体) |
| NTTテクノクロス | NTT系ソフト・セキュリティ | 563億円(2025年3月期 単体) |
| SBテクノロジー | MSクラウド/セキュリティに強み | -(24年度単体は親会社セグメントに統合) |
| 大塚商会 | IT販売×SIの独立系大手 | 約1兆円(2024年度 連結) |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | みずほ系のIT×コンサル | – |
| オージス総研 | Daigas(大阪ガス)系SI | 471億円(2025年3月期 連結:子会社数値欄) |
たとえば、NTTデータ(売上高:4兆6,387億円)や日立製作所(9兆7,833億円)、富士通(3兆5,501億円)といった大手SIerは、官公庁や大企業のインフラ案件を一手に担う代表格です。こうした企業は発注側としてプロジェクトを管理しており、請け負い型の下請け企業とは立場がまったく異なります。
もちろん、誰もがこれらの元請けに直接入社できるわけではありません。しかし、転職先の企業が「これら元請けと直接取引しているかどうか」は、チェックして損のない重要ポイントです。企業サイトの取引先一覧やIR情報、採用ページの実績紹介などを手がかりに確認してみてください。
元請け企業の名前を見つけられるなら、その企業は少なくとも二次請け以下ではない可能性が高くなります。「下請けIT企業の見分け方」という視点から考えると、これは確かな判断材料になります。
そして、元請け企業・上流工程を扱う上場企業に転職を実現したい方は、IT業界に精通した専門の転職エージェントをフル活用しましょう。
業界の取引構造や元請け企業との関係に詳しいアドバイザーが、自社開発・一次請けなど、安定した環境の企業を厳選して紹介してくれます。
自分で探すよりも、プロと一緒に動くことで、年収・働き方・将来性のすべてをバランスよく叶える転職が実現できます。
✅【無料】年収アップも実現!IT専門の転職エージェントおすすめ3選
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営『マイナビIT AGENT』|一人ひとりのニーズにマッチした転職を提案するIT・Web業界に強い転職エージェント(※マイナビのプロモーションを含みます。)
- 希望企業への転職成功率96%を誇る『レバテックキャリア』|圧倒的な内定率!5人に4人が年収UPを実現するIT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが内定獲得まで徹底サポートするIT特化型転職エージェント。
- 社内SEの転職支援に特化した『社内SE転職ナビ』|社内SE求人は10,000件以上&入社後の定着率96.5%!専任アドバイザーが経歴や希望を丁寧にヒアリングし、該当する自社開発・情シス求人を提案。
【Q&A】下請けIT企業の見分け方に関するよくある質問

最後に下請けIT企業の見分け方に関するよくある質問をまとめました。
たとえば、一次請けと下請けの具体的な違いや、よく耳にする「多重下請け構造」の実態、そして働き方に違法性があるのかといった点について、わかりやすく丁寧に解説しています。
【質問1】一次請けSIerの一覧は?
一次請けとして代表的なのは、NTTデータ、富士通、日立製作所、NEC、日本IBM、野村総合研究所(NRI)、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)、TIS、SCSK、日鉄ソリューションズといった企業です。
これらは官公庁や金融、製造業などの大規模案件を直接受注し、要件定義から運用までを担う体制を持っています。就職や転職を考える際は、このような企業群を“元請けの代表格”と捉えると判断がしやすいです。
【質問2】IT企業の二次請け企業一覧は?
残念ながら、二次請け企業を一覧化した公的な情報は存在しません。理由は明確で、IT業界は案件ごとに発注先・受注先が入れ替わる多重構造になっているからです。
経済産業省も「システム取引の重層化による不透明性」を課題として挙げており、現場ごとに関係図が変わるのが実情です(出典:産業構造・市場取引の可視化)。もし企業の立ち位置を確認したい場合は、取引先の数や案件規模、発注元の実名公開の有無をチェックしてみましょう。
【質問3】SIerは多重下請けですか?
多くのSIer(システムインテグレーター)は多重下請け構造の中に位置しています。
大手が上流工程を押さえ、設計やテストなどの工程を中小企業や個人事業主に再委託する形が一般的です。公正取引委員会の調査でも、情報処理業は下請け比率が高いと報告されています(最終下請では「下請取引依存度90%以上」が44.6%。出典:ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書)。つまり、業界全体で「多層化」が常態化しているのが現実です。企業の規模よりも、どの工程を担当しているかを見極めるのが重要です。
【質問4】元請けと下請けの見分け方は?
見分ける際のカギは、「契約先」と「指示を出すのは誰か」の2点です。
たとえば、契約書に記載された発注元が自社でない場合、そして現場での指示が常に別会社から出ている場合、その企業は下請けである可能性が高いといえます(出典:労働者派遣と請負の区分の必要性)。労働者派遣や準委任などの契約形態によって、業務指示の責任者が変わるため、応募前や面接時にこの点を詳しく確認するのが効果的です(出典:参考資料)。求人票に書かれている契約形態や面接官の説明には特に注意を払ってください。
【質問5】IT業界でよくある多重下請け構造とは?
IT業界では、発注元(エンドユーザー)から一次請け→二次請け→三次請けへと仕事が流れていく構造が一般的です。
一次請けはプロジェクト全体を管理し、下位層は特定工程を請け負います。こうした多重構造は効率化の一方で、情報共有の遅れや中間マージンの発生を招くリスクもあります。経産省の調査でも、層が増えるほど取引が不透明化しやすいと警鐘を鳴らしています。
【質問6】多重下請けが禁止になるのはいつから?
現時点で「多重下請けそのもの」を法律で禁止する動きはありません。
政府や経産省が進めているのは、あくまで再委託構造の“見える化”と“適正化”です。たとえば契約内容を明確にするガイドラインの整備や、発注・受注の透明性を高める取り組みが中心です(出典:情報システム・モデル取引・契約書)。完全な禁止ではなく、「不当な多重化」を防ぐ方向に舵を切っているのが現状です。
【質問7】IT企業の孫請けの働き方に違法性はある?
孫請けの立場自体は違法ではありません(出典:参考資料)。ただし、現場で発注側の社員が直接指示を出している場合は「偽装請負」、派遣社員をさらに別の現場へ送る場合は「二重派遣」となり、いずれも法律違反です。
厚生労働省も度々注意喚起を出しています(出典:参考資料)。契約形態や指揮系統が曖昧な環境では、違法状態に陥るリスクがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ:下請けIT企業の見分け方と勤めるリスクや回避する方法
下請けIT企業の見分け方と勤めるリスクや回避する方法をまとめてきました。
改めて、下請けIT企業の見分け方8選をまとめると、
- 求人票に客先常駐と記載がないか調べる
- 契約形態(請負/準委任)の記載を確認する
- 事業内容にSESやアウトソーシングがあるか調べる
- 取引先企業に偏りはないか業種と会社名を調べる
- 社内サービスや自社システムの有無を確認する
- 勤務地や勤務時間が未確定かチェックする
- オフィス規模と社員数のバランスを見る
- 帰社日や社内イベントの頻度を探す
そして、IT下請け企業の見分け方|覚えておきたい5つの視点もまとめると、
- 求人票に「客先常駐」や「SES」の記載がある企業は要注意
- 契約形態が「準委任」「請負」の場合は元請けではない可能性が高い
- 自社サービスや自社開発案件がない企業は下請け色が強い傾向
- 面接時に発注元との関係性や案件の流れを聞くことで構造を把握できる
- 元請け企業の一覧と比較し、取引実態を調べると立ち位置が見えてくる
「下請けIT企業の見分け方」を知ることは、キャリアを守るうえで欠かせません。
求人票や企業情報を丁寧に確認し、元請けか下請けかを見抜く目を養えば、働き方や将来性に大きな違いが生まれます。
自分に合った職場選びの第一歩として、正しい情報収集が重要です。