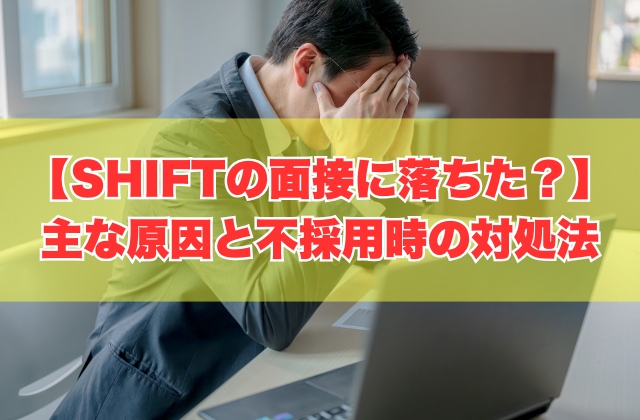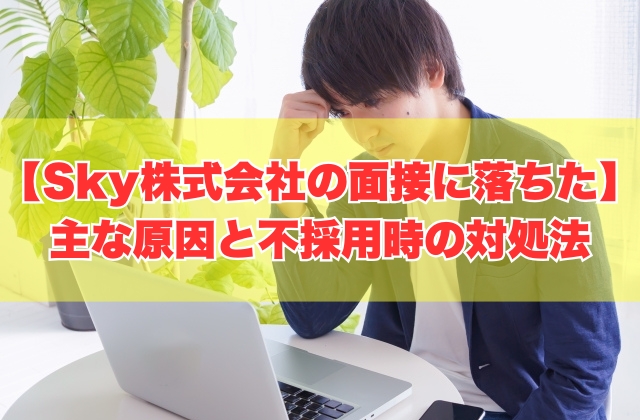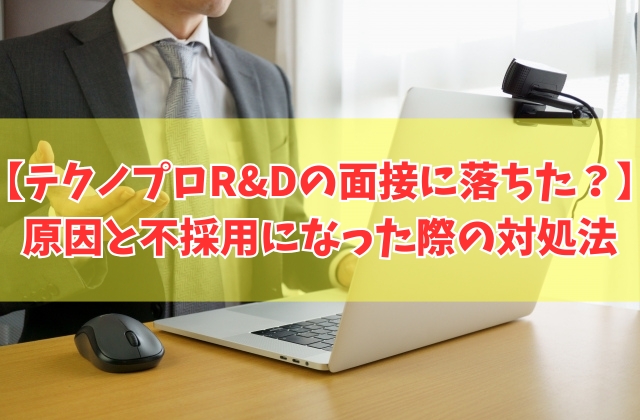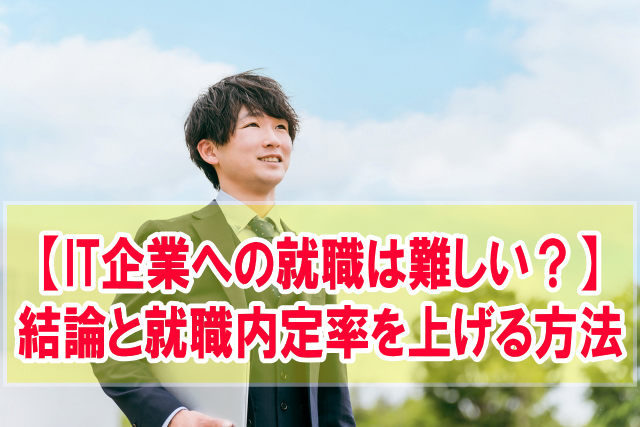「Sansanの志望動機はどのように考えたらいい?」
「今すぐ使える例文はある?具体的な面接対策も教えてほしい!」
Sansanに本気で入りたいと思っていても、「志望動機で何を伝えるべきか分からない」と感じていませんか?
特に新卒や転職希望者では、企業の価値観やビジネスモデルを深く理解し、それを自分の言葉で伝えることが求められます。
しかし、Sansanの掲げる「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションに共感しつつ、なぜSansanでなければならないのかを言語化するのは簡単ではありません。
そこでこの記事では、今すぐ使える“Sansanへの志望動機例文”を目的別に紹介しつつ、面接での伝え方まで含めて面接対策を分かりやすく解説します。
あなたの想いがしっかり伝わるよう、ぜひ最後までご覧ください。
- Sansanのミッションや事業内容に対する共感を具体的に伝えることが重要
- 志望動機には入社後に実現したいことを明確に含めると説得力が増す
- 面接では志望理由に加え、プロダクト理解や企業研究の深さが問われる
Sansanへの志望動機を作成する際は、「なぜSansanなのか」を具体的なエピソードで示すことが鍵です。
単なる企業の魅力ではなく、自分の価値観や経験とどう結びつくかを語ることで、面接官に強く印象づけることができます。志望動機に加え、入社後の貢献意欲や目標まで伝えましょう。
とはいえ、限られた時間でそのすべてを一人で就活対策するのは困難です。あなたもすでに、気づいているのではないでしょうか?
だからこそ『レバテックルーキー』のような就活エージェントの活用が効果的。専門アドバイザーがあなたの強みを見極め、Sansanのような難関企業に刺さる自己PR・志望動機の設計を徹底サポートしてくれます。
迷う前に、一歩踏み出してみてください。忙しい就職活動の中でも最大限の結果を残す“大きな助け”になります。
そして、視点や提案の幅を広げるためにも、就活エージェントは2~3社登録しておくのがおすすめ。比較することで自分に合ったサポートを見極めやすくなり、限られた就活期間を最大限に活かすことができます。
✅【完全無料】実績多数で内定率アップ!IT・Web業界特化の就活エージェントおすすめ3選
- 8,000社以上の優良IT企業情報を保有『レバテックルーキー』|大手Web企業から急成長ベンチャーまで幅広く紹介!志望企業に合わせたES添削や面接対策、ポートフォリオの添削を実施し、内定率アップへ導きます。
- オリコン顧客満足度第3位『TECH-BASE 就活エージェント』|利用後の内定獲得実績5.6倍!IT業界に精通したアドバイザーが内定まで伴走。初歩的なことから専門的なことまで何でも安心して相談できます。
- 文系・理系問わず内定まで最短10日『ユニゾンキャリア就活』|Google口コミ★4.8!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが、就活相談~内定後&入社後も徹底的にサポートします。
Sansanへの志望動機例文10選(新卒向け)
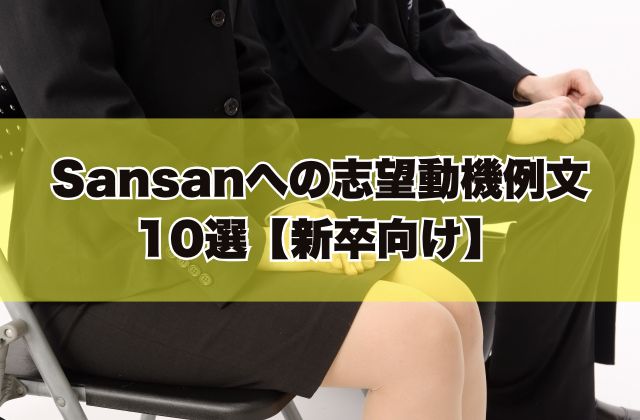
Sansanへの就職を目指す新卒の方に向けて、魅力的で説得力のある志望動機の例文を10個紹介します。
Sansanに就職を考えている人や、Sansanの志望動機を考えている人にとって、今すぐ使える志望動機の例文は非常に参考になります。
自分らしさを伝えながらも、企業のミッションや価値観と一致する内容にすることが、採用担当者の心に響くポイントです。
以下の例文を参考に、自分の経験や想いに合わせた表現に落とし込んでいきましょう。
出会いからイノベーションを生み出すミッションに共感した
「私はSansanの掲げる「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションに強く共感し、志望いたしました。大学では経営学を学ぶ中で、人とのつながりが新たな価値を生む重要な要素であると実感しました。ゼミ活動では企業訪問を通じて多くの方と出会い、課題解決のアイデアを得る経験があり、出会いがもたらす可能性の大きさに感動しました。Sansanのサービスは、単なる名刺管理にとどまらず、人と人の関係性を整理し、企業活動における新たな価値創出を後押ししている点に魅力を感じています。また、Bill OneやEightなど複数のプロダクトを通じて、業務効率の向上やビジネスチャンスの最大化に貢献している姿勢にも惹かれました。私は、チームでの取り組みや相手との信頼関係構築に自信があり、この強みを生かして、お客様の出会いがより実りあるものとなるような支援をしたいと考えています。Sansanで働くことで、世の中の出会いを活性化し、社会にイノベーションを生み出す力になりたいです。」
志望動機は「ミッションに共感しました」だけで終わると印象が弱くなってしまいます。なぜ共感したのかを、実体験や自分の考えと結びつけて書くことが大切です。
また、貢献したい姿を言葉にする際は、抽象的な表現を避け、どんな場面で力を発揮したいのかまで踏み込むと説得力が出ます。
ミッションと自分の価値観が自然に重なるように整理しながら文章にすると、読み手に「この人は本当にそう思っているんだな」と伝わりやすくなります。
名刺をデータにして営業を強くするサービスに惹かれた
「私はSansanの「名刺をデータにして営業を強くする」というサービスに魅力を感じ、志望いたしました。大学でのゼミ活動では、地元企業の営業力向上に関する調査を行い、顧客情報の整理が不十分なケースが多いことに気づきました。担当者の記憶や個人の努力に頼った営業活動は、再現性が低く、成果が安定しにくいと感じました。Sansanは名刺という日々必ず生まれる情報を、組織全体で活用できる形に変えることで、営業活動における「出会いの価値」を最大化している点に強い可能性を見ました。営業は人との信頼関係が基盤であり、その関係を継続的に深めるための情報は、企業にとって大きな資産になります。私は、顧客やビジネスの関係性を整理し、次の提案につなげる仕組みを支えることで、企業の成果に直接貢献したいと考えています。情報が生きた形で循環し、営業がより創造的な活動に集中できる環境を広げることに力を尽くしたいです。」
この志望動機をまとめるうえで大切なのは、単に「共感した」と伝えるだけでは弱いということです。なぜそのサービスに惹かれたのか、自分の経験とどう結びついたのかを具体的に書くことで、読み手にリアリティと納得感を与えられます。
また、志望動機が「企業がやっていること」だけの説明になってしまうと、他の応募者と差がつきません。「自分だからこそ」できることに焦点をあてて、文章に芯を通しましょう。想いだけでなく、行動や成果に落とし込む視点があるとより説得力が増します。
社会の仕事の効率を上げ人の力を引き出す事業に関わりたい
「私は、Sansanが展開する「社会の仕事の効率を上げ、人の力を引き出す」という事業理念に強く共感し、志望いたしました。大学時代のインターンで、紙ベースの名刺や書類管理が業務の非効率さを生み出している現場を目の当たりにし、テクノロジーによる業務改善の可能性に興味を持ちました。Sansanのサービスは、単に名刺を管理するだけではなく、業務の無駄を省き、働く人が本来の力を発揮できるように支援する仕組みであると理解しています。このようなサービスを提供する企業で働くことは、多くの人が自分の能力をより良い形で発揮できる社会づくりに貢献できると感じました。私は、人の強みを引き出す支援や、チームで協力しながら課題を解決していくことにやりがいを感じています。Sansanの事業に関わることで、自分自身の力も高めながら、働く人々の可能性を広げる力になりたいと思っています。」
この志望動機を作るうえでは、「効率化」や「人の力を引き出す」といった言葉だけに頼らず、自分の体験や見た光景を具体的に書くことがカギになります。
たとえば「インターンで目にした非効率な業務」など、リアルな場面を一つ添えるだけで、読み手の印象は大きく変わります。また、共感だけで終わらせず、「自分ならどう関わりたいか」「何ができると思ったか」まで踏み込めていれば、内容としては十分に伝わるものになります。
全体の構成や言葉選びに迷ったら、身近な誰かに話すようなトーンで書いてみるのもおすすめです。
データを生かした提案で企業の成果に貢献したい
「私はSansanの提供するデータ活用の仕組みに強く関心を持ち、志望いたしました。大学でのゼミ活動では中小企業の営業課題を調査し、顧客情報の整理が不十分で、関係性を維持するための提案が担当者の経験に依存している現状を知りました。情報が個人にとどまることで、組織としての営業力が十分に発揮されていない点に課題を感じました。Sansanは名刺や取引情報をデータとして蓄積し、組織全体が共有できる形に変えることで、営業提案をより戦略的に行える環境をつくっていると理解しています。私は、情報を整理し価値のある形に変える仕事にやりがいを感じます。営業担当者が自分らしい提案力を発揮できるように支援し、企業の成果向上に貢献したいと考えています。データを生かした提案が企業の可能性を広げると信じており、その取り組みを支える一員として成長していきたいです。」
「データを生かす」という言葉は抽象的に見えがちですが、自分の経験と絡めることで一気に具体性が生まれます。特に、数字やプロセスの工夫に触れると説得力が増します。
「なぜ惹かれたのか」「どう貢献できるか」を、自分の言葉で自然に語ることが鍵です。
書くときは共感だけで終わらず、自分の行動や考えとミッションをどう結びつけられるかを意識すると、面接官の心にも響きやすくなります。
お客様の課題を聞き改善を続ける姿勢に共感した
「私はお客様の声を丁寧に受け止め、サービスを継続して磨き続けるSansanの姿勢に惹かれ、志望いたしました。大学時代のプロジェクト活動では、地域企業にヒアリングを行い、現場に寄り添った提案を重視してきました。課題の本質を理解するには、相手が何に困り、どんな未来を望んでいるのかをしっかり聞くことが欠かせないと感じました。Sansanは、名刺管理やBill Oneなどの事業を通じて、お客様の日々の業務にある無駄や負担に向き合い、使いやすさの改善を積み重ねていると理解しています。その継続性と誠実さに深い共感を持ちました。私は対話から信頼関係を築くことが得意であり、その強みを生かして、お客様が抱える業務の悩みを整理し、最適な活用方法を提案できる存在を目指したいと考えています。サービスの提供だけではなく、課題解決に寄り添い続ける姿勢が社会に新しい価値を生むと信じており、その取り組みに自分の力を重ねたいです。」
この志望動機をつくるうえでは、「共感した」という言葉に自分の経験や行動をどう結びつけるかが重要です。
ただ気持ちを述べるだけではなく、なぜその姿勢に惹かれたのか、自分が何を見て感じたのかまで丁寧に掘り下げてください。
そのうえで、「どんな形で貢献したいのか」を自分の強みと絡めて書くと、内容に厚みが出て、読み手に伝わる志望動機になります。
新卒から成果に向き合う文化で早く成長したい
「私は新卒の段階から成果に向き合う文化を持つSansanに強く魅力を感じ、志望いたしました。学生時代は、地域の商店街を対象とした集客改善プロジェクトに参加し、目標に向けて自ら考え、行動し、振り返りを重ねる重要性を学びました。努力の過程だけでなく、成果として形に残す責任と達成感を実感できた経験は、今後の働き方にも深く影響しています。Sansanは「挑戦を後押しする環境」と「成果に責任を持つ姿勢」が根づいていると理解しています。若手でも大きな役割を担い、事業に直接貢献できる機会が多い点に魅力を感じています。私は、現状に満足せず新しい視点を取り入れながら、貢献の質を高め続けたいと考えています。周囲との協力を大切にしつつも、主体性を持って目標達成に向き合う姿勢を持ち続けることで、Sansanの成長に力を尽くしたいです。」
単に「共感しました」と伝えるだけでは相手の心には響きません。
なぜその姿勢に魅力を感じたのか、自分のどんな経験と重なるのかを丁寧に言葉にすることが大切です。できれば、相手の話に耳を傾け、課題を一緒に考えていくような行動を取ったエピソードを交えると、説得力がぐっと増します。
読み手が「この人なら一緒に働きたい」と思える内容になっているかを、第三者の目で見直す習慣も忘れないようにしましょう。
学びながら挑戦し成果で語れる人材になりたい
「私は、学びを重ねながら新しい挑戦に取り組み、その結果を成果として示せる人材を目指しているため、Sansanを志望いたしました。学生時代のアルバイトでは、売り場改善の提案に取り組み、実際に売上の向上につながった経験があります。知識を吸収するだけでなく、行動に移し結果を振り返ることで成長が加速すると感じました。Sansanでは、若手でも意思を持って提案し、主体的に役割を担う機会が多いと理解しています。「出会いから価値を生み出す」という目的を持ち、顧客の状況に合わせた提案が求められる環境は、自分の考える成長の形と一致しています。私は、日々学んだことを業務に生かし、周囲から信頼される成果を積み上げたいです。挑戦し続ける姿勢を忘れず、顧客と事業の前進に貢献できる人材として活躍したいと考えています。」
志望動機を伝えるうえで大切なのは、「自分らしさ」がきちんと伝わるかどうかです。
このテーマの場合、企業の考えに共感したという気持ちだけではやや弱いため、「どんな経験を通してそう感じたのか」「自分なら何ができるか」まで踏み込んで書くのが理想です。
たとえば、学生時代の体験や考え方を交えながら話を広げると、読み手にもイメージが伝わりやすくなります。表面的な言葉ではなく、想いと行動がきちんとつながっているかを意識してみてください。
先輩社員の話に刺激を受け自分も挑戦したい
「Sansanへの志望理由は、先輩社員の話を通じて感じた挑戦する姿勢と熱意に大きな刺激を受けたことです。大学のキャリアイベントでSansanの社員の方と直接お話しする機会がありました。そこで伺った、入社直後から大きな裁量を持って業務に取り組み、試行錯誤しながらも着実に成果を出していく話に深く心を打たれました。特に印象に残っているのは、「若手でも意見を言える文化があり、実行まで任される」と話されていた点です。このような環境で自分も成長していきたいと思い、Sansanを強く志望しました。私自身も学生時代、ゼミ活動やアルバイトで新しい挑戦に前向きに取り組んできました。失敗を恐れず、学びながら前進する姿勢には自信があります。Sansanのように、挑戦を歓迎する社風の中で働くことで、自分自身の力を試しながら貢献できる人材へと成長したいです。」
ただ「先輩の話に感動した」と書くだけでは、印象に残りません。何に心を動かされ、自分のどんな価値観や経験と重なったのかを、できるだけ具体的に掘り下げましょう。
「若手にも任せる文化」「裁量がある」という言葉は多くの企業が使うので、それを自分の体験とどう結びつけたのかがカギになります。
誰かの話をきっかけにした“自分の変化”や“決意”を丁寧に言葉にできれば、ぐっとリアリティのある志望動機になります。上辺の共感ではなく、内側から湧き出た意志が見えるかどうかが重要です。
Bill Oneで働き方を変える挑戦に参加したい
「私は、Bill Oneがもたらす働き方の変化に強い魅力を感じ、Sansanを志望いたしました。大学で企業の業務改善に関する研究を進める中で、請求書処理に多くの時間が費やされている現状に触れました。紙やPDFで届く請求書の整理や確認は手間がかかり、ミスも生まれやすいと感じました。Bill Oneは請求書をデータとして一元管理し、担当者の作業負担を軽くする仕組みを提供している点に価値を感じています。働く人の時間を守り、集中すべき仕事に力を注げる環境をつくる姿勢に共感いたしました。私は、現場の声に耳を傾けながら改善を続けられる人材を目指しています。チームと協力し、課題に対する解決策を考え成果につなげる取り組みを大切にしてきました。Bill Oneの成長に参加し、働き方の変化を社会へ広げていく挑戦に貢献したいです。」
志望動機に「先輩社員の話」を取り上げるなら、ただ感動しただけでは伝わりません。
相手のどんな言葉に心が動いたのか、自分のどんな経験と重なったのか。具体的なエピソードを交えて書くと、読み手に熱意がしっかり届きます。
「だからSansanを選んだ」と納得してもらえる筋道をつくることが、共感を得るための鍵になります。共感を示すだけで終わらず、「自分ならこう貢献できる」と視点を未来に向けると、より好印象です。
Contract Oneで会社の利益を守る仕組みに貢献したい
「私がSansanを志望する理由は、「Contract One」を通じて企業の契約管理を効率化し、会社の利益を守る仕組みに貢献したいと考えているからです。大学では経営学を学び、企業活動における契約書の重要性を実務の観点から研究しました。その中で、契約書の管理不備や更新漏れによるトラブルが、企業に大きな損失を与えるリスクになることを知りました。Contract Oneは、契約書をデータで一元管理し、内容の可視化やリマインド機能によって業務リスクを未然に防ぐサービスです。このプロダクトが持つ社会的意義と実用性に強く惹かれ、自分もこのような仕組みを広めていく側に立ちたいと思いました。私は、細かな確認作業を継続する力や、周囲と連携してミスを減らす工夫をする力に自信があります。契約という企業の根幹を支える分野で、安心して働ける社会の実現に貢献したいです。」
「Contract One」に触れる志望動機を書く際に大事なのは、単なるサービス紹介で終わらせず、契約業務が企業にとってどれほど重要か、自分なりの視点で掘り下げることです。
「契約管理=地味だけど極めて重要」と捉えたうえで、それにどう関心を持ったのか、なぜそこに関わりたいのかを、過去の学びや実体験と結びつけて具体的に語るのが効果的です。
文章の中では、「企業活動を支える」という視点を忘れずに、志望理由に厚みを持たせることを意識しましょう。
Sansanへの志望動機例文10選(中途向け)
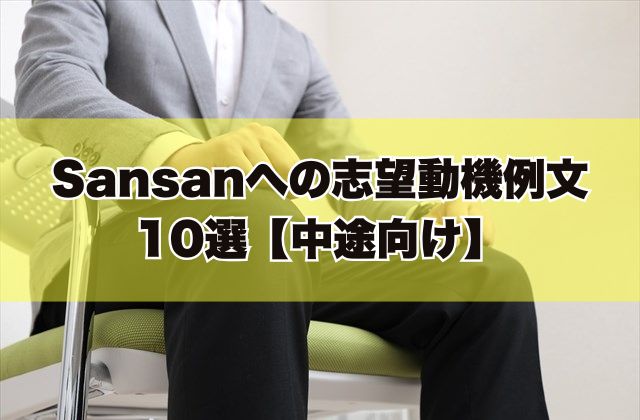
ここからは、Sansanへの転職を検討している方に向けて、実際の業務やサービスに基づいた「Sansanへの志望動機例文10選(中途向け)」を紹介します。
プロダクトの価値や自らの経験をうまく結びつけることが、採用担当者の心に響く志望動機を作るコツです。
以下に記載する例文を参考に、自分らしい志望理由を具体的に表現していきましょう。ぜひ、今後の転職活動の参考にお役立てください。
社会の書類仕事を減らし時間を生む仕組みを作りたい
「社会の書類仕事を減らし、働く人が本来の業務に集中できる環境づくりに貢献したいという思いから、Sansanを志望しています。前職ではバックオフィス向けシステムの開発に携わり、紙の書類や手入力が原因となるミスや確認作業の多さが、現場の負担になっている状況を多く見てきました。Bill OneやContract Oneは、請求書や契約情報を正確にデータ化し、共有や管理をスムーズにすることで、時間と労力を確実に削減できる仕組みだと感じています。社会全体でデジタル化が進む一方、現場では依然として紙業務が残っている領域が多く、そのギャップを埋める技術の必要性を実感しました。開発者として、使いやすさや安定性にこだわりながら、実際の現場の声に合わせて改善を続けられる環境で挑戦したいと考えています。働く人の時間を生み出すサービスに携わり、日々の業務を少しでも前向きにできる仕組みづくりに貢献したいです。」
この志望動機を書くときに一番大事なのは、プロダクトの説明に終始しないことです。
たとえば「業務効率が上がるから良さそう」といった薄い印象にとどめてしまうと、志望動機としては説得力に欠けます。
ポイントは「なぜそのテーマに関心を持ったのか」と「自分の経験とどうつながっているのか」の二点をはっきりさせること。
経験の具体性が強くなるほど、共感から納得に変わります。志望先に“合う人材”であることを、自分の言葉で語れるかどうかがカギです。
契約情報を見える化して安心して働ける社会に近づけたい
「前職では、社内で締結された契約書の所在が分からず更新漏れが起き、取引先との信頼関係に影響が出たことを経験しました。このようなリスクを回避し、誰もが安心して働ける環境を作るためには、契約情報の見える化と管理の効率化が不可欠であると強く感じました。Sansanの提供する「Contract One」は、契約情報を一元管理し、リスクを最小限に抑えながら、業務を効率化する優れたサービスだと考えています。エンジニアとして、契約の可視化を通じて企業の不安を解消し、組織全体の生産性向上に貢献したいと考えています。私自身、バックエンド開発とデータ構造の設計に強みがあり、契約データの取り扱いやリマインド機能の実装など、ユーザー視点に立った開発に取り組んできました。Sansanのプロダクトをさらに使いやすく、安全性の高いものへと進化させ、安心して働ける社会の実現に貢献したいと思い、志望いたしました。」
まず大切なのは、自分の経験に根ざしたエピソードを起点にすること。
単に「共感しました」では弱く、実際に困った場面や具体的な課題を挙げ、その解決策としてSansanのプロダクトがどう響いたかをしっかり言葉にするのがコツです。
そのうえで、自分の得意分野と会社の求めるスキルの接点をどう見出したかを語ると、ぐっとリアリティが増します。
「共感」だけで終わらず、「だから貢献したい」と話をつなげる流れを意識すると、読み手の印象に残る志望動機になります。飾らず、でも芯のある言葉を選ぶことが大切です。
大量データを生かし営業の出会いを価値につなげたい
「前職では営業支援ツールの開発を担当し、営業現場で蓄積されるデータの活用が十分に行われていない課題を実感しました。多くの企業では、名刺や商談履歴、顧客接点などの情報が分散し、必要なタイミングで活用できないまま埋もれてしまうことが多くあります。Sansanの「営業を強くするデータベース」というコンセプトに強く共感したのは、この課題に真正面から向き合い、出会いを成果につなげる仕組みをデータとテクノロジーで実現している点です。エンジニアとして、名刺情報や接点履歴などの構造化・分析に携わり、データの価値を引き出す機能開発に貢献したいと考えています。私自身、データベース設計やログ解析、機械学習モデルの前処理実装に強みがあり、事業成長を技術の力で支える役割を担えると感じています。Sansanで、営業活動の可能性を広げる仕組みづくりに挑戦したいと考え、志望いたしました。」
この志望動機を書くときは、「データ活用」という抽象的な言葉にとどまらず、自分が過去に感じた課題や違和感をきちんと言葉にすることが大切です。
たとえば「営業現場でデータが埋もれていた」といった具体的な体験をもとに話を展開すれば、読み手はあなたの視点に納得しやすくなります。そのうえで、Sansanの事業と自分の強みがどこで重なるのかを丁寧に言葉でつなげると、内容に筋が通ります。
技術面のスキルに触れるときも、「できること」を並べるだけではなく、「どう貢献できるか」を意識すると、印象が大きく変わります。AIらしさのない、血の通った文章とは、こうした背景や意図がきちんと伝わるものだと思います。
名刺データの認識精度を高めて使いやすさを広げたい
「前職では画像処理技術を活用したデータ抽出システムの開発に携わり、文字の読み取り精度が業務効率に大きな影響を与えることを実感しました。名刺情報は企業にとって重要な「出会いの記録」であり、正確にデータ化されて初めて活用価値が生まれると考えています。Sansanが提供する名刺管理サービスは、単に情報を保存する仕組みではなく、営業活動の強化につながるデータ基盤として多くの企業を支えています。エンジニアとして、画像認識処理の改良やアルゴリズムの最適化に関わり、より早く精度の高いデータ化を実現し、使いやすさと信頼性を高める取り組みに貢献したいと考えています。ユーザーが「自然に使える」状態を目指し、現場の声を取り入れながら改善を続ける姿勢にも強く共感しています。名刺データの可能性をさらに引き出し、価値ある出会いを次の成果につなげる基盤づくりに関わりたいと考え、志望いたしました。」
この志望動機を組み立てるうえで大切なのは、「なぜSansanの技術に注目したのか」と「自分の経験やスキルがどこで役立つのか」を、ありきたりな表現ではなく自分の言葉で描くことです。
技術やサービスに対する共感だけでなく、そこに自分が加わることで何を改善できるか、どう価値を広げられるかまで踏み込んで書くと、読み手にしっかり伝わります。
理想論に終わらず、実務との接点を意識すると説得力がぐっと増します。
請求書のデータ化をもっと早く正確にして負担を減らしたい
「前職では、経理部門が毎月多くの請求書を処理する現場を支援する業務に携わり、手入力による作業が精神的な負担や作業時間の増加につながっている状況を見てきました。入力ミスが発生すると確認作業が増え、さらに時間が奪われる悪循環も生まれていました。Bill Oneが提供する請求書のデータ化は、企業の日常業務の負担を大きく減らし、本来の価値創出に集中する環境を広げる取り組みであると感じています。エンジニアとして、認識精度の向上や処理速度を高める仕組みづくりに関わりたい思いがあります。具体的には、文字読み取り処理の精度改善や、ユーザーが迷わず操作できる画面の工夫に取り組み、使い続けやすいサービスに成長させたいと考えています。多くの企業で当たり前に利用される社会的基盤となるように、サービスの改善と挑戦に参加したいと志望いたしました。」
志望動機を書くうえで意識したいのは、「どんな課題意識を持っていたか」「Sansanのどのサービスに共鳴したか」「自分の技術がどう役立てるか」という3つの軸です。
とくに、エンジニア職で中途応募する場合は、過去の経験とスキルを単に並べるだけでは弱くなりがちです。
「なぜSansanなのか」「なぜそのプロダクトを選んだのか」という視点を自分の言葉で深掘りすることが、読み手の共感を生む近道になります。
同じ人や会社を正しくまとめる仕組みを良くしたい
「前職では、顧客情報が複数のシステムに分散し、「同じ人物なのに別人として管理されている」状態が度重なり、営業活動に支障をきたす場面を何度も経験しました。特に名寄せ処理が不十分なことで、過去の取引履歴や接点情報を正確に把握できず、提案の質やスピードが落ちてしまう状況に強い課題を感じました。Sansanが提供する名刺管理サービスは、名寄せ精度の高さと人軸でのつながりを可視化する点において業界の先を行っていると感じています。私はこれまでに、自然言語処理を用いたデータ統合や文字列類似度を活用した照合システムの開発に携わってきました。これらの知見を活かし、Sansanの名寄せ機能をさらに進化させ、正確かつスムーズな情報統合によって営業活動全体を底上げしたいと考えています。顧客接点を信頼できるかたちで一元化することで、「出会い」が真に価値ある資産となる仕組みづくりに貢献したいです。」
この志望動機を書くうえで大切なのは、「名寄せ」というテーマを単なる技術の話に終わらせないことです。
過去の業務経験を通して、自分がどんな場面で困ったのか、何に疑問を持ったのか、具体的なエピソードを添えると、読み手の印象にしっかり残ります。
そして、Sansanの技術やサービスに対する理解が、自分のスキルとどう結びつくのかを丁寧に言葉にすること。抽象的な理想論ではなく、自分がどんな貢献ができるのかを“地に足のついた言葉”で語ると、志望理由にリアリティが生まれます。
技術だけでなく、人や業務への視点も忘れずに盛り込むのがコツです。
速さと安定を両立し毎日の操作をもっと軽くしたい
「前職では業務用Webアプリケーションのフロントエンド開発を担当しており、表示の遅さや動作の不安定さがユーザーの業務効率に直接影響することを身をもって体験しました。特に毎日繰り返し使う画面のレスポンスが1秒遅れるだけでも、作業ストレスの原因となり、業務全体のパフォーマンス低下を招く場面もありました。Sansanのプロダクトは、名刺や請求書といったビジネスに欠かせない情報を扱うため、安定性と操作性の両立が非常に重要だと考えています。私自身は、ReactやTypeScriptによる非同期処理の最適化や、APIレスポンスのキャッシュ設計、UIの描画負荷軽減など、パフォーマンスと安定性の改善に取り組んできました。Sansanでの開発では、こうした経験を活かして「毎日安心して使える軽やかな操作体験」を実現したいです。単に機能を作るのではなく、使い手の気持ちに寄り添った設計を追求する姿勢で、プロダクト価値の向上に貢献したいと考え、志望いたしました。」
この志望動機では、技術力だけでなく「使う人の気持ちにどれだけ寄り添えるか」が大切な軸になります。
ユーザーが日々どんな操作をしていて、どこで不満を感じやすいか──その感覚を持っていることが、Sansanのプロダクト開発では強みになります。
具体的な改善経験や工夫した技術もきちんと交えて、自分が“どう役に立てるのか”を自然な言葉で伝えると、読み手にもしっかり響きます。
数字で語る必要はありませんが、エピソードにリアリティを持たせることを意識すると説得力が増します。型にはまりすぎず、自分の言葉で書くことが一番大事です。
障害に強い仕組みづくりで安心して使えるサービスにしたい
「前職ではクラウドサービスのインフラ運用を担当し、システム障害が発生した際の影響の大きさと、その対応スピードの重要性を実感しました。特に業務用システムでは、わずかな停止が大きな損失につながることから、常時安定して利用できる環境づくりが最優先課題でした。Sansanは、名刺や請求書などビジネスに欠かせない情報を管理・活用するサービスであり、ユーザーにとって「いつでも使えること」が大前提だと考えています。私はこれまで、可用性を高めるための冗長構成や、障害発生時のフェイルオーバー自動化、ログのリアルタイム監視による未然防止といった対策を実装してきました。Sansanにおいても、障害に強い基盤を整え、すべての利用者が安心して使い続けられるプロダクトづくりに貢献したいと考えています。単に技術を追求するだけでなく、ユーザー視点に立ち、見えないところで支えるインフラの信頼性を高める仕事に強いやりがいを感じています。」
障害対応やインフラ運用の経験は、どうしても技術面に偏りがちです。ただ、それだけでは読む人の心に響きません。
重要なのは「どんな困りごとを、どう解決してきたか」を実感をもって伝えることです。
Sansanがなぜ安定性を大切にしているのか、その理由を利用者の視点から語ることで、自分の志望動機に深みが出ます。
経験やスキルは「どう活かすか」まで描けてこそ、納得感のある内容になります。数字や実績も、押しつけがましくならないよう注意しましょう。
技術よりも人と仕事に向き合う姿勢を前面に出すことが、信頼につながります。
障害に強い仕組みづくりで安心して使えるサービスにしたい
「前職では金融業界向けの基幹システムのインフラエンジニアとして、24時間365日稼働を前提とした障害対策や復旧体制の構築を担当していました。特に重要視していたのは、障害を未然に防ぐ予兆検知と、万が一の際に迅速にサービスを復旧させるオペレーションの整備です。Sansanは、名刺管理や請求書処理といったビジネスの基盤を支えるサービスを提供しており、ひとたびトラブルが起これば顧客の業務に直結するため、強固で柔軟なインフラが不可欠だと考えています。私は、可用性の向上やシステムの冗長化、障害監視の自動化といった仕組みづくりに加え、SREの観点からサービス全体の信頼性を担保することに注力してきました。Sansanでも、これまでの経験を活かし、ユーザーがいつでも安心して使える環境をつくるために貢献したいと考えています。日々の安定稼働がプロダクトの価値を裏側から支えているという責任とやりがいを持って、障害に強いサービスづくりに尽力したいです。」
単に「障害に強い」と言うだけでは、どこかで聞いたような志望動機になってしまいます。
大切なのは、自分が関わった具体的な事例や取り組みを交えながら、Sansanという会社の提供価値にどんな視点で向き合っているかを伝えることです。
また、数字や改善策を挙げて客観性を持たせると説得力が増します。そのうえで、「なぜSansanなのか」「どんな貢献ができるのか」という2点が自然に読み取れるような流れを意識すると、グッと印象に残る内容になります。
あくまで主役は読んでいる採用担当者。その視点に立って、わかりやすく、そして熱意が伝わる表現を心がけましょう。
現場の声を製品にすぐ反映できる流れを強くしたい
「前職ではSaaSプロダクトの開発エンジニアとして、カスタマーサポートや営業から挙がる顧客の要望や課題を機能改善に反映する体制づくりに取り組んできました。しかし、開発と現場の距離が遠く、フィードバックが届くまでに時間がかかることが多く、結果としてユーザー満足度の向上に結びつきにくい状況に課題を感じていました。Sansanは「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションのもと、実際の利用者の声を重視し、現場からのフィードバックを迅速に製品に反映する姿勢を持っている点に大きな魅力を感じました。私自身も、仕様調整やプロトタイプ検証を現場の担当者と協力しながら行い、スピーディに改善を回す開発スタイルにやりがいを感じてきました。Sansanにおいても、現場と開発が一体となり、価値あるプロダクトをより早く世の中に届ける体制を支える一員として貢献したいと考えています。変化に柔軟に対応しながら、利用者に寄り添った開発を継続的に行っていきたいです。」
単に「現場の声を大事にしたい」と書くだけでは、ありきたりな印象で終わってしまいます。
大切なのは、なぜ自分がそう感じたのか、どんな場面で課題を実感し、どのような行動を取ってきたのかをしっかり描くことです。
Sansanの開発スタイルに共感した理由も、単なる理想論ではなく、自分の経験と地続きで語ることで説得力が増します。
スピード感や連携の重要性をどう捉えているか、実例を交えて言葉にするのがポイントです。
志望動機作成に欠かせないSansanが求める人材の特徴

Sansanに就職・転職を目指す際には、企業がどのような人材を求めているのかを理解することが、志望動機を効果的に伝えるための第一歩です。
そこで「志望動機作成に欠かせないSansanが求める人材の特徴」をまとめました。
これらの特徴に自分の経験や想いを重ねることで、より説得力のある志望動機を作成できます。求める人物像ごとのポイントを詳しく解説していきます。
仕事に本気で向き合い情熱を注げる人
Sansanでは「新しい当たり前をつくる」ことを掲げ、日々の業務に真正面から向き合える人を求めています。ただ与えられたタスクをこなすのではなく、自ら目的を考え、熱意をもって手を動かせる姿勢が重視されています。
実際、Sansanが大切にしている価値観を言語化した「バリューズ」の一つに「仕事に向き合い、情熱を注ぐ」という言葉が明記されており、これは同社が人材採用において大切にしている価値観のひとつです。
たとえば、過去に担当していた業務で、自分から仕組みを見直して改善を提案した経験がある方や、プロジェクトを推進するなかで周囲を巻き込み、成果にコミットし続けたエピソードを持っている方は、Sansanの目指す人物像にかなり近いと言えるでしょう。
何気ない日常業務のなかにこそ、自分の熱意を示せる場面は多くあります。目の前の仕事に心から向き合い、小さな変化を積み重ねていく姿勢。その誠実な努力こそが、Sansanが大切にしている「出会いからイノベーションを生み出す」という考え方とも深く結びついています。
顧客を新しい価値へそっと導ける人
「どうすれば目の前の顧客が“気づいていない課題”に気づけるだろう」。Sansanが求める人物像には、そんな繊細さと先回りの視点を持てる人が挙げられています。顧客の言葉通りのニーズに応えるだけでなく、「その先にある本質的な価値」を一緒に見つけていく。それがSansanで大切にされている姿勢です。
たとえば以前、名刺管理に悩むクライアントに対し、私は単にツール導入を勧めるのではなく、「この情報が営業現場でどう生きるか」「どうすればチーム全体の提案力が上がるか」といった視点でサポートしました。結果的に、名刺は“ただの情報”から“戦略的な資産”に変わり、顧客の営業成果にもつながりました。
Sansanでは「Lead the Customer(顧客を導く)」という考え方を掲げており、公式サイトでもその価値観が明確に示されています(出典:Sansan公式企業理念)。直接的な押し付けではなく、あくまで“そっと寄り添い、自然と導いていく”スタンスが評価されるのです。
志望動機としてこの姿勢を語るなら、「ただ売る人」ではなく「顧客の未来像を一緒に描ける人」を目指してきた過去のエピソードを添えると、Sansanとの親和性がより伝わるはずです。
意思と意図を持って自ら判断し動ける人
Sansanが求めているのは、「自分の頭で考え、迷いながらでも一歩を踏み出せる人」です。マニュアル通りに動くのではなく、「この判断にはどんな意味があるのか」「なぜこの行動を選ぶのか」を自分なりに考え、行動に移す力が重要とされています。
実際、Sansanのコーポレートサイトにも「Lead the customer(顧客を導く)」や「Face your mission(使命に向き合う)」といった価値観(Philosophy)が明確に記されており、その中には“主体性”を持った姿勢が求められていることがにじんでいます。
たとえば、以前担当していたプロジェクトで、「誰かの指示を待つ前に、まず仮説を立てて提案を出す」ことを習慣にしていた経験があれば、それはまさにSansanが評価するタイプです。
実際に「提案内容をもとに別チームも動き出し、結果的にプロダクト改善に直結した」というような成果があるなら、志望動機に深みを与えるエピソードになります。
型にはまった表現よりも、自分の判断と行動にどう意味があったかを素直に語る。それがSansanに伝わる“らしさ”をつくります。
失敗から学び成長し続ける姿勢がある人
Sansanでは、一度の失敗で評価が下がるような環境ではありません。むしろ、挑戦の過程で生じたつまずきをどう振り返り、次にどんな工夫を重ねられるかに注目しています。
企業のインタビュー記事でも「失敗を必要以上に恐れない組織づくり」を進めていることが紹介されており、行動した先に得られる学びにこそ価値を置いていることが分かります(参考:Sansan公式インタビュー)。
たとえば、仕事の中で期待した成果が出なかった経験があったとしても、その場面をどう分析し、改善案を組み立て、次の挑戦に反映させたかを語れる人は、Sansanが求める人物像に近いと言えます。大切なのは「失敗しないこと」ではなく、経験から「成長し続ける姿勢」を持っているかどうかです。
志望動機を伝える際には、過去の挫折や反省点を隠す必要はありません。その経験をどう糧にしてきたのか、言葉で説明できることが、Sansanを目指す上で大きな強みになります。
変化を恐れず挑戦し続けられる人
「ずっと同じやり方では通用しない」──Sansanが本気で求めているのは、そんな現実をまっすぐ見つめて、変化の中にチャンスを見いだせる人です。
たとえば、Sansanが掲げる行動指針(Sansanのカタチ)の中には「Don’t fear change, and challenge yourself(変化を恐れず、挑戦していく)」という言葉があります。
これは単なるスローガンではありません。実際に社内では、慣れた業務の枠を越えて自ら提案し、未知のプロジェクトに飛び込むような文化が根づいています(※Sansan公式サイトより)。
実際に、たとえば前職で業務改革があり、新システムの導入が決まったとき、「誰かやるだろう」と他の人が足を止めるなか、率先してその新しい仕組みに挑戦した経験があれば、それこそがSansanが求める“挑戦する人”です。
志望動機を考えるなら、「過去にどんな変化と向き合い、どう前に進んだか」を具体的に振り返ってみてください。その経験がきっと、Sansanの目に留まる強いメッセージになります。
志望動機づくりの参考になるSansanで働く魅力や強み

志望動機を作成するうえで、Sansanで働く魅力や強みを理解することは非常に重要です。
企業の価値や文化、提供しているサービスの特徴を知ることで、より説得力のある志望理由を伝えることができます。
ここでは、Sansanの代表的な魅力や強みを具体的に紹介しながら、志望動機に活かせるポイントを明らかにしていきます。
名刺管理で業界を先導する主力サービスの強み
Sansanといえば、名刺管理の領域で確かな存在感を築いている会社です。法人向けサービス「Sansan」は、名刺情報をただスキャンして保管するだけのツールではありません。
名刺やオンラインでのつながりをまとめて管理し、営業活動に使える“人のネットワーク”として企業に還元できる点が大きな特徴です。
名刺データは99.9%という精度でデジタル化され、社内で共有できる資産へと変わっていきます。実際に導入企業は多く、10年連続でシェアNo.1、シェア率81.6%という数字は信頼の証といえます(出典:ニュースリリース)。
こうした「当たり前の仕事を、より前に進める仕組み」を提供しているところに、このサービスの強さがあります。
志望動機に落とし込むなら、「名刺を情報資産として活用し、出会いを価値に変える」という考え方に惹かれたことを、自分の経験と重ねて語ると説得力が出ます。
EightやBill Oneなど複数事業で成長できる環境
Sansanに惹かれる理由の一つに、「ひとつの会社の中で多彩な事業に関われる」という魅力があります。名刺管理の印象が強い方も多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。
たとえば、名刺管理サービス「Sansan」に加えて、営業支援アプリの「Eight」や、請求書をデータ化して経理業務を効率化する「Bill One」など、事業の幅は年々広がっています。公式のIR資料によれば、同社は現在、「Sansan/Bill One事業」と「Eight事業」という2つの柱でビジネスを展開中。
これにより、営業DXから経理DX、さらにはビジネスSNS領域まで、多様なフィールドでのチャレンジが可能になっています。
実際に、Eightは中小企業を中心に導入が進んでおり、チームで名刺情報を共有して営業活動に活かす仕組みが評価されています。一方、Bill Oneは請求書処理の自動化という切り口で、多くの企業の経理業務を支える存在へと成長しています。
こうした実例を見ても、Sansanが単なる「名刺管理の会社」ではないことが分かるでしょう。
ひとつの職種にとらわれず、複数の事業をまたいで経験を積める。しかも、それが社会課題の解決につながる──そんなキャリアパスを望む人にとって、Sansanはまさにうってつけの職場だと思います。
志望動機を語る際には、こうした環境の豊かさや、自分がどの事業に関心を持っているかを具体的に伝えると、説得力がグッと増します。
出会いから新しい価値を生むはっきりした目的
Sansanという会社に惹かれる理由のひとつは、「出会いからイノベーションを生み出す」という、非常に人間味のあるミッションにあります。これは単なるスローガンではなく、企業としての芯をなす考え方です。
Sansanは、名刺管理の枠にとどまらず、人と人の出会いが持つ可能性そのものに価値を見出し、それをビジネスの現場でどう活かしていくかを本気で考えている会社です。実際に公式サイトでは、「出会いの連鎖が社会を前進させる」と明言しています。
この言葉の裏側には、業務の効率化だけでなく、信頼やつながりといった目に見えにくい価値を大切にしている姿勢がにじんでいます。
たとえば、学生時代に他学部のメンバーと協力しながらサービス企画を行った経験がある方なら、その「出会い」から何か新しいものを生み出せた体験があるはずです。そうした実感を持つ人にとって、Sansanの目指す方向はきっと共感できるはずですし、自分の経験が仕事にも活かせると感じられるのではないでしょうか。
このように、Sansanが掲げる目的はとても明確です。そして、その目的に自分の価値観が重なると感じられたなら、それは立派な志望理由になります。表面的な企業イメージではなく、企業が大事にしている「意味」に自分の歩みを重ねること。それこそが、心に届く志望動機につながっていくのです。
家賃補助と子育て支援で生活を安心して働ける
「働きやすさって、やっぱり生活の安定から始まると思うんです」。Sansanの福利厚生を調べていて、そう感じた人は多いのではないでしょうか(出典:カルチャー)。
渋谷や表参道から電車で2駅以内という、都心の便利なエリアに住むだけで家賃補助が受けられる「H2O制度」や、小さなお子さんがいる家庭には嬉しい育児支援「OYACO」など、社員の暮らしに寄り添った制度がきちんと整っています。
実際、Sansanの公式サイトを見ると、働く時間だけでなく“暮らす環境”にも本気で向き合っていることが伝わってきます。
参考までに、家賃補助の対象となるのは、表参道・渋谷から2駅以内に居住している場合(月3万円支給)、さらに「近くに住むことで生まれる偶然の出会いや対話が、新たな価値を生む」という思想に基づいているというのも、Sansanらしい考え方です。
「育児中でも、キャリアを諦めずに働ける会社を探していた」「通勤の負担を減らして、仕事にもっと集中したかった」──そんな自分自身の経験を志望動機に添えることで、福利厚生とライフスタイルを結びつけた、説得力あるアピールができます。
Sansanを志望する理由に迷っているなら、一度、自分の「理想の働き方」と照らしてみてください。その中にきっと、「安心して働ける理由」が見つかるはずです。
海外拠点と連携してグローバルに挑戦できる
Sansanに惹かれた理由のひとつが、「海外とつながる仕事ができる環境が整っている」という点です。
たとえば、シンガポールにはすでにアジア統括拠点があり、2022年にはフィリピンのセブに開発拠点が設立されました(出典:ニュースリリース)。さらに、2024年にはタイ・バンコクに現地法人を立ち上げるなど、東南アジアを中心にグローバル展開を加速させています(出典:ニュースリリース)。
これらの動きは、単なる海外進出にとどまりません。日本のチームと海外拠点が密に連携しながらサービスを育てていく体制があり、言葉や文化の壁を越えたコラボレーションが生まれているのです。
実際に、私は大学時代に交換留学を経験し、多様な価値観に触れる中で「いつか海外の仲間と共にものづくりをしたい」という思いが芽生えました。Sansanのように実際の海外展開実績があり、現地での事業拡大を本気で進めている会社なら、自分の経験も活かしながら貢献できると強く感じました。
「sansan 志望動機」と検索する人の多くは、企業の将来性や働く環境を重視しているはずです。そうした人たちにとって、海外チームと一緒に働けるチャンスがあるSansanの環境は、間違いなく魅力的です。
逆にSansanに応募する志望動機としてダメな例5選
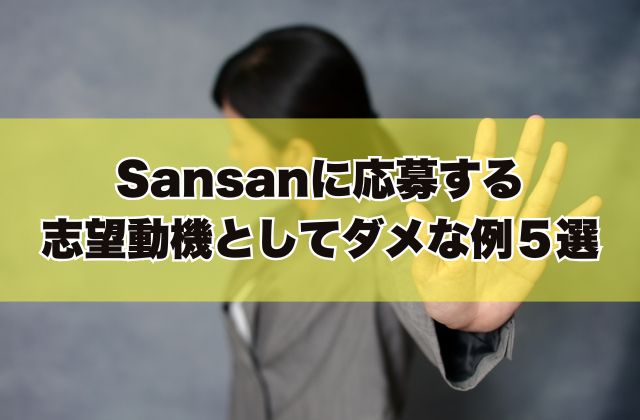
Sansanに応募する際は、企業理念や事業内容への理解が求められます。
そこで重要なのが「逆にSansanに応募する志望動機としてダメな例5選」を知ることです。
よくある失敗例を把握しておけば、自分の志望動機が的外れにならず、評価されやすい内容に仕上げやすくなります。.
次に紹介する5つのNGパターンをもとに、避けるべき表現や考え方を確認しましょう。
給料が高そうだからとだけ伝える志望動機
「給与が良さそうだから」。
正直な気持ちとしては理解できますし、それを魅力に感じてSansanを目指す人も多いはずです。でも、それだけを理由にした志望動機は、選考では響きません。
Sansanが大切にしているのは、「出会いからイノベーションを生み出す」という考え方。そのビジョンに共感し、自分もそこで何かを生み出したい──そんな想いを持った人を求めています。給与や待遇は大事ですが、それ以上に「何のために働くのか」が問われます。
たとえば、「給与が高そうで魅力的だったから志望しました」と話してしまうと、どこか受け身に聞こえてしまいますし、「それなら他の会社でもいいのでは?」と受け取られてしまうかもしれません。
そうではなくて、「Sansanの“出会いを資産に変える”という事業に共感した」「自分の○○の経験を生かして、その価値をさらに広げたい」といったように、自分の考えや体験と重ねながら伝えることで、初めて“志望動機”になります。
条件面に惹かれたとしても、それをきっかけにSansanのどんなところに価値を感じたのか。どうして他社ではなくSansanだったのか。その“なぜ”を自分の言葉で語れるかどうかが、合否を分けるポイントになります。
有名企業だからと何となく志望しただけ
Sansanという名前を聞いて、ピンと来た方も多いかもしれません。実際、知名度は高く、テレビCMや街中の広告で見かけることも少なくありません。しかし、「有名だから」「なんとなく安心感があるから」といった理由だけで志望してしまうのは、採用選考では大きなマイナスになります。
Sansanの採用サイトを見ても、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションや、社員が自ら考えて動くカルチャーが重視されていることがはっきりと伝わってきます。つまり、企業が目指している未来や、自分がその中でどう活躍できるかを語れなければ、志望動機としては不十分なのです。
たとえば、「貴社は有名企業なので志望しました」と書いたところで、それが他社でも通用する内容である限り、Sansanを選んだ意味は見えてきません。
一方で、「名刺を起点にしたデータ活用で働き方を変えている点に惹かれました。自分も営業経験を活かして、企業の情報活用を支援したいです」といった表現なら、なぜSansanなのかが伝わります。
選考を突破したいなら、「知名度」ではなく「共感」と「貢献」に軸を置いた言葉を。名前ではなく、姿勢と価値観で語ることが、良い志望動機への第一歩です。
福利厚生の良さだけを理由にすると、評価されづらい
「福利厚生が整っているからSansanに入りたい」──気持ちはよく分かりますが、それだけでは志望動機としては不十分です。
採用担当が見ているのは、制度の魅力に惹かれているかどうかよりも、「この会社で何をしたいのか」「なぜSansanなのか」という視点です。Sansanが掲げる“出会いからイノベーションを生み出す”というミッションにどこまで共感しているか。そのうえで自分のスキルや想いがどうつながるのかが、志望動機の説得力を左右します。
たとえば「家賃補助が魅力的だったので志望しました」とだけ伝えたとしたら、あなたでなくてもいいと思われかねません。でも、「営業現場の非効率を変えたい。その思いとSansanの事業が重なった」と語り、そのうえで「長く働ける制度が整っているからこそ、自分の力を存分に発揮できそうだ」と付け加えれば、納得感がまったく違います。
福利厚生は大切です。ただ、それは“手段”であって“目的”ではありません。だからこそ、志望動機に組み込むなら、自分の目指す働き方や実現したい未来とセットで語ることが大切なのです。
他社でもよい内容でSansan志望の必然性がない
「どの企業にも当てはまりそうな志望動機だと、Sansanで働きたい理由としては弱いです」と採用担当者が語ったとしたら、少しドキッとするかもしれません。実際、多くの企業が「自社らしさ」を見抜こうとしています。Sansanも例外ではなく、「なぜうちなのか?」を重視しています。
Sansanが掲げる「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションは、単なるスローガンではありません。名刺管理という一見地味な領域から、企業同士の出会いや人のつながりを可視化し、新たなビジネスの種を生み出してきた実績があるからこそ、そこに共感し行動できる人材を求めているのです。
たとえば「御社の働きやすそうな環境に惹かれました」という志望理由は、一見ポジティブですが、他の企業でも通用してしまいます。
その代わりに、「名刺を通じて企業間の関係を“資産”に変えるという考え方に驚きました。人の出会いが持つ力を信じている自分にとって、この仕組みを広めることに本気で向き合いたいと感じたのが、Sansanを選んだ理由です」といった言葉なら、きっと採用担当者の心に届くはずです。
Sansanの強みは、ただのIT企業ではなく、“社会との接点をつくる会社”であること。志望動機にも、その感覚をきちんと込めることで、他社との違いを明確に伝えられます。
入社後に何をするかが具体的に語られていない
「御社の理念に共感しました」「サービス内容に惹かれました」──一見問題なさそうに見える志望動機ですが、実はここに落とし穴があります。
Sansanのように、明確なミッションを掲げて成長を続ける企業では、「共感しました」の先にあるアクションが非常に重要です。ただ好印象を持った、興味が湧いたという理由だけでは、他の応募者と差がつきません。
実際、Sansanの採用ページでも「出会いからイノベーションを生み出す」という目的に、自らの行動でどう関わるかを考えられる人を求めています。
たとえば、「名刺管理サービスが便利そうだった」と伝えるよりも、「営業職として、名刺データを活用し顧客ごとの課題に応じた提案を行い、営業チーム全体の成果向上に貢献したい」と語った方が、入社後の姿が明確に伝わります。企業側も、そこにリアリティや期待感を感じるのです。
志望動機において大切なのは、「入ったらどう動くか」がしっかり描かれているかどうか。自分の過去や思いだけで終わらせず、Sansanというフィールドで何を起こしたいのかまで踏み込むことが、面接突破のカギになります。
Sansanに応募する志望動機を踏まえた面接対策のポイント

Sansanに応募する志望動機を踏まえた面接対策のポイントを意識することで、面接官に伝わる表現ができるようになります。
面接では「なぜSansanなのか」「入社後に何を実現したいのか」が特に重視されます。
そのため、志望動機で触れた内容を面接でも一貫して説明できるよう整理しておくことが大切です。
ここからは、面接の場で意識したい具体的なポイントを5つ紹介します。今後の面接対策の参考にお役立てください。
志望動機は「出会いからイノベーション」と結ぶ
Sansanを志望する理由を語るときは、同社が掲げる「出会いからイノベーションを生み出す」という考えを、自分の経験と結びつけて説明することが重要です。
なぜなら、Sansanではこの理念が単なるスローガンではなく、事業や日々の仕事の指針として共有されているからです。
例えば、学業やアルバイトで人と協力して新しい価値が生まれた体験があるなら、「人との出会いをきっかけに成果が生まれた」具体的な場面を思い出してみてください。
ミーティングで誰かの視点に気づかされて方向性が変わった、相手の強みがプロジェクトを動かした、といった小さなエピソードでも構いません。その経験と、Sansanが名刺や顧客接点のデータ化を通してビジネスに新しい力を生み出そうとしている姿勢を重ねれば、志望理由に自然な説得力が生まれます。
つまり、「自分は人との出会いをきっかけに何を感じ、どんな成果につなげたのか」を軸に据え、それがSansanでどう活きるのかを語ることが大切です。
Sansanと他社の違いに触れて志望理由を深める
「なぜSansanを選んだのか」を伝えるとき、ほかの企業ではなくSansanでなければならない理由がきちんと伝わると、面接官の印象はまるで変わります。
Sansanの大きな特長は、単なる名刺管理にとどまらず、「出会い」をビジネスの資産として捉え、その価値を最大限に引き出す仕組みを提供していること。
たとえば、同社の法人向けサービス「Sansan」では、名刺だけでなく、メール署名やWebフォームから取得した情報も一元化し、営業活動の可視化に活用できます。こうした発想は、ほかのIT企業でも見かけるものではありません。
具体的に、志望理由を説明する一例を示すと、
個人的に、大学でマーケティング活動に携わっていた際、イベントで交換した名刺を活かしきれず、貴重なつながりを失ってしまった経験があります。Sansanのサービスを知ったとき、「こんなふうに“出会い”を武器にできたらどれほど良かっただろう」と感じたのが、正直なところです。
加えて、Sansanは国内外に拠点を持ち、グローバル展開にも積極的。海外と連携しながらプロダクトを育てていける点にも大きな魅力を感じました。
このように、自分の体験と重なる部分や、他社とは異なるSansanの強みを志望動機に織り交ぜることで、志望理由に“深み”が生まれます。
プロダクトを実際に使い感想と改善案を述べる
Sansanの選考で強く印象に残る志望動機を伝えるには、自分の言葉で「プロダクトをどう感じたか」を語ることがとても大切です。単なる好印象ではなく、使用したうえで見えた課題や改善点まで触れられると、採用側にも本気度が伝わります。
たとえば、一例をお示しすると、
私は大学のゼミで企業と連携するイベントに参加し、参加者から名刺をいただく機会が何度かありました。ただ、その名刺を手入力でスプレッドシートにまとめる作業が思いのほか大変で、時間もかかり、整理もうまくいかないままになってしまいました。そんな経験があったからこそ、「Sansan」というプロダクトを知ったときは衝撃でした。名刺をスマホで撮るだけで、正確なデータとして取り込まれ、社内で共有できる仕組みがある。正直「こんなに楽になるのか」と感じました。
実際に無料版アプリを試したところ、スキャンの精度が高く、登録もスムーズでした。ただ一方で、初めて使う人にとっては「次に何をすればいいか」が少しわかりづらく、簡単なチュートリアルや初回ガイドがもう少し丁寧であれば、さらに使いやすくなると感じました。
このように、実体験を通じて得た気づきや改善のアイデアを伝えることは、「貴社のプロダクトに関心がある」という言葉以上の熱意を示す方法になります。志望動機を語る際は、体験ベースで感じたことを、自分なりの言葉で真っすぐに届けることが何よりも大切だと実感しています。
顧客の課題をどう解決したいかを具体的に示す
志望動機の中で「顧客の課題をどう解決したいか」を語る人は多いですが、その内容にリアリティや深さが伴っているケースは意外と少ない印象です。表面的な「お客様に貢献したい」では、どの会社でも言えてしまいます。
だからこそ、Sansanを志望するなら、「どんな課題が、なぜ発生しているのか」「自分ならどう関われるか」を、自分の体験や考えと結びつけて語ることが重要です。
たとえば、Sansanが提供する法人向けサービスでは、名刺情報・メール署名・人脈・営業履歴といった多様な接点を1か所に集約し、営業の見落としや機会損失を防ぐ仕組みを構築しています。これは、公式のIR情報にも明記されている同社の核となる価値です。
この機能を実際に知っていると、たとえば「名刺をもらってもExcel管理で止まってしまっていた」「チーム内で誰がどの顧客と接点を持っていたか不明だった」といった、リアルな“あるある”に気づけるはずです。
だからこそ、「顧客が抱えている“出会いを機会に変えられない”という課題に対し、Sansanの仕組みをどう活用し、どの場面で改善が起きるのか」を自分なりの視点で語れると、面接官にも伝わります。そこまで踏み込んで話せる人は多くありません。
Sansanのようにプロダクトの思想と課題解決が直結している企業では、「自分ならどう価値を届けられるか」を言葉でなく、具体的なシーンや体験に置き換えて語れることが、大きな差になります。
逆質問で事業や文化への関心と熱意を示す
Sansanの面接で「最後に何か質問はありますか?」と聞かれたとき、準備しておいた逆質問の内容によって、印象は大きく変わります。ただ義務的に質問をするのではなく、自分がこの会社の何に惹かれたのか、どこに本気で興味があるのかを、率直にぶつける時間だと考えてみてください。
Sansanでは「出会いからイノベーションを生み出す」という独自のミッションを掲げています。この言葉が単なるスローガンではなく、日々の業務にどう根付いているのか。そのリアルな実感を社員の言葉で聞くことができれば、面接の場で一気に深い対話に入れます。
実際、面接体験談では「若手がどこまで裁量を持って動けるのか」「ミッションが行動にどうつながっているか」などを質問し、印象が良かったという声も上がっていました。
たとえば、「最近、社内で“出会いからイノベーション”を体現したような取り組みがあれば教えてください」と聞けば、事業理解の深さが伝わりますし、「若手の意見が事業に反映された事例があれば、ぜひ伺いたいです」と続ければ、文化への関心も自然に示せます。
逆質問は、自分の考えや価値観を“問いかけ”というかたちで伝えられる唯一の機会です。Sansanという企業に本気で入りたいのであれば、事業や文化へのリスペクトと好奇心を、しっかり言葉にして届けることが何より大切です。
Sansanをはじめ大手IT企業から内定を勝ち取る就活支援サービス
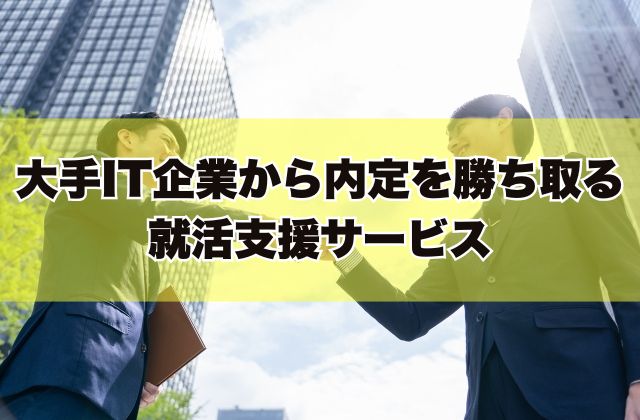
IT業界でキャリアを目指すなら、特に「大手IT企業を志望している」「エンジニア・技術系で活躍したい」という方には、『レバテックルーキー』の活用が非常に有益です。
その理由は、運営母体の実績・求人企業の質・サポート体制のすべてが“ITエンジニア志望者向け”に特化しているためです。
たとえば、同サービスでは内定実績として「最短2週間で内定」「実装経験を条件とした学生の内定率85%以上」という数字が公式に出されています(※公式サイト調べ)。
具体的には、レバテックルーキーでは、ITエンジニア就活を熟知したアドバイザーが、志望者ひとりひとりのスキルや希望をヒアリングしたうえで、8,000社以上の企業から自分に合った求人を紹介しています。
しかも、プログラミング未経験であっても相談できる体制が整っており、文系出身の方でも“エンジニアとして就職する選択肢”を実現している点も評価されています。
だからこそ、Sansanへの志望動機を検討中で「IT/技術職で働きたい」「自社開発やサービス企画にも関わりたい」という方には、レバテックルーキーを通じて関連企業の選択肢を広げつつ、志望先であるSansanのような企業にしっかり自分の強みを活かせる準備を並行して進めると、勝率が高まります。
ファーストキャリアをSansanをはじめ大手IT企業と決めている方は、ぜひご活用ください。
Sansanに転職したい人向けの転職支援サービスおすすめ3選
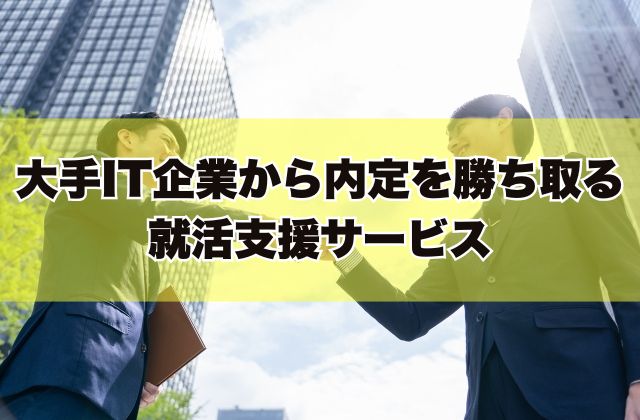
Sansanに転職したい方は、志望動機づくりや企業理解に加えて、非公開求人や面接対策のサポートを受けられる転職支援サービスを活用することが近道です。
とくにIT業界に詳しいエージェントを選ぶと、Sansanの選考傾向や求められる人物像に沿ったアドバイスを得られます。
ここでは「Sansanに転職したい人向けの転職支援サービスおすすめ3選」として、安心して相談できるサービスを紹介します。
【転職支援1】マイナビIT AGENT
Sansanのような成長性の高いIT企業を目指すなら、『マイナビIT AGENT』の活用を一度真剣に検討してみてください。
というのも、このエージェントはIT・Web業界に特化しており、紹介される求人の質やマッチ度が他とは一線を画しています。
担当するアドバイザーも業界事情に精通しており、「この企業は今、どういう人材を求めているか」といった情報までリアルに把握しているのが強みです。
実際、サイト上でも社内SE、インフラ、開発エンジニアといった多職種の求人が並んでおり、経験が浅めの人向けの案件も豊富(※公式サイトより)。
書類添削や面接対策の支援も無料で受けられるため、「Sansanで働きたいけど、何をどう準備すればいいかわからない」という人にとって、かなり心強い味方になるはずです。
特に印象的なのは、選考対策の質。単に形式を整えるのではなく、自分の経験を「Sansanが重視する価値観」とどう結びつけるかまで一緒に考えてくれるので、志望動機の説得力が格段に増します。
改めて『マイナビIT AGENT』の特徴・利用するメリットをまとめると、
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営のサービス
- 全国の大手上場企業から人気ベンチャーまで幅広い求人の紹介が可能
- 特に関東エリアの求人を網羅!一都三県の優良企業の求人が豊富
- 応募書類の準備から面接対策まで、親身な転職サポート
- IT業界出身のキャリアコンサルタントがニーズにマッチした転職を提案
転職活動は情報と準備で結果が大きく変わります。もし本気でSansanを狙うなら、信頼できるプロと並走することが近道になると断言できます。
【転職支援2】レバテックキャリア
SansanのようなIT系企業への転職を考えるなら、『レバテックキャリア』の活用は非常に有効です。
理由は明快で、レバテックキャリアはIT・Web業界に精通したアドバイザーが、あなたの経歴や希望に沿った求人を丁寧に提案してくれるからです。
このサービスの特徴は、業界特化型ならではの濃いサポート体制。たとえば職務経歴書の添削や面接準備はもちろん、企業ごとの選考傾向を踏まえた具体的なアドバイスも受けられます。
実際、レバテックキャリア経由で年収アップやキャリアの幅を広げた方も多く、特に20代後半から30代前半のIT職経験者に支持されています。
Sansanが求めるようなエンジニア職や社内SE、プロダクト開発に携わるポジションも多く、非公開求人の紹介も期待できます。キャリアの方向性がまだ明確でなくても、対話を通じて整理してくれるため、情報収集の第一歩として相談してみるのもおすすめです。
改めて『レバテックキャリア』の特徴・利用するメリットをまとめると、
- ITエンジニアが利用したい転職エージェントNo.1
- 求人紹介だけでなく開発現場のリアルな情報も把握可能
- IT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが徹底サポート
- 内定率を上げる企業別の面接対策・アドバイスも実施
- エンジニアとしての市場価値診断(年収診断)も受けられる
「今の働き方に迷いがある」「もっと自分の技術を活かせる場所を探したい」──そんな想いが少しでもあるなら、一度レバテックキャリアのサポートを受けてみてください。
転職活動が前向きに進み始めるきっかけになるはずです。
【転職支援3】社内SE転職ナビ
社内SEとして落ち着いた環境で長くキャリアを築いていきたい──そんな方には『社内SE転職ナビ』が頼れる味方になります。
このサービスは、名前の通り社内SEやITインフラ職など“社内のIT部門”に特化した転職支援サイトです。派遣や常駐ではなく、自社内で腰を据えて働きたい人には特におすすめです。
特徴としてまず挙げたいのは、取り扱う求人の“濃さ”です。自社開発を行う企業や、情報システム部門を持つ大手企業の求人が豊富で、非公開案件も多数。
しかも、担当キャリアコンサルタントがしっかりヒアリングを行い、単なるスキルマッチではなく、働き方や社風との相性まで見たうえで企業を紹介してくれます。
実際に利用した方の声を見ると「客先常駐ばかりだった自分でも、初めて“社内SE”としての転職が決まった」「希望した働き方と年収が両方叶った」など、満足度の高い感想が多く見られます。
丁寧な書類添削や企業ごとの面接対策にも定評があり、初めての転職でも安心感があるのもポイントです。
改めて『社内SE転職ナビ』の特徴・利用するメリットをまとめると、
- 10,000件以上の社内SE求人を保有し、多種多様な企業・ポジションから選べる!
- 入社後の定着率96.5%を誇り、求人と応募者のマッチング精度が高い!
- IT業界に詳しいコンサルタントが面談・書類添削・面接対策などを無料でサポート!
もしSansanのような事業会社で、サービスを支える立場として活躍したいと考えているなら、一度相談してみる価値はあるでしょう。
単に求人を紹介するだけでなく、キャリアの方向性まで一緒に考えてくれるので、「社内SEとしてどんな未来を描きたいか」を整理したい方にもぴったりです。
【Q&A】Sansanへの志望動機に関するよくある質問

最後にSansanへの志望動機に関するよくある質問をまとめました。
よくある疑問を具体的に解消しながら、面接官に伝わる魅力的な動機の作り方や答え方を解説します。
就活でSansanは難易度が高いですか?
結論から言えば、Sansanの選考はやや難しめです。
法人向け名刺管理サービスで長年トップシェアを維持しており、知名度も高いため、そもそも応募母数が多くなりやすい会社です。そのうえ、新卒採用では複数回の面談を通して、ミッション理解や価値観の相性を丁寧に見られます。準備不足のまま挑むと、言葉が浅くなりやすいところが難しさにつながります。
だからこそ、Sansanの志望動機では、単なる「サービスが良い」ではなく、「その価値を自分がどう広げていきたいのか」まで描けると一気に強くなります。
Sansanの面接スタイルは圧迫面接?
「圧迫」というより、落ち着いた対話の中で考えを深堀りされる面接が多い印象です。
最終面接は対面で行われることが多く、相手の言葉よりも“姿勢”を見ているように感じられます。ミッションである「出会いからイノベーションを生み出す」について、どれほど自分の体験とつなげて話せるかが鍵になります。
たとえば「なぜこの価値に自分は惹かれたのか」「どの場面でそれを感じたのか」をエピソードとして手渡すように話すと、表情や空気感も含めて伝わりやすくなります。
Sansanへ入社する理由はどう伝える?
ポイントは、「自分が実現したい価値」をSansanの事業と接続して話すことです。
同社は複数のプロダクトで、社会の非効率をデータ化によってほどいていこうとしています。なので、「なぜSansanでなければいけないのか」を語る際には、事業のどの課題に関わり、どんな改善や提供価値を届けたいかまで触れると深みが出ます。たとえば「Bill Oneで請求処理の負担を軽くし、時間を生み出す支援をしたい」という形です。
意志と役割が結びついた動機は、自然と伝わり方が変わります。
Sansanへの転職軸は何を重視すべき?
Sansanへ転職を考えるなら、「どのような価値づくりに関わりたいか」と「どのフィールドで成長したいか」を軸に据えるのがおすすめです。
Sansanは名刺、契約書、請求書といったアナログな情報をデータ化し、複数のサービス同士で価値をつなげています。“SaaS × 業務効率化 × データ活用”という領域で、事業間の連携による成長の余地が大きい会社です。
自分のキャリアに「顧客価値を形にするプロセスを身につけたい」という視点があれば、この環境は相性がいいと言えます。
Sansanの最終面接で落ちるのはなぜ?
最終面接でつまづくケースは、「言っていることは正しいけれど、自分の中で消化しきれていない」状態のときが多いです。
つまり、志望動機が一般論に寄りすぎていたり、入社後の役割のイメージが曖昧だったりする状況です。最終面接は、互いに長く働くイメージをすり合わせる時間でもあります。
経験・行動・成果・そこからの学びを“簡潔に、自分の言葉で”話せるかが重要になります。背伸びせず、実感のある言葉にまとめ直して臨むと、印象が大きく変わります。
まとめ:Sansanへの志望動機例文を新卒・中途に分けて徹底解説
Sansanへの志望動機例文を新卒・中途に分けて徹底解説してきました。
改めて、Sansanへの志望動機作成時のポイントをまとめると、
- Sansanの志望動機は「出会いからイノベーション」を軸にまとめると説得力が増す
- 他社との違いを理解し、自分がなぜSansanで働きたいのかを具体的に語ることが重要
- Sansanのサービスやプロダクトを実際に触れて感想と改善提案を伝えると評価されやすい
- 顧客の課題に対して自分がどう貢献できるかを明確に示すことが信頼につながる
- 面接では逆質問を通して事業理解や文化への共感をアピールすることで熱意を伝えられる
「Sansanへの志望動機」を作成する際は、理念や事業内容を理解した上で、自分の経験や価値観とつなげて語ることが大切です。
プロダクトを使った体験や、自分がどのように企業や顧客に貢献できるかを明確に言語化することで、面接官に「一緒に働きたい」と思わせる志望理由になります。