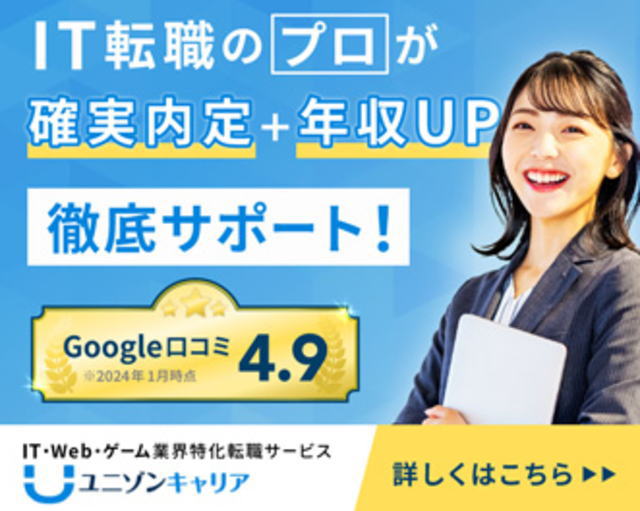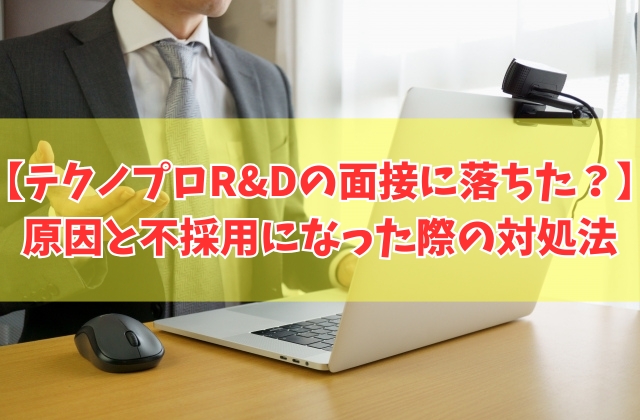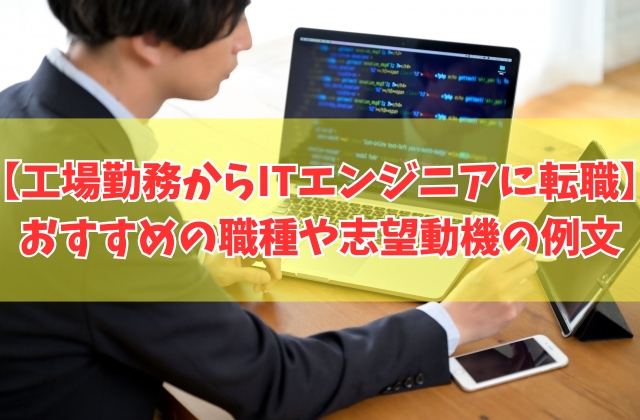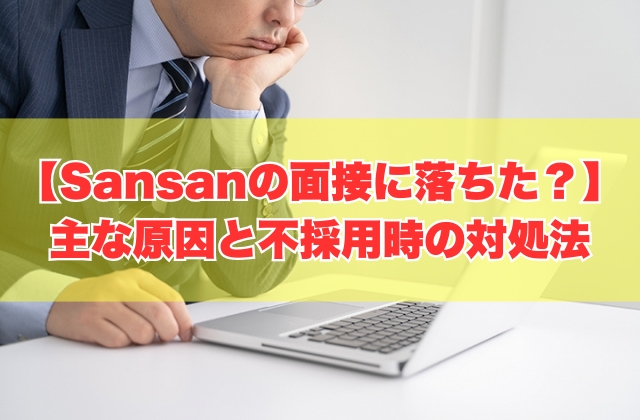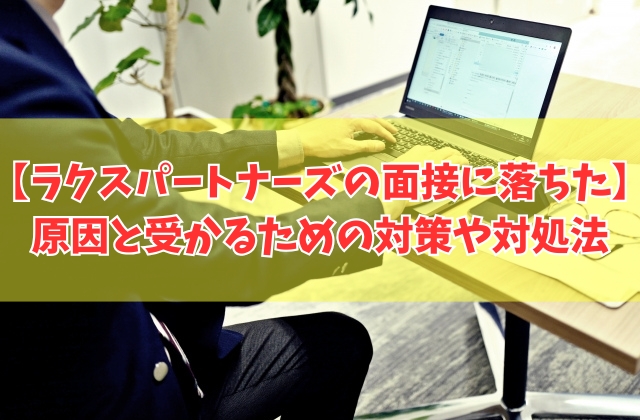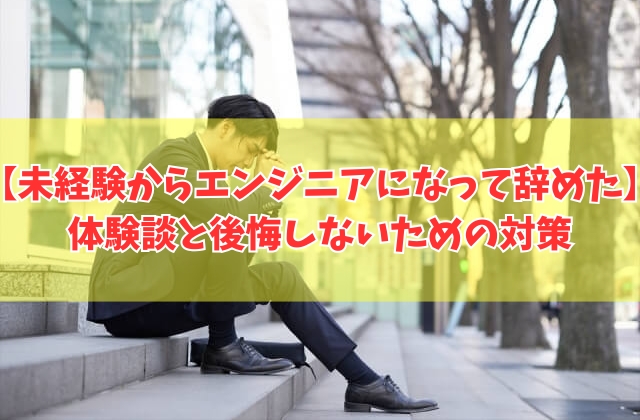
「未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談の内容は?」
「転職して後悔しないためにどんな対策が必要?未経験でも利用できるサービスはないの?」
未経験からITエンジニアを目指す人にとって、最初の一歩は期待と不安が入り混じる瞬間です。
SNSや口コミには、未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談が数多くあり、その多くが「もっと準備しておけばよかった」という声であふれています。
理想と現実のギャップに直面してからでは遅く、働く環境やサポート体制、成長できるかどうかを見極めることが欠かせません。
この記事では、未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談をもとに、同じ失敗を防ぐための具体策をわかりやすく紹介します。
- 事前の企業調査や職場環境の確認が不足すると、早期離職につながりやすい
- スキル習得やキャリア形成の視点を持たずに就職すると、将来の選択肢が狭まる
- サポート体制や成長機会がない職場では、未経験者が孤立しやすい
未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談には、共通した落とし穴があります。
入社前に企業や働き方の実態をしっかり把握し、成長できる環境かどうかを見極めることが、後悔しないキャリア選びのカギになります。
とはいえ、求人票だけで教育体制の実態を見極めるのは至難の業。実際、「研修あり」と書かれていても、入社してみたら“放置状態”だった…というケースも少なくありません。
だからこそ、業界専任アドバイザーが企業の内情まで把握している無料の転職エージェントを活用しましょう。
自分に合った研修・フォロー体制のある企業を紹介してもらえるため、「入って後悔した…」を防げます。
✅【無料】未経験からITエンジニアを目指す!転職エージェントおすすめ3選
- IT・Web業界特化の転職エージェント『ユニゾンキャリア』|優良企業の求人10,000件以上&年収UP83%!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが面接対策や必要書類の作成方法など手厚くサポート。
- 就職支援実績50,000名超え『UZUZ(ウズウズ)』|大手からベンチャーまで登録企業社数3,000社以上!完全オーダーメイドの面接対策で内定率UPだけでなく入社後のミスマッチも防ぐ、オンリーワンの支援サービス。
- IT就職&IT学習のダブルサポート『ウズウズIT』|就業マッチング4,000名以上!入社後の定着度は驚異の93.6%超えを達成する、ITエンジニアを目指す求職者・大学中退者に特化した就業サポート。
そして今では、未経験でも無料で基礎から学び、就活サポートまで受けられるサービスが登場しています。
「何から始めればいいかわからない」という方でも、学習~内定まで完全サポートしてもらえるため、最短ルートでITエンジニア就職を目指せます。
そんな未経験から稼げるITエンジニアに就職したい方は、以下3つの就職支援サービスがおすすめです。
いずれも“完全無料”で手厚いサポートを受けられる実績豊富なサービスのため、安心してITエンジニアを目指せます。
✅【完全無料】未経験からITエンジニアを目指す!就職支援サービスおすすめ3選
- 完全無料で未経験からITエンジニアに『ネットビジョンアカデミー』|就職率98%&IT資格(CCNA)の合格率99%!ITスキル習得だけでなく就職支援も徹底サポートする20代向けプログラミングスクール。
- 最短60日でIT就職を成功に導く『プログラマカレッジ』|累計受講者数5,738名!就業率98.3%(平均内定獲得数3.7社)を誇る大卒・第二新卒向け国内最大級の就活直結型プログラミングスクール。
- IT就職&IT学習のダブルサポート『ウズウズIT』|就業マッチング4,000名以上!入社後の定着度は驚異の93.6%超えを達成する、ITエンジニアを目指す求職者・大学中退者に特化した就業サポート。
【現実】未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談10選
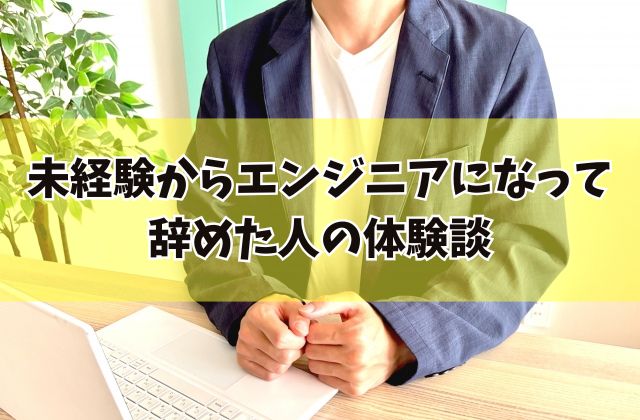
未経験からITエンジニアとして働き始めたものの、理想と現実のギャップに直面して早期に辞めてしまう人も少なくありません。
「未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談10選」では、SNS(知恵袋、X、YouTubeなど)の声をもとに実際にエンジニア職を離れた方々が何に悩み、どんな理由で離職を決意したのかを具体的に紹介します。
これからエンジニアを目指す方にとって、現場のリアルを知ることは大切な準備の一つです。体験談を通して、事前に知っておくべき課題や、心構えを深めていきましょう。
【体験談1】土日出勤や残業が常態化していた
新卒で初めての転職先として、ITエンジニアを「未経験歓迎」で募集していた中小企業に飛び込んだAさん。最初は「やっと技術職になれた」と胸が高鳴っていたそうです。ところが配属先は慢性的な人手不足で、納期に追われる現場。月末やシステムのリリース前になると終電は当たり前、朝方までデバッグ作業を続けることもありました。週末に出社することも常態化し、気づけば3か月以上も休みらしい休みが取れていなかったと振り返ります。家に帰れば食事を流し込み、倒れるように寝るだけ。半年ほどで体調を崩し、ついに退職を決めたとのことです。
こうした実態は、未経験からエンジニアを目指す人にとって決して珍しい話ではありません。特に小規模な受託開発会社や下請けの現場では、納期優先・長時間労働が常態化しているケースがあります(出典:参考資料)。
求人票に記載されている労働時間や休日制度はあくまで“建前”であることも多く、現場のリアルは働いてみないと分かりにくいのが現状です。入社前に企業の口コミや在職者の声を調べ、働き方の雰囲気を把握しておくことが、後悔を防ぐための重要な一歩になります。
【体験談2】夜間・休日の連絡対応に疲弊した
未経験からエンジニアとして入社したBさんは、初めての現場で「夜間対応あり」と聞いていましたが、実際は想像以上に過酷だったと話します。システムトラブルが起こるたびに夜中でも電話が鳴り、休日でも緊急メールが届く生活が続きました。リリース直後の週末はスマートフォンを手放せず、常に緊張した状態で過ごすことが当たり前になっていたそうです。友人との予定も急な呼び出しで何度も中止になり、プライベートの時間が奪われていくことに強い疲労感を覚え、最終的に体調を崩して退職を決意したと振り返っています。
未経験からエンジニアになる場合、夜間や休日の対応が業務に含まれることは少なくありません。特にインフラ保守や運用を担うポジションでは、トラブル時の緊急対応が日常化している職場もあります(出典:運用・管理(IT))。
求人票には「シフト制」や「待機あり」と書かれていても、実際の頻度や負担感は現場ごとに大きく異なります。入社前に働く社員の声や口コミを調べ、対応回数やサポート体制を確認することが、心身への負担を減らすための重要な対策になります。
【体験談3】休みの日も技術勉強に追われた
Cさんは文系出身で、未経験からエンジニア職に就職。毎日が新しい発見の連続で、最初のうちは仕事も学びも楽しく感じていたそうです。しかし、ある時を境に「学ばなければ」という焦りが強くなり、休日も朝から夜まで参考書とパソコンに向かう日々が続いたといいます。周囲の先輩たちと比べて自分だけが劣っている気がして、技術のキャッチアップに必死でした。気づけば、友人との約束を断ることが当たり前になり、趣味の時間もゼロに。生活から楽しみが消え、半年後には「何のために働いているのか分からなくなった」と語っていました。
未経験からエンジニアになると、多くの人が「早く一人前にならないと」というプレッシャーを感じます。とくに周囲が経験者ばかりの職場では、自己学習への強迫観念に近い意識が芽生えやすくなります。
とはいえ、継続的な勉強は確かに大切ですが、心身を削るような努力では長続きしません。あらかじめ業務に必要なレベルを把握しておき、無理のないペースで成長を目指すことが、結果的に自信と実力につながります。「休む勇気」も、エンジニアとして大切な資質のひとつです。
【体験談4】スキルが伸び悩み挫折を感じた
Dさんは「未経験でも安心」と書かれていた求人に魅力を感じ、思い切ってITエンジニアの道へ進みました。最初は小さな修正作業やテスト業務からスタートし、徐々に技術を学べると思っていたそうです。しかし実際には、半年経っても同じような単純作業ばかりで、プログラミングや設計に挑戦できる機会はほとんどありませんでした。周囲の先輩たちが高度な技術を扱っているのを横目に、自分だけが成長していない感覚に苦しみ、ついには自信を失ってしまったといいます。努力しても道が開けない状況に疲れ、最終的に退職を選んだとのことです。
未経験からエンジニアとして働く場合、すぐにスキルアップできる環境が整っているとは限りません。特に下請けやサポート業務中心の現場では、任される仕事が限定され、成長の機会が少ないことがあります(出典:参考資料)。
技術を身につけるには、与えられた業務だけでなく、自ら勉強の時間を確保したり、社内外で経験を積む工夫が必要です。入社前に担当業務の範囲やキャリアパスを確認し、スキル習得の見通しを持つことが、挫折を防ぐための重要なポイントになります。
【体験談5】配属ガチャで不適切な現場に配属された
Eさんは、研修制度が整っていると聞いていたIT企業に未経験で入社しました。入社後の面談では「成長できる環境を用意します」と言われていたそうですが、実際に配属されたのは社内でも評判の悪い炎上案件の現場。初日から手順書もなく、常にピリピリした空気の中で作業を続ける日々が始まりました。周囲に質問できる雰囲気もなく、フォロー役の先輩もほとんど不在。精神的な負担がどんどん積み重なり、「どうして自分がこの現場に?」という疑問を抱いたまま、3ヶ月で退職する決断をしたとのことです。
IT業界では「配属ガチャ」と呼ばれるように、希望していないプロジェクトに突然アサインされることがあります(出典:企業の人材採用の変化)。とくに未経験者の場合、教育が行き届かない現場に配属されると、スキルを身につける前に心が折れてしまうことも少なくありません。
会社全体の制度が良くても、現場ごとの環境差が激しいことがあるため、入社前に「配属の決め方」「現場のサポート体制」などを確認しておくことが重要です。ミスマッチを避けるためにも、配属後のフォロー体制までチェックしておきましょう。
【体験談6】サポートがなく自力対応を強いられた
Fさんは、未経験からエンジニアを目指し「教育体制が整っている」とうたう企業に入社しました。研修は1か月だけで、その後すぐに現場に配属されたそうです。初めて触れるシステムの保守業務を任されましたが、手順書は古く、質問できる先輩も不在。エラーが出ても原因を一から調べるしかなく、毎日が手探りの状態だったといいます。精神的に追い詰められながら夜遅くまで自習し、ようやく対応できるようになっても評価は得られず、孤立感が増して退職を決意したとのことです。
未経験からエンジニアになる場合、企業によってはフォロー体制が整っていない現場に配属されることがあります。教育制度があっても、実際には配属先にメンターや指導者がいないケースが少なくありません。
こうした環境では、自己解決力が鍛えられる一方で、過剰な負担により心身をすり減らす危険があります。入社前に研修終了後のサポート体制や相談先の有無を確認し、孤立しにくい環境を選ぶことが、長く働くための大きなポイントになります。
【体験談7】仕様変更や無理な納期に振り回された
Gさんは未経験からエンジニアに転職し、最初の配属先は中規模のWeb開発案件でした。やる気に満ちて取り組んでいたものの、クライアントからの仕様変更が頻繁に発生。開発の途中で設計が何度もやり直しになり、そのたびに納期は据え置きという状況でした。ある時はリリースの1週間前に機能の追加が決まり、終電での帰宅が続いたそうです。自分の努力ではどうにもならない要因に振り回され続け、次第に疲弊。「技術以前にスケジュールの理不尽さが辛かった」と語り、半年で離職に至ったとのことです。
エンジニアの現場では、顧客都合や社内の判断で突然仕様が変わることが少なくありません。特に受託開発やベンチャー企業では、納期が最優先され、現場の負担にしわ寄せが来るケースもあります(出典:参考資料)。
未経験で入った人にとって、こうした突発的な変更への対応は大きなストレスになります。入社前にどのような働き方が求められるのか、案件の進行管理体制や顧客対応の範囲などを確認しておくことで、こうしたギャップによる早期退職を防ぎやすくなります。
【体験談8】周囲社員とのスキル差に打ちのめされた
Hさんは未経験でIT企業に入社し、「現場で学びながら成長できる」と期待を抱いていました。しかし配属先は経験豊富な中堅社員ばかりで、日々の業務スピードについていけず、質問するのも気後れしてしまう環境だったといいます。自分だけが作業に時間をかけてしまい、何度もやり直しを求められる中で、「なんでこんなことも分からないの?」というような視線を感じることが増えていきました。いつの間にか発言も減り、気づけば周囲とまともな会話もできない状態に。自信をなくし、わずか5か月で退職を決断したとのことです。
未経験からエンジニアとして働く場合、職場の人間関係やスキルレベルの差に戸惑うことはよくあります。
成長したい気持ちがあっても、周囲と比較してしまうことで焦りや劣等感が生まれやすくなるのです。特に孤立した環境では、悩みを抱え込んでしまいがちです。
入社前に「新人が質問しやすい雰囲気かどうか」や「成長を支える教育体制があるか」といった点を確認しておくことが、安心して学べる環境選びにつながります。技術力だけでなく、人との関係性も職場選びの重要な基準になります。
【体験談9】メンタルを支える相談相手がいなかった
Iさんは未経験からエンジニア職に挑戦し、右も左も分からない中で毎日必死に業務に向き合っていました。しかし、少しずつトラブル対応や納期プレッシャーが積み重なり、気づけば業務中に何度も動悸や頭痛を感じるようになっていたそうです。上司は忙しく、同僚もそれぞれの仕事で手いっぱい。相談できる雰囲気もなく、気軽に話せる相手が社内に誰一人いない状況だったと振り返ります。「自分だけがつまずいている気がして、どんどん自信がなくなった」と話し、最終的には体調を崩して退職を決断することになったとのことです。
未経験からエンジニアになると、技術面だけでなく精神的な負担も非常に大きくなります。
慣れない業務や人間関係、孤立感が積み重なると、真面目な人ほど心が疲弊しやすくなります。とくに新人を支えるメンターや相談窓口がない職場では、悩みを抱え込んでしまう傾向があります(出典:参考資料)。
入社前に「誰に相談できるのか」「新人フォローはどのように行われるのか」を確認しておくことが、心の健康を守るうえで非常に重要です。メンタル面のケアも、長く働くために欠かせない要素のひとつです。
【体験談10】未経験者に割り振られた業務は単純サポートばかり
Jさんは、ITエンジニアとして成長できる環境を求めて未経験から転職しました。ところが配属後に任されたのは、資料の修正やデータの入力、議事録の作成といったサポート業務ばかり。最初は「まずは簡単な仕事から」と自分に言い聞かせていたそうですが、3か月経っても開発には一切関われず、「いつになったらコードを書かせてもらえるのか」と不安を抱えるようになったといいます。同期が少しずつプログラミング業務を任されていく中、自分だけが取り残されているような気がして心が折れ、半年で退職を決めたそうです。
未経験からエンジニアになった場合、最初は簡単な業務から始まることは自然ですが、スキルアップの機会が与えられない環境だと早い段階で成長の壁にぶつかります。企業によっては未経験者に対し、長期間サポート業務だけを担当させるケースも見られます(出典:参考資料)。
将来のキャリアを考えるなら、どのくらいの期間で実務に入れるのか、ステップアップのロードマップがあるかを面接時に確認しておくことが大切です。「何を任せてもらえるか」は、エンジニアとしての将来に大きく関わってきます。
未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談に共通する3つの後悔
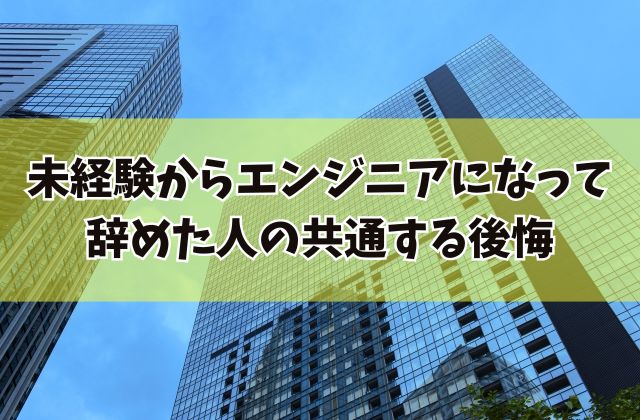
未経験からエンジニアを目指して就職したものの、早期に退職してしまう人には共通する「後悔の理由」があります。
なかでも「未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談に共通する3つの後悔」は、これからIT業界に踏み出そうとする人にとって重要な教訓となります。
ここでは、実際の体験談をもとに、転職前に見落としがちなポイントを紹介していきます。
【後悔1】十分な企業研究を行わずに会社を選んでしまったこと
IT業界の求人には「未経験歓迎」や「教育制度充実」といった耳触りのいい言葉が並びます。
しかし、そこだけを信じてしまうと、いざ働き始めたときに「こんなはずじゃなかった」と強い後悔を抱くことになりがちです。表に出る情報は限られており、現場の雰囲気やプロジェクトの実態は外からでは見えにくいからです。
実際にKさん(27歳)は、求人票の文言に安心して某IT企業へ入社しました。面接でも「未経験者を丁寧に育てます」と説明され、成長できる環境だと信じていたそうです。
ところが実際に配属された先は、教育どころか納期優先の現場。休日出勤や時間外対応が当たり前で、相談できる人もいませんでした。「入社前にもっと調べておけば…」と悔やんでいるといいます。
こうしたミスマッチを避けるには、企業研究を“求人票以外”の情報源から行うことが欠かせません。
実際、転職経験者300人への調査では、企業研究を徹底した人ほど就職後の満足度が高いという結果が出ています(Geekly調べ)。会社の理念や社風、技術環境、実際の働き方を、説明会や社員インタビュー、口コミサイトなどで多角的に確認することが、後悔を減らす最大のカギです。
【後悔2】労働時間・休日の実態を確認しなかったこと
求人票や面接の言葉に安心して飛び込んだ結果、働き始めてから「話が違う」と感じた人は少なくありません。とくに未経験からエンジニア職に就いた方の中には、理想と現実のギャップに打ちのめされたという声もあります。
たとえばLさん(20代・女性)の話です。就職先の担当者からは「定時帰宅を基本とした働き方」と説明を受けたそうですが、実際に配属されたのは導入期が重なったプロジェクトチーム。繁忙期に突入すると、終電間際まで残業が続き、土日もシステムテストの対応で休めない日が何週間も続きました。Lさんは当時を「今思えば、あれは“覚悟”がないと乗り切れなかった」と振り返ります。
実は、こうしたケースは決して特殊な話ではありません。dodaの調査では、ITエンジニアの平均残業時間は月22.6時間とされています。また、厚生労働省の統計によれば、情報通信業の年間労働時間は1,933時間で、全産業平均の1,724時間を明らかに上回っているというデータも出ています(出典:IT業界の長時間労働対策について)
こうした背景をふまえると、入社前に確認すべきは「聞こえのいい言葉」ではなく、実際の現場の声です。面接の場では遠慮せず、「月の残業時間はどのくらいですか?」「休日出勤は発生しますか?」といった質問を投げかけてみてください。
さらに、社員インタビューや口コミ、SNSなど“生の声”に目を通しておくと、会社の実像が見えてきます。
時間は取り戻せません。自分の時間をどう扱う会社なのかを見極めてから、エンジニアというキャリアに一歩踏み出すことをおすすめします。
【後悔3】指導や相談体制があるか確認しなかったこと
未経験からエンジニアに挑戦した人がつまずきやすい理由のひとつが、「サポート体制の実態を見誤ったまま入社してしまうこと」です。求人票に“教育あり”と書かれているだけでは、実際の現場でフォローがあるかどうかまでは分かりません。
たとえばMさん(20代後半・男性)は、面接で「研修制度あり」と説明されて安心して転職しました。しかし配属先は繁忙期真っ只中。先輩に相談する余裕はなく、トラブル対応も一人で抱え込む毎日が続きました。入社から半年ほどで疲労が限界に達し、退職という選択を取らざるを得なかったそうです。「誰にも聞けない状況が一番つらかった」と振り返っています。
実際に、未経験エンジニアを受け入れる企業のなかには、メンター制度や定期面談などを設け、相談窓口を明確にしているところもあります。
Wantedlyの事例では「研修後3か月は講師陣が伴走し、毎週面談を実施する」といったフォロー体制を紹介している企業もありました。
入社前に確認する方法はシンプルです。面接の場で「研修後は誰に相談できますか?」「メンター制度はありますか?」と具体的に尋ねてみること。そして口コミやSNSで、実際に働いていた人の声を探してみること。サポートが手薄な環境で孤立しないためには、この下調べが何よりも力になります。
未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談から失敗しないための対策
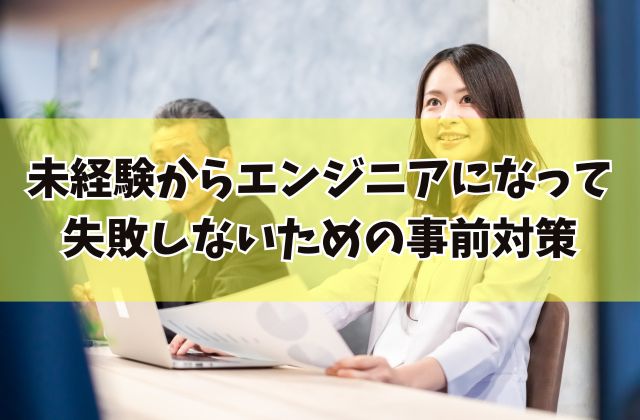
未経験からエンジニアとして働き始めたものの、理想と現実のギャップに悩み早期に退職する人は少なくありません。
こうした経験者の声をもとに、「未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談から失敗しないための対策」を知ることは、将来のキャリア選択で大きな助けになります。
ここでは、実際の体験談に基づいた具体的なポイントを紹介し、後悔を防ぐための手がかりを整理しています。
【対策1】プログラミングの基礎知識を入社前に習得しておく
未経験からエンジニアに挑戦する場合、現場での“つまずきポイント”はたいてい決まっています。その筆頭が、「基礎が頭に入っていない状態で実務に放り込まれる」こと。右も左も分からず、先輩の会話がまるで外国語のように感じる。そんな空気に押し潰されて辞めてしまった、という声は決して少なくありません。
例えば、ある30代の転職者は、ProgateとドットインストールでHTML・CSS・JavaScriptの初歩を一通りこなしてから現場に入りました。実務経験ゼロのまま業務スタートでしたが、「何となくコードの構造が見えるだけでも、不安のレベルが違った」と話しています。
逆に、完全な白紙状態で入社した同期は、初日からSlackに流れる単語さえ理解できず、わずか2か月で退職していったそうです。
Zennの技術系記事でも、未経験者が事前に押さえるべき知識として「変数」「関数」「条件分岐」「Git」「SQL」などが挙げられています。どれも難解なアルゴリズムではなく、手を動かせば数日で感覚が掴めるものばかりです。
最低限でも構いません。入社前に基礎だけでも触れておくことで、現場での焦りやストレスを大きく減らせます。空いた時間に15分だけでも画面に向かってコードを書いてみる──それが、あなた自身を守る最初の一歩になるはずです。
そして今では、未経験でも無料で基礎から学び、就活サポートまで受けられるサービスが登場しています。
「何から始めればいいかわからない」という方でも、学習~内定まで完全サポートしてもらえるため、最短ルートでITエンジニア就職を目指せます。
そんな未経験から稼げるITエンジニアに就職したい方は、以下3つの就職支援サービスがおすすめです。
いずれも“完全無料”で手厚いサポートを受けられる実績豊富なサービスのため、安心してITエンジニアを目指せます。
✅【完全無料】未経験からITエンジニアを目指す!就職支援サービスおすすめ3選
- 完全無料で未経験からITエンジニアに『ネットビジョンアカデミー』|就職率98%&IT資格(CCNA)の合格率99%!ITスキル習得だけでなく就職支援も徹底サポートする20代向けプログラミングスクール。
- 最短60日でIT就職を成功に導く『プログラマカレッジ』|累計受講者数5,738名!就業率98.3%(平均内定獲得数3.7社)を誇る大卒・第二新卒向け国内最大級の就活直結型プログラミングスクール。
- IT就職&IT学習のダブルサポート『ウズウズIT』|就業マッチング4,000名以上!入社後の定着度は驚異の93.6%超えを達成する、ITエンジニアを目指す求職者・大学中退者に特化した就業サポート。
【対策2】企業の教育制度や研修制度を事前に確認する
「ちゃんと教えてもらえると思って入ったのに、実際は放置されっぱなしだった」。そんな声、実はよく聞きます。未経験からエンジニアに挑戦する場合、教育体制の有無は働きやすさを大きく左右します。にもかかわらず、「研修あり」という言葉だけを鵜呑みにしてしまうと、後悔する結果になりかねません。
たとえば、ある大手のIT企業では、基礎的なマナーから始まり、ネットワーク、プログラミング、セキュリティに至るまで、未経験向けに段階的な研修カリキュラムを整備しているところもあります。
一方、実情が「先輩に聞きながら慣れてください」レベルの会社も珍しくありません。聞きにくい空気、教えてもらえない雰囲気…そんな環境では、学ぶ以前に心がすり減ってしまいます。
だからこそ、面接では遠慮せずにこういった点を深掘りしておきましょう。
- 研修期間はどれくらいか
- 実務配属後のサポート体制がどうなっているか
- 定期的な面談や振り返りの仕組みがあるか
加えて、口コミサイトや社員インタビューを通じて、実際に研修が「役に立った」と語っている人がいるかどうかも確認しておくと安心です。求人票に「研修制度あり」と書かれていても、実態は千差万別。「教える気がある会社かどうか」を見極める目を持つことが、後悔しない就職への第一歩です。
とはいえ、求人票だけで教育体制の実態を見極めるのは至難の業。実際、「研修あり」と書かれていても、入社してみたら“放置状態”だった…というケースも少なくありません。
だからこそ、業界専任アドバイザーが企業の内情まで把握している無料の転職エージェントを活用しましょう。
自分に合った研修・フォロー体制のある企業を紹介してもらえるため、「入って後悔した…」を防げます。
✅【無料】未経験からITエンジニアを目指す!転職エージェントおすすめ3選
- IT・Web業界特化の転職エージェント『ユニゾンキャリア』|優良企業の求人10,000件以上&年収UP83%!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが面接対策や必要書類の作成方法など手厚くサポート。
- 就職支援実績50,000名超え『UZUZ(ウズウズ)』|大手からベンチャーまで登録企業社数3,000社以上!完全オーダーメイドの面接対策で内定率UPだけでなく入社後のミスマッチも防ぐ、オンリーワンの支援サービス。
- IT就職&IT学習のダブルサポート『ウズウズIT』|就業マッチング4,000名以上!入社後の定着度は驚異の93.6%超えを達成する、ITエンジニアを目指す求職者・大学中退者に特化した就業サポート。
【対策3】面接で実際の業務内容や責任範囲を詳しく聞く
「開発に関われます」って書いてあったのに、入ってみたらExcelで手順書ばかり──そんな話、意外と珍しくありません。特に未経験からIT業界に飛び込んだ人たちの体験談には、こうした“ズレ”が頻繁に登場します。
たとえば、ある男性はこう語っています。「入社前、面接で“開発に携われる”って言われたので期待していました。でも実際は先輩の資料作成がメイン。コードはほぼ触れず、ただの補助要員でした」。本人は何が悪かったのか分からず、半年で退職を決断したそうです。
こうしたミスマッチを防ぐには、面接で「どこまでが自分の担当なのか」を掘り下げて聞いておくことが不可欠です。具体的には、こんな質問が役に立ちます。
- 最初の3ヶ月でどんなタスクを任されるか
- 現場のチーム構成と新人の役割
- 技術的なミスが起きたときのサポート体制
- 評価の基準や責任の範囲
求人票や面接のフレーズは、どうしても抽象的になりがちです。だからこそ、「それって、実際にどんな作業をするんですか?」と具体的に聞く勇気が必要なんです。遠慮は不要です。後で「話が違った」と嘆くより、今の一歩が未来を守ってくれます。
【対策4】残業・休日対応の実態を社員・口コミで調べる
求人票に書かれている「残業は月20時間以内」「完全週休2日制」──こんな文言を鵜呑みにして、入社後に後悔する人が後を絶ちません。とくに未経験でエンジニア職に飛び込む場合、「現場のリアル」が見えていないまま意思決定してしまうケースが多く見られます。
実際、IT業界の平均残業時間は月23.2時間という調査結果があり(Geekly調べ)、dodaのデータでも21.2時間と報告されています。ただし、これは“平均値”。裏を返せば、月40時間を超える会社もあれば、休日出勤が常態化している現場もあるということです。
口コミサイトを見ると、「平日は毎日2時間残業、月末は休日出勤も当たり前」「繁忙期は有給なんて取れない」というような体験談が普通に出てきます。
だからこそ、「実際どうなのか?」を、自分の目と耳で確かめにいく必要があります。OpenWorkや転職会議といった口コミサイトで、気になる企業名+「残業」「休日出勤」「有給取得」などのキーワードで調べてみましょう。
また、面接の場で「実際の平均残業時間」や「直近1年間の休日出勤の有無」などを具体的に質問するのも大事です。できれば、SNSやSlackコミュニティなどを使って、現場の社員とつながり、リアルな声を拾えれば理想的です。
「知らなかった」で済まされないのが、就職の現場。特にIT業界は、見えない“働き方の罠”が潜んでいることもあるため、事前調査は後悔しないための最初の防波堤になります。
【対策5】入社前に相談できるメンターや支援制度を確認する
エンジニア未経験で飛び込むからこそ、何よりも必要なのは「困ったとき、頼れる人がいるかどうか」です。技術が分からないのは当然。でも、それを受け止めてくれる仕組みがなければ、たとえやる気があっても、気持ちは折れてしまいます。
実際、ネット上には「入社したら放置」「質問しても誰も答えてくれない」といった声が散見されます。一方で、ウィメックスのように、1年間のメンター制度がある企業も存在します(出典:参考事例)。
専任で相談に乗ってくれる人がいれば、業務のことだけでなく、心の揺れや不安も自然と和らぎます。
大切なのは、「研修あり」という言葉に安心しすぎないこと。面接のときは以下のように、踏み込んで聞いてみてください。
- 研修後も相談できる先輩はいますか?
- メンタリングの頻度や形式はどうなっていますか?
- 実際にサポートが活用されているか、過去の例はありますか?
加えて、OpenWorkや転職会議などの口コミサイトを使って、実際にその制度が“形だけ”になっていないか、実体験ベースでチェックすることも欠かせません。
目に見えにくい“人の支え”の仕組みは、入社後の安心感に直結します。制度があるかないかではなく、「ちゃんと機能しているか」を見極めること。それが、未経験者が安心してキャリアを歩むための鍵になります。
【対策5】将来のキャリアパスや昇給制度を見越して選ぶ
エンジニアとしてスタートを切るとき、働きやすさや雰囲気の良さばかりに目を向けてしまいがちですが、長く続けたいなら「この会社で成長していけるのか」を冷静に見極める必要があります。
なぜなら、キャリアの先が見えない環境では、頑張りが実を結ばず、数年後に行き詰まるケースが少なくないからです。
たとえば、IT業界では約8割のエンジニアが毎年昇給しているという調査(※Geekly調べ)もありますが、実際に中身を見てみると、評価基準が不透明だったり、年功序列が根強く残っていたりと、「スキルに応じた評価」がなされていない職場も珍しくありません。キャリアアップや昇給が形式だけのものになっていると、モチベーションは下がる一方です。
ですから、面接の場では以下のような質問を遠慮せず投げかけましょう:
- 昇給の仕組みや頻度はどのようになっていますか?
- 技術職としてのキャリアと、マネジメント職への道、両方選べますか?
- 昇給が見送られるケースは、どんな要因があるのでしょうか?
なかには「オープンアップITエンジニア」のように、キャリアレベルごとに報酬テーブルが明示されている企業もあり、自分が今どこにいて、どう成長すれば報われるのかが一目でわかります。こうした仕組みは、未経験者にとって非常に心強い指標になります。
目の前の「内定」や「雰囲気の良さ」に飛びつく前に、その先に広がる道がどれだけ明確か、どれだけ自分の成長と収入に直結するか──そこにしっかり目を向けておくことが、後悔しない就職・転職につながります。自分の未来は、面接での質問一つで大きく変わるのです。
とはいえ、求人票だけで将来のキャリアパスや昇給制度を見極めるのは至難の業。実際、入社してから「思っていた評価制度と違った」と感じるケースも少なくないのです。
だからこそ、業界専任アドバイザーが企業の内情まで把握している無料の転職エージェントを活用しましょう。
あなたの希望やスキルレベルに合った企業を紹介してもらえるだけでなく、キャリアパスや昇給制度の実態もプロの視点で教えてもらえます。
将来を見据えて後悔しない選択をするためにも、まずは無料相談から始めてみましょう。
✅【無料】未経験からITエンジニアを目指す!転職エージェントおすすめ3選
- IT・Web業界特化の転職エージェント『ユニゾンキャリア』|優良企業の求人10,000件以上&年収UP83%!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが面接対策や必要書類の作成方法など手厚くサポート。
- 就職支援実績50,000名超え『UZUZ(ウズウズ)』|大手からベンチャーまで登録企業社数3,000社以上!完全オーダーメイドの面接対策で内定率UPだけでなく入社後のミスマッチも防ぐ、オンリーワンの支援サービス。
- IT就職&IT学習のダブルサポート『ウズウズIT』|就業マッチング4,000名以上!入社後の定着度は驚異の93.6%超えを達成する、ITエンジニアを目指す求職者・大学中退者に特化した就業サポート。
【無料】未経験からITエンジニアを目指す!実績豊富な転職支援サービス3選
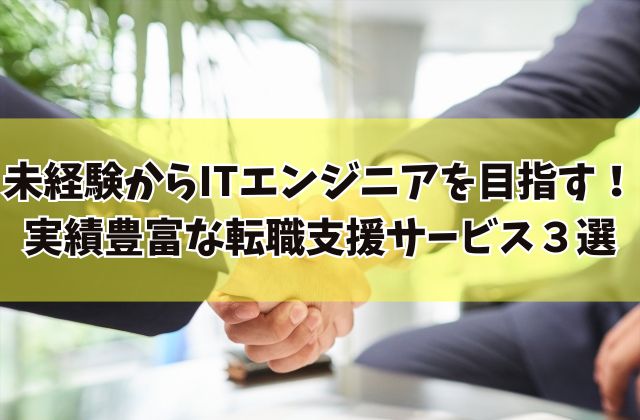
未経験からITエンジニアとして新たな一歩を踏み出すなら、経験者の体験談を知るだけでなく、「無料」で利用できる転職支援サービスを活用することが重要です。
転職活動を一人で進めると不安が多くなりがちですが、実績のある支援サービスなら、学習サポートから企業選びまで丁寧にフォローしてもらえます。
ここでは、未経験からITエンジニアを目指す人に特化し、安心してスタートが切れる支援サービスを3つ厳選して紹介します。
【サービス1】ネットビジョンアカデミー
未経験からエンジニアを目指すなら、「どうせやるなら、無料で本気のサポートを受けたい」と考えるのは自然なこと。そんな希望に応えてくれるのが、『ネットビジョンアカデミー』です。
ここは、インフラエンジニアの育成に特化した無料スクールで、CCNAというネットワーク系資格の取得を目指しながら、最短2か月での就職をゴールに据えています。テキスト代や研修費用は一切かからず、加えて履歴書の添削から模擬面接、企業紹介まで手厚いサポートが受けられるのが魅力です。
実際のところ、卒業生の多くが「インフラって何?」という状態からスタートしており、それでも短期間で正社員としてIT業界に踏み出しています。特に、「何から始めたらいいかわからない」と悩んでいる人にとって、この環境はまさに足がかりになるはずです。
ただし、注意点もあります。受講条件として「東京近郊での勤務が可能なこと」が求められるため、地方在住者は選択肢に入れにくい場合も。
とはいえ、無料でここまでの内容を提供しているスクールは他にあまり見かけません。まずは説明会に参加して、現場の声や制度のリアルを自分の耳で確かめてみるとよいでしょう。
【サービス2】ユニゾンキャリア
未経験からIT業界に飛び込もうとしたとき、何が一番不安かといえば「自分に合った企業が見つかるか」「そもそも採用してもらえるか」ではないでしょうか。そんなとき、無理にひとりで動き回るより、頼れるプロに相談するのが近道です。
『ユニゾンキャリア』は、まさにそういう“迷っている人”に寄り添ってくれる存在です。
このサービスの強みは、ただ求人を紹介するだけではありません。担当するキャリアアドバイザーは、IT業界出身者や現場に詳しい人ばかり。知識がゼロでも、何をすれば良いのかをイチから教えてくれます。
書類添削や面接対策といった支援はもちろん、企業ごとの対策資料まで用意されているというのは、正直驚きでした。
実際に使った人の声を調べてみると、「未経験でも対応が手厚かった」「希望と違う求人を無理に勧めてこなかった」という評価が多く見られました。こうした細やかな配慮が、安心感につながっているのでしょう。
「どう動けばいいかわからない」「そもそも向いているのかわからない」──そんな不安を抱えている人ほど、まずはユニゾンキャリアの面談を受けてみる価値があると思います。
迷ったまま時間だけが過ぎてしまう前に、誰かと一緒に最初の一歩を踏み出してみませんか?
【サービス3】ウズウズIT
「未経験からでもIT業界に入れる」──そう聞いて希望を抱いた人が、実際に道を切り開いている場所があります。それが、『ウズウズIT』。
単なる学習サービスではなく、“学んだ先の就職”まで視野に入れた支援を、完全無料で提供している点が特に心強いです。
特徴的なのは、受講者の大半がIT未経験であるにもかかわらず、インフラ・開発の両コースから最短1か月で内定を獲得しているという事実。
しかも、学習だけにとどまらず、面接対策や企業紹介、内定後のサポートまでトータルで対応。ひとりで不安を抱え込まずに済むよう、伴走する形で支援が続く点が、辞めずに続けられる理由にもなっています。
もちろん、無料という言葉には注意が必要。条件や対象地域、紹介企業の範囲など、事前に確認すべき点はあります。ただ、いわゆる“受けっぱなしのスクール”ではなく、「ちゃんと就職して終わる」ことを前提とした構成になっている分、情報収集さえ怠らなければ、選択肢として非常に現実的です。
スクール選びで迷うなら、ウズウズの説明会で話を聞いてみる価値はあります。公式サイトでは卒業生の実例も紹介されているので、イメージしやすいはずです。
【Q&A】未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談に関するよくある質問
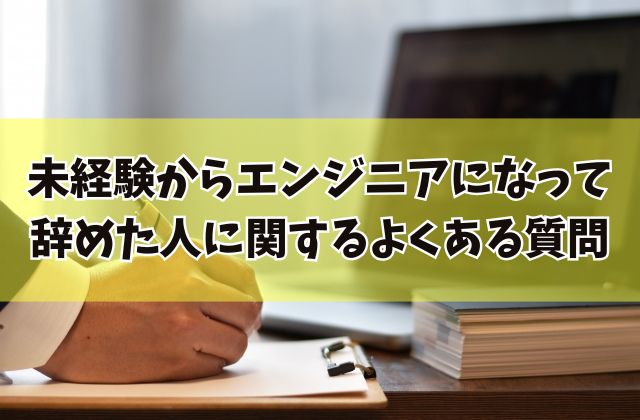
最後に未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談に関するよくある質問をまとめました。
よくある声や疑問を取り上げ、一つひとつ丁寧に解説していきます。選択に迷う前に、リアルな声に目を通しておきましょう。
【質問1】未経験からエンジニアになって後悔?知恵袋の声は?
掲示板には「思っていたのと違った」「辞めたい」といった後悔の声も見かけます。でも、そうした投稿だけを鵜呑みにするのは危険です。
現実には、IT人材が足りていない会社が多く、IPAのデータでも62.1%の企業が「大幅に人が足りない」と回答しています。SNSや知恵袋は、あくまで個人の体験や感情の一部。企業の口コミサイトや面接の場で、実際の働き方を確かめる方が、ずっと確実な判断につながります。
【質問2】女性でも未経験からエンジニアになって続けられる?
「女性でもやっていけるのか不安…」という声をよく聞きますが、答えはYESです。
内閣府の統計でも、情報通信業で働く女性の割合は約3割。まだ少ないものの、国は今「女性デジタル人材の育成」に本腰を入れています(出典:女性デジタル人材の育成について)。
実際、時短勤務やリモートに対応した企業も増えてきました。入社前には、制度が“あるか”だけでなく、“実際に使われているか”まで確認することが、長く働くための鍵です。
【質問3】未経験エンジニアはうざいと思われやすい?
正直に言えば、受け入れ態勢が整っていない職場では、そう思われてしまう可能性もあります。特にOJTに頼りきりで、質問するたびに先輩の手を止める環境だと、肩身が狭くなることも。
でも、週ごとの学習報告や、こまめな進捗共有ができる人は、むしろ評価されやすいです。見学や面接では、「入社後のサポート体制」や「質問のしやすさ」について具体的に聞くと、ミスマッチを避けやすくなります。
【質問4】未経験エンジニアはいらないと言われるの?
「未経験=いらない」と感じてしまう場面があっても、それは職場の体制の問題です。
実際、IPAの調査では「人が足りない」と答えた企業が85.1%(「やや不足26.6%」「大幅に不足58.5%」の合計)にのぼっています(出典:デジタル時代のスキル変革等に関する調査(2024年度))。
教育前提で採用する会社も少なくありません。大切なのは、入社前に「どんな研修があるか」「何を任されるのか」を細かく確認すること。配属やサポート次第で、未経験でも一気に力を伸ばせます。
【質問5】28歳からでも未経験でエンジニアになれる?
28歳はむしろ“ちょうどいい”年齢です。
転職サイトdodaのデータによると、20代後半は転職成功者が最も多い層。IT業界の平均年齢も30代前半なので、28歳なら年齢面の不利はありません。
ただし、採用されるには準備が必要です。ポートフォリオには、HTMLやCSSだけでなく、APIやSQLなど“実務に近い”技術を入れると、説得力がグッと上がります。
【質問6】未経験エンジニアで辞めたいときの選択肢は?
つらいと感じたら、まずは自分の心と体を守ることが先決です。
厚生労働省の「こころの耳」では無料相談が受けられますし、労働条件で悩んでいるなら「労働条件相談ほっとライン」にも電話できます。無理を続けずに一度立ち止まり、相談できる窓口を使いましょう。落ち着いてきたら、転職や社内異動、学び直しなど、新しい選択肢をじっくり検討すれば大丈夫です。
まとめ:未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談と後悔しないための対策
未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談と後悔しないための対策をまとめてきました。
改めて、未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談をまとめると、
- 土日出勤や残業が常態化していた
- 夜間・休日の連絡対応に疲弊した
- 休みの日も技術勉強に追われた
- スキルが伸び悩み挫折を感じた
- 配属ガチャで不適切な現場に配属された
- サポートがなく自力対応を強いられた
- 仕様変更や無理な納期に振り回された
- 周囲社員とのスキル差に打ちのめされた
- メンタルを支える相談相手がいなかった
- 未経験者に割り振られた業務は単純サポートばかり
そして、未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談から導き出せる5つの結論もまとめると、
- 働き方や職場環境の現実を事前に調べないと、理想と現実のギャップで離職につながる
- 指導体制が整っていない職場では、孤立しやすくメンタル面でも疲弊しやすい
- 未経験者に任される業務内容が単調だと、成長実感が得られず早期離職の原因になる
- 転職支援サービスの選択によっては、企業とのミスマッチを防げる可能性が高い
- あらかじめ基礎学習や企業研究を行うことで、未経験でも後悔のないキャリア選択ができる
未経験からエンジニアになって辞めた人の体験談を振り返ると、準備不足や職場選びのミスが多く見られます。
長く働ける環境を選ぶには、事前の情報収集と信頼できる転職支援の活用が欠かせません。失敗談から学び、理想と現実のギャップを埋める行動がカギです。