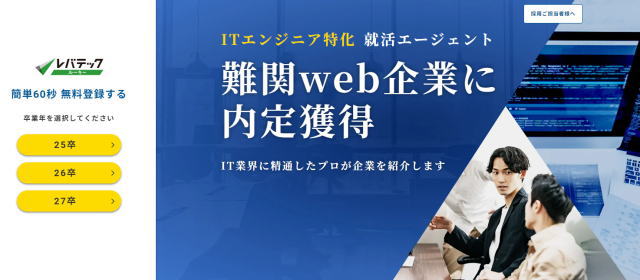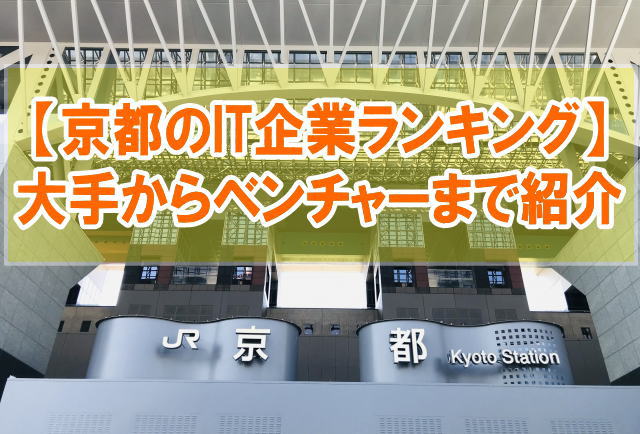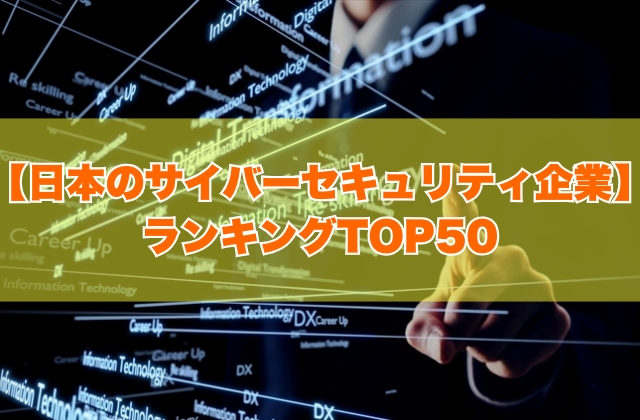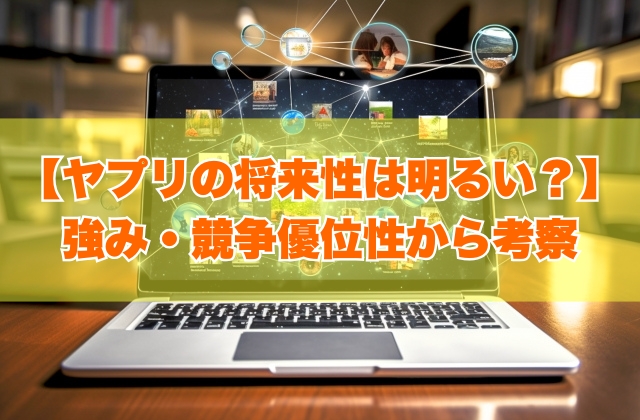
「ヤプリの将来性は明るい?」
「どんな人に向いてる会社?内定を勝ち取るためにはどんな対策が必要?」
就職や転職を考えるうえで、企業の将来性はとても重要な判断材料です。
特に成長著しいIT業界では、どの企業を選ぶかで今後のキャリアが大きく左右されることもあります。
「ヤプリって実際どうなの?」「ノーコードって本当に伸びるの?」
そんな不安や疑問を抱えている方に向けて、本記事では「ヤプリの将来性」に焦点を当てて、強み・競争優位性や事業上の課題から今後の見通しを徹底考察していきます。
- ノーコード市場で国内シェアNo.1という実績が信頼性と将来性の裏付けとなっている
- 導入700社超と継続率99%以上の実績が長期的な成長性と高いサービス価値を示している
- 人手不足を背景にノーコード需要が拡大し、ヤプリの存在価値が高まっている
ヤプリの将来性は、成長中のノーコード市場における圧倒的な実績と高い継続率、そして社会課題を背景とした需要の増加により、非常に明るいと考えられます。
IT分野への就職や転職を目指す方にとって、今後のキャリアにおいて検討する価値のある有望企業といえるでしょう。
そしてあなたが就活生で、ヤプリなど大手IT企業に就職を希望しているなら『レバテックルーキー』の活用を強くおすすめします。
『レバテックルーキー』は、大手Web企業から急成長ベンチャーまで。8,000社以上の企業情報を保有する、ITエンジニア専門の就活サービスです。
IT業界に詳しいプロによる就活サポートで、内定率アップへ導きます。ファーストキャリアをヤプリなどIT大手と決めている方は、ぜひご活用ください。
もし、あなたが転職希望者なら「IT専門の転職エージェント」を活用することをおすすめします。
転職エージェントを活用すれば、あなたのニーズに合ったIT企業“だけ”を紹介してくれます。転職先企業の希望条件を伝えるだけで、その日のうちに求人を複数紹介してくれます。
実績豊富なおすすめの転職エージェントを3社厳選しご紹介します、ぜひご活用ください。
✅【無料】年収アップも実現!IT専門の転職エージェントおすすめ3選
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営『マイナビIT AGENT』|一人ひとりのニーズにマッチした転職を提案するIT・Web業界に強い転職エージェント(※マイナビのプロモーションを含みます。)
- 希望企業への転職成功率96%を誇る『レバテックキャリア』|圧倒的な内定率!5人に4人が年収UPを実現するIT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが内定獲得まで徹底サポートするIT特化型転職エージェント。
- 社内SEの転職支援に特化した『社内SE転職ナビ』|社内SE求人は10,000件以上&入社後の定着率96.5%!専任アドバイザーが経歴や希望を丁寧にヒアリングし、該当する自社開発・情シス求人を提案。
【結論】ヤプリの将来性は明るい?

結論から言うと、ヤプリの将来性は「明るい」と言えます。これは単なる印象ではなく、いくつもの数字や市場動向から裏づけされている事実です。
まず注目すべきは、ヤプリが展開するノーコードアプリ市場の成長性です。業界全体として年々拡大を続けており、2028年には現在の約1.8倍になるという見通しも出ています。IT人材不足が深刻化する中、「プログラミング不要でアプリが作れる」というヤプリのビジネスモデルは、今後ますますニーズを集めるでしょう。
実際、ヤプリは国内で700社以上に導入されており、しかも99%以上という高い継続率を誇っています。これは単に新しいから使われているのではなく、顧客の満足度が高く、必要とされ続けている証拠です。
さらに売上も好調で、2024年には年間売上55億円を突破。営業利益も黒字に転じており、収益性の面でも安定感が増しています。
加えて、「アプリを作りたいけど開発リソースが足りない」という企業は今後も増えていくでしょう。そんな課題に柔軟に応えられるのが、まさにヤプリのような存在です。ブランド認知も着実に高まっており、「ノーコードアプリといえばヤプリ」と言われるポジションを築きつつあります。
こうした背景から、ヤプリは単なる流行りのスタートアップではなく、堅実に成長を続ける実力派企業だと考えられます。IT業界でキャリアを築こうとしている方や、転職先を見極めたい方にとって、ヤプリは今後の動向に注目すべき企業の一つです。
とはいえ、成長企業の将来性を正しく見極め、自分のキャリアと結びつけて判断するのは簡単ではありません。
だからこそ、IT領域に精通した『就活エージェント』を活用することで、ヤプリのような企業の最新動向や採用の裏側まで踏まえたアドバイスを得られます。
就活エージェントを活用すれば、あなたの強みをどのポジションで最大化できるかまで具体的に提案してくれるため、独学で進めるよりも納得感のある企業選びが可能になります。
限られた時間の中で、最大限の結果を残したい方、就活で失敗したくない方は、ぜひご活用ください。
✅【完全無料】実績多数で内定率アップ!IT・Web業界特化の就活エージェントおすすめ3選
- 8,000社以上の優良IT企業情報を保有『レバテックルーキー』|大手Web企業から急成長ベンチャーまで幅広く紹介!志望企業に合わせたES添削や面接対策、ポートフォリオの添削を実施し、内定率アップへ導きます。
- オリコン顧客満足度第3位『TECH-BASE 就活エージェント』|利用後の内定獲得実績5.6倍!IT業界に精通したアドバイザーが内定まで伴走。初歩的なことから専門的なことまで何でも安心して相談できます。
- 文系・理系問わず内定まで最短10日『ユニゾンキャリア就活』|Google口コミ★4.8!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが、就活相談~内定後&入社後も徹底的にサポートします。
ヤプリの将来性を7つの強み・競争優位性から考察

ノーコードアプリ開発の代表格として注目されるヤプリは、成長市場の中で確かな存在感を放っています。
特にヤプリの将来性を強み・競争優位性から考察することは、就職や転職を検討している人にとって重要な視点です。
業界トップクラスのシェアや導入実績、柔軟なサービス設計など、選ばれる理由には明確な根拠があります。
ここからは、IT企業への就職や転職を目指す方に向けて、ヤプリの優位性と今後の成長可能性について具体的に解説していきます。
【考察1】国内ノーコードアプリ市場でシェアNo1の安心感
ヤプリが将来有望だと語られる理由のひとつに、「国内ノーコードアプリ市場での圧倒的なシェア」があります。数字だけを見ると少しピンとこないかもしれませんが、アプリをコードなしで作れるノーコードツールの中で、ヤプリは今や“選ばれ続けている”存在なのです。
実際に、株式会社ヤプリの決算説明会資料によれば、2023年度における同社のノーコードアプリ市場でのシェアは「37.1%」。売上規模も「48.6億円」とされており、これは業界トップを意味します。しかも「ノーコード部門で国内No.1」という調査結果まで出ているとなれば、信頼に値する実績といえるでしょう。
さらに注目したいのが、サービスを導入した企業の数です。公式サイトではすでに「約900アプリが導入」され、「継続率は99%」という非常に高い数字が公開されています。ここまで続けて使われるプロダクトは、そう多くありません。
ノーコード開発というと、まだ新しい分野だと感じる方も多いかもしれません。ただ、その市場規模は2022年度に「約239億円」、翌2023年度には「316億円」と拡大を続けています。こうした背景の中で、ヤプリは単なる一企業ではなく、業界そのものの成長を牽引する存在になりつつあります。
企業がアプリ開発を検討する際、最も避けたいのは「使いこなせないツールを選ぶこと」や「途中でサポートがなくなること」です。その点、ヤプリは高いシェアと利用継続率、そして多くの導入事例を持ち合わせており、非常に安心感のある選択肢として、多くの企業に信頼されているのです。
【考察2】コードを書かずにスマホアプリを作れる強み
ヤプリの大きな特徴といえば、専門的なコードを書かなくてもアプリを形にできる点です。プログラミング経験のない担当者でも手を動かしながら画面を組み立てられるため、開発依頼にかかる費用や時間を抑えたい企業には心強い仕組みだと感じます。
実際、ヤプリは公式に「完全ノーコードプラットフォームで3年連続シェアNo.1」を掲げており、導入企業からの評価が数字として現れています。
従来、iOSとAndroidの両方に対応するアプリを外部へ依頼すると、半年以上かかるケースは珍しくありません(出典:参考資料)。ただ、ノーコード型の開発環境では、制作期間を数か月ほどに短縮できるという調査もあります。
この差は、事業スピードを重視する企業にとって大きな意味を持ちます。
利用者の声を見ても「ブラウザで画面を作り替えられる」「ドラッグ&ドロップで配置するだけでアプリの形ができた」といった意見が多く、専門のエンジニアがいない会社でも導入しやすい印象です。自社アプリを内製できる選択肢が増えるのは、企業にとって大きな武器になります。
こうした背景を見ると、ノーコードでアプリを作れる強みは、ヤプリの将来性を語るうえで欠かせないポイントだと言えるはずです。ノーコード市場そのものが成長している中、技術に縛られずにサービスづくりに挑戦できる環境がある企業で働きたい方にとって、ヤプリは十分に魅力的に映る“将来性あり”の会社だといえます。
【考察3】700社以上導入と99%以上継続率が示す信頼
ヤプリという企業の“信用力”を語るうえで、外せないのが「700社以上の導入実績」と「継続率99%超」という2つの数字です。これらは単なる結果ではなく、多くの企業から長く選ばれてきた証しでもあります。
サービス開始は2013年。そこから10年を超える歳月の中で、ヤプリのアプリ開発プラットフォームは着実に支持を集め、導入企業は700社を突破。直近では「900アプリ以上導入」「継続率99%」とも言われています。これは、導入した企業のほぼすべてが使い続けているという驚異的な数値です。
この継続率の高さは、「導入して終わり」ではない、ヤプリの地道な改善とサポート体制の積み重ねによるものだと感じられます。初期の導入支援はもちろん、使いやすさを保つためのUI改善、業種に応じた柔軟な機能追加など、実際に利用している企業に寄り添う姿勢が信頼に結びついているのでしょう。
実際、公式サイトや求人情報でもこの実績は前面に押し出されています。企業が何か新しいツールを導入するとき、「他の会社はどれくらい使っているのか」「ちゃんと続けられているのか」という点を気にするのは当然です。そうした不安を払拭してくれる“実績”が、ヤプリにはしっかりと備わっています。
こうした背景から見ても、ヤプリは単なる勢いのあるIT企業ではなく、“顧客に長く使われ続ける”ことを実現している稀有な存在です。就職や転職を考える人にとっても、「腰を据えて働ける会社かどうか」を見極める大きなヒントになるのではないでしょうか。
【考察4】利用料が積み上がる安定したビジネスモデル
ヤプリの将来性を語るうえで見逃せないのが、売上が積み上がっていくサブスクリプション型のビジネスモデルです。単発で終わる取引ではなく、月額で継続的に収益が入る仕組みを採用しているため、一度導入されたら安定した収益が見込めます。
実際、2024年時点での平均月額利用料は44.2万円に達し、導入アプリ数は893件に上っています。また、解約率はわずか0.78%と非常に低く、多くの企業が長期にわたってヤプリを使い続けている状況が明らかです(出典:決算説明会資料)。
初期費用に加え、月額利用料と有料オプションが組み合わさった料金体系は、企業にとっても段階的に価値を感じやすく、ヤプリにとっては着実な収益源となっています。
企業が不況の波にさらされる中でも、必要とされ続けるアプリサービスを、低いハードルで提供できるのはヤプリの強み。こうした構造があるからこそ、景気に左右されにくく、右肩上がりで収益が積み上がるわけです。
IT業界で働くことを考えている方にとっても、このような堅実で継続性のある事業モデルを持つ企業は非常に魅力的です。将来の安定を見据えて働きたいという方にとって、ヤプリは有力な選択肢のひとつになるはずです。
【考察5】人手不足で高まるノーコード需要を取り込める
日本全体で深刻化している「人手不足」。この問題は、IT業界でも例外ではありません(出典:人手不足の背景)。特にアプリ開発の現場では、エンジニアの確保に苦労している企業が年々増加しています(出典:IT人材需給に関する調査)。
そんな中、注目されているのがノーコード開発です(出典:RPA導入実践ガイドブック)。
ヤプリが展開するノーコード型アプリプラットフォームは、プログラムが書けなくても、誰でもスマホアプリを作れるという点が大きな魅力です。事実、ヤプリは「完全ノーコード領域で3年連続シェアNo.1」を記録しており、その実績が支持の強さを裏付けています(出典:プレスリリース)。
また、国内のノーコード市場全体を見ても、今後も堅調に拡大が見込まれています。MIC総研のレポートによれば、ノーコード/ローコード開発市場は以下の通り右肩上がりで推移しており、労働力不足に悩む企業の“代替手段”として定着しつつあることがうかがえます。
ローコード/ノーコード開発ツール市場の国内売上について、
- 2022年度:2,786億円
- 2023年度:3,144億円(前年比112.9%)
- 2024年度:3,589億円(前年比114.2%)
上記の通り、毎年10%超の高成長を続けていると報告。ノーコード単体でも、2023年度135.7%増、2024年度128.8%増と「急拡大が続いている」と分析。
たとえば、自社でアプリを作りたいと思っていても、エンジニアに依頼する予算や時間がないという中小企業は少なくありません。ヤプリなら、マウス操作だけで開発が進められるため、現場の社員がそのままアプリを内製できるケースもあります。特別なスキルがなくても扱えるため、業務負担の軽減にもつながるでしょう。
このように、エンジニア不足という時代背景とノーコードの利便性が合致している今、ヤプリが提供するプラットフォームは、まさに時代のニーズにマッチしたサービスだといえます。だからこそ、「ヤプリ 将来性」というテーマにおいて、同社のビジネスが今後さらに広がる余地は十分にあると感じられます。
【考察6】幅広い業種の課題に対応できる柔軟なサービス性
ヤプリのサービスが評価されている理由のひとつに、「どんな業界でも活用できる柔軟性」があります。実際、アプリの使い道は業種によって大きく異なりますが、それでも同じプラットフォームがしっかりと機能している点は注目に値します。
たとえば、飲食や小売といった対顧客向けの業界では、アプリが売上に直結するツールとして使われています。実際にスイーツブランド「BAKE」は、アプリを導入してからEC売上が440%もアップしたという実績があります(※ヤプリ公式事例より)。
一方で、三菱UFJ信託銀行のような金融機関では、社内コミュニケーションを円滑にするための“業務改善ツール”として導入された事例が紹介されています。
このように、店舗運営の現場から大企業の社内DXまで、ヤプリのアプリは非常に幅広い用途に応えています。事実、公式の開示情報によると、同社は教育・小売・社内活用・Eコマースなど、複数の分野で導入が進んでいるとのこと。1つのサービスがこれだけ多様な現場で重宝されている例はそう多くありません。
業種を問わず導入できるということは、それだけ成長機会が多いということです。景気や流行に左右されにくいサービスというのは、長く安心して使える証とも言えますし、IT業界への転職を考えている人にとっても、安定性のある企業で経験を積めるチャンスにつながるはずです。
【考察7】ノーコードアプリといえばヤプリと言われるブランド力
今、ノーコードでアプリを作る話になると、必ずと言っていいほど名前が挙がるのが「ヤプリ」です。業界内でここまでブランド名が浸透しているサービスはそう多くありません。
ヤプリは単に“ノーコードでアプリが作れるツール”という枠を超えて、企業のデジタルシフトに寄り添うパートナーとしての信頼を築いてきました。
実際、2023年時点での導入企業数は750社を突破し、アプリの累計ダウンロード数は2億回を超えています。これは単なる数字ではなく、「ヤプリなら安心して使える」「ヤプリなら成果が出る」と判断する企業が確実に増えている証拠です。
ノーコードというと便利さばかりが強調されがちですが、ヤプリがここまで認知を広げられた背景には、“顧客体験の質”を重視する姿勢があるのだと感じます。
さらに、同社のミッションには「デジタルを簡単に、社会を便利に」という言葉が掲げられています。この思想がサービス設計やサポート体制にまで落とし込まれており、それが結果として「ノーコードアプリといえばヤプリ」と自然に口にされるブランドにつながっているのだと思います。
就職や転職を考える人にとって、この「名指しで選ばれるブランド力」がある企業に身を置けるということは、大きなキャリア資産になります。自分の関わるプロダクトが、世の中でしっかり評価されている。その実感を得られる環境は、そう多くはありません。
一方でヤプリの将来性を占ううえで重要な今後の課題

ヤプリはノーコード領域で高い評価を得ており、多くの企業に導入されている一方で、将来性を占ううえでは冷静な視点で課題にも目を向ける必要があります。
実際、競合の増加や景気の変動、契約企業の動向などは事業の安定性に影響を与える要因です。
ここでは「ヤプリの将来性を占ううえで重要な今後の課題」として、今後注意すべき懸念点を整理し、より現実的な視点で将来性を判断する材料を紹介します。
【課題1】ノーコード分野で競合サービスが増えるリスク
ヤプリは今や「ノーコードといえばヤプリ」と言われるほどの存在感を持っていますが、手放しで楽観視できるわけではありません。将来性を冷静に見極めるうえで、競合サービスの増加は無視できない要素のひとつです。
実際、ノーコードやローコード開発ツールの市場は、ここ数年で急速に拡大しています。IT調査会社のデータによれば、2023年度の国内市場は812億円に達し、5年後には1.8倍になる見込みとのこと(出典:ITR Market View:ローコード/ノーコード開発市場2025)。
この数字からも分かる通り、業界全体が「伸びる領域」として注目を集めており、新しいサービスが次々と登場している状況です。
たとえば、ツール比較サイトを見ると、ヤプリ以外にもさまざまなノーコード系サービスがずらりと並び、それぞれが独自の強みやターゲット層を打ち出しています。口コミやレビューも豊富で、「他社ツールのほうがうちの業務には合っているかも」と考える企業が出てくるのも自然な流れでしょう。
もちろん、現時点でヤプリが築いてきた実績やブランド力は簡単には崩れません。ですが、これから先も選ばれ続けるには、「ヤプリじゃないとダメだ」と言わせる理由を作り続ける必要があります。
こうした競合環境の変化は、ヤプリへの就職や転職を検討している人にとっても、決して見逃せないポイントです。「成長市場にいるから安泰」というわけではなく、そこでどんな戦い方をしているのか、どんな差別化を打ち出しているのか──そうした視点で企業研究をしておくことが、後悔のないキャリア選択につながっていくはずです。
【課題2】景気悪化で企業のアプリ投資が抑えられる心配
ヤプリのようなアプリ開発支援サービスは、デジタル化の波に乗って順調に広がりを見せていますが、景気の影響は無視できません。特に不況に突入した際、多くの企業が最初に見直すのが「新たな投資」です。
実際、Gartnerの調査によると、物価上昇や景気後退への警戒感から、IT関連の予算を縮小する動きが日本企業の中でも見られるようになっています。ソフトウェアへの投資自体は伸びているものの、「今すぐ必要なもの以外は先送り」という判断を下す企業も少なくありません(出典:世界的なインフレ/景気後退が日本企業に与える変化やIT投資への影響に関する調査結果)。
経済産業省の資料では、製造業をはじめとする業界で、無形資産への投資意欲は確かに増えているとされつつも、景況感が悪化するとその足は鈍ります。実際に、アプリ開発に予算や人手を充てるのは「景気が良いときに限る」といった考え方が、現場レベルで根強いのが現実です。
こうした経済情勢が続けば、ヤプリにとって新規契約の獲得や機能拡張の提案がしにくくなる局面が訪れる可能性があります。IT業界でのキャリアを見据えるなら、成長分野の影にある「投資リスク」にも目を向けておくと良いでしょう。
【課題3】契約企業の解約や利用縮小が増える可能性
ヤプリは「解約率1%未満」という非常に高い顧客維持率を誇っており、業界内でも信頼の厚いサービスとして知られています(出典:有価証券報告書)。
ただ、どれだけ数字が優れていても、契約先の数が増えれば増えるほど、そこに潜むリスクも大きくなるというのが実情です。
特に気になるのが、企業の方針転換やコスト削減の動きです。たとえば、景気の悪化で広告費やIT予算を抑える企業が増えると、アプリ運用にかける費用の見直しが入る可能性があります。アプリそのものは必要でも、「もう少し規模を縮小して運用しよう」と考える企業が出てきても不思議ではありません。
また、他社のノーコードツールが価格面や機能面で魅力的に見えた場合、乗り換えが検討されるケースも出てくるでしょう。ヤプリの競争力が落ちるという話ではなく、むしろ市場が成熟している証拠ですが、だからこそ今後の成長を続けるには、一社一社の満足度を高める施策がますます重要になります。
契約数の増加は喜ばしい反面、「顧客離れ」という見えにくいリスクも同時に大きくなることを、就職・転職を検討している方にはぜひ知っておいてほしいところです。
今後の将来性からヤプリに就職が向いている就活生の特徴とは
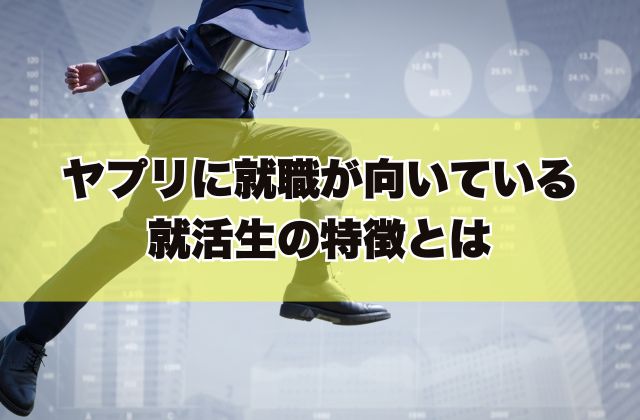
ヤプリの将来性を踏まえると、成長中のノーコード市場で活躍したい就活生にとって魅力のある企業といえます。
一方で、事業方針やサービスの特徴を理解した上で、自分の適性が合うか見極めることも大切です。
「今後の将来性からヤプリに就職が向いている就活生の特徴」という視点では、興味や価値観だけでなく、成長意欲や顧客理解の姿勢なども判断材料になります。
ここからは、特に相性が良いと考えられるタイプを紹介します。
【特徴1】ノーコードやスマホアプリに強い興味がある人
ヤプリで働くことを前向きに考えるなら、「ノーコード」や「スマホアプリ開発」に強い興味を持っていることが、大きな原動力になります。
ヤプリの主力サービスは、プログラミング不要でアプリを作成・運用できる「Yappli」。その特徴からも分かるように、エンジニア経験よりも“スマホアプリで何を実現したいか”という発想力や好奇心が重要視される職場です(出典:募集要項)。
同社の採用サイトにも「ノーコードで顧客の課題を解決する」という言葉が何度も登場しており、技術的スキルよりも、ツールをどう使いこなすか、誰にどう届けるかに重きが置かれていることが伝わってきます。
実際、Yappliはすでに700社以上で導入されており(2024年時点)、その運用を支える立場として活躍するには、“アプリで人の役に立ちたい”という動機が欠かせません。
「自分のアイデアをアプリという形にして届けたい」「技術に詳しくなくても、スマホアプリの可能性にワクワクする」と感じている人には、まさにヤプリはぴったりの環境です。興味があるという気持ちは、立派な素質。就活や転職の軸として、自信を持って伝えてよい要素になるでしょう。
【特徴2】社会や身近な生活をもっと便利にしたい人
「どうしたらもっと暮らしが快適になるだろう」と日頃から考えている人にとって、ヤプリのような会社は非常に相性が良いかもしれません。
ヤプリが掲げているミッションは「デジタルを簡単に、社会を便利に」。たとえば、アプリ開発の知識がない店舗スタッフでも、自分たちで簡単に予約アプリを作成して運用できるような仕組みを提供しています。
実際、ヤプリのサービスは学校や自治体、小売業、飲食業など、私たちの生活に身近な場面で幅広く活用されており、まさに現場から社会全体を便利に変えていく力を持っています(出典:wantedly)。
たとえば、地元のイベント情報をアプリでわかりやすく発信できるようになったことで、高齢者や子育て世代にも情報が届きやすくなった事例もあります。別のケースでは、飲食店がアプリを導入したことで、注文の手間や混雑が減り、利用者の満足度が上がったという声も聞かれます。
こうした小さな変化の積み重ねが、社会の「もっと便利にしたい」という願いを現実にしているのです。だからこそ、自分の仕事を通じて人の役に立ちたい、身近な課題を解決したいと考えている人には、ヤプリという選択肢はとても魅力的に映るはずです。
【特徴3】お客様の立場で考え喜んでもらうことが好きな人
「誰かの役に立てたと実感できる瞬間がいちばん嬉しい」──そんな思いを持っている人にとって、ヤプリの仕事はとてもやりがいのあるものになるはずです。
ヤプリが提供するアプリ開発サービスは、ただシステムをつくるだけのものではありません。たとえば「もっと簡単に予約したい」「お得な情報を知りたい」といった、日々のちょっとした不便を解消するようなアイデアがアプリの機能に反映されていきます。
あるスイーツブランドの事例では、ユーザーが楽しめるクイズやクーポンを組み込み、結果的にEC売上が440%も伸びたという実績がありました。
こうした成果は、開発側が「使う人の気持ち」にしっかり寄り添っているからこそ生まれるものです。現場の声を聞きながら、「どうすればもっと便利になるか」「どんな仕組みなら楽しんでもらえるか」を一つひとつ丁寧に考え続ける。その積み重ねが、サービスの価値を大きく押し上げているのです。
お客様の反応に喜びを感じられる人、目の前の課題にじっくり向き合える人。そんな姿勢を持つ方なら、ヤプリでのキャリアはきっと充実したものになるでしょう。
【特徴4】初めての仕事にも自分から挑戦し学べる前向きな人
新しい環境で戸惑うのは誰だって同じ。でも、だからこそ「まずやってみよう」と一歩踏み出せる人にとって、ヤプリはとても相性の良い会社です。
実際、ヤプリでは新卒1年目の若手が、入社して間もなく実務に加わり、自分で手を動かして価値を生み出しています。たとえば新卒エンジニアとして採用された方は、1年以内に成果を出しチームに貢献したと語っていました(出典:サポーターズ公式note)。
また、学生インターンが自ら考えた新機能を開発・提案し、チームからしっかり評価されたという実例もあるんです。
つまり「経験がないからできない」ではなく、「やってみてから考える」スタンスが歓迎される環境だということ。現場では手を挙げた人に仕事が集まる風土が根づいています。
「まだ自信はないけど、成長したい」「とにかく挑戦してみたい」──そんな気持ちを持っている人にとって、ヤプリはきっと毎日が刺激的で、自分を大きく変える場になるはずです。
【特徴5】変化の多い環境を楽しみコツコツ改善できる人
ヤプリのような急成長中のIT企業では、「変化を楽しめるかどうか」が日々の仕事を前向きに続けていく鍵になります。どんな職種でも、やるべきことは次々に移り変わり、昨日までの当たり前が今日には通用しない。そんなスピード感の中で働くことになります。
実際にヤプリでは、「ゼロトゥワン」や「再構築」といったキーワードが社内カルチャーに組み込まれており、社員一人ひとりが仕組みや業務を自ら見直し、より良く変えていく姿勢が求められています。フラットな風土が根付いているからこそ、肩書きに関係なくアイデアを出し合い、小さな改善でも価値とされる環境です。
たとえば技術チームでは、ノーコードアプリのレイアウト機能を全面的に見直し、誰でも使いやすくなるよう改善を重ねた事例があります。見えないところで地道に努力を積み重ね、それを楽しめる人材がチームに大きな影響を与えているのです。
もしあなたが「決まった作業をこなすよりも、仕組みを少しずつ良くしていく方が楽しい」と感じるタイプなら、ヤプリの環境はまさにぴったりです。日々の変化にワクワクしながら、自分なりの工夫を重ねていける人には、大きな成長のチャンスが広がっています。
ヤプリはじめ大手IT企業から内定を勝ち取るための就活対策6選

ヤプリの将来性に魅力を感じて就職を目指すなら、選考対策は入念に行う必要があります。
とくにヤプリのような成長企業や大手IT企業では、一般的な面接対策だけでは通用しない場面も多くあります。
そこでここからは「ヤプリはじめ大手IT企業から内定を勝ち取るための就活対策6選」と題し、実際に役立つ準備のポイントを具体的に解説していきます。
【対策1】ヤプリなど志望企業のサービス内容を徹底的に研究する
ヤプリのように勢いのあるIT企業を本気で狙うなら、最初に取り組むべきなのはサービスへの理解を深めることです。面接で「なぜうちなのか」を問われたとき、この部分が薄いと説得力が一気に落ちてしまいます。
ヤプリが展開する「Yappli」は、ノーコードでアプリをつくって運用まで完結できるプラットフォームです。公式ページをのぞくと、50種類を超える機能が用意されていたり、年間で200回以上も改善が加えられていたりと、サービスが常に磨かれていることが分かります。プッシュ通知やクーポン配信、店舗情報の連携など、企業のマーケティングに直結する仕組みも揃っています。
こうした特徴を知っているだけで、面接での話し方が自然と変わってきます。
例えば、「小売企業がアプリを通じてお客様とつながる手段を増やす点に魅力を感じた」「UI/UXを学んできた経験から、Yappliの管理画面の設計思想に興味を持った」といったように、自分の経験と重ねて説明できるようになります。実際、就活体験談でもサービス理解が浅いと深掘りの質問に答えづらいという声が多く、ここをどれだけ準備できるかで選考の手応えは大きく変わります。
ヤプリをはじめ大手IT企業の選考を突破するうえで、サービス研究は避けて通れません。志望動機も自己PRも、土台となるこの準備が整っているほど、あなた自身の魅力が面接でまっすぐ伝わるようになります。
そして、こうしたサービス研究を精度高く進めたいなら、IT業界に特化したサポートが受けられる『レバテックルーキー』を活用することで理解の深さが大きく変わります。
レバテックルーキーなら、ヤプリのような成長企業がどこを評価し、どんな視点を重視するのかを踏まえて、あなたの経験を“選ばれる言語”へ最適化してくれるため、志望動機の質が一段上がります。
自力では拾いきれない業界情報まで得られ、内定への距離を一気に縮められます。ぜひご活用ください。
【対策2】なぜヤプリや大手ITで働きたいのか自分の軸を言葉にする
ヤプリや大手IT企業を本気で目指すなら、「なぜ自分はここで働きたいのか?」という根っこの部分を、しっかりと言葉にしておくことが不可欠です。企業が選考で見ているのは、スキルや知識だけではありません。会社の考え方に共感できる人か、同じ方向を見て歩ける人か、そこが大きなポイントになってきます。
実際にヤプリでは、「ミッションやバリューに共感できる人」「テクノロジーへの関心がある人」という視点が重視されており、自分なりの志望理由が曖昧だと、せっかくの面接でも説得力に欠けてしまいます(出典:学情 企業情報ページ)。表面的な志望動機では通用しません。
たとえば、「技術に詳しくない店舗スタッフでも簡単に使えるアプリを提供している点に惹かれました。現場の課題をテクノロジーで解決したいという想いがあり、ヤプリのようにノーコードでそれを実現する企業に強く共感しています」といった具合に、想いと企業の強みが噛み合っていると、面接官の心にも残りやすくなります。
どんなに自己PRやガクチカを磨いたとしても、根本となる「なぜその会社なのか」があいまいだと、評価されにくいのが現実です。だからこそ、自分の価値観や興味をベースに、ヤプリやIT企業を選ぶ理由をしっかり整理し、自然な言葉で伝えられる準備をしておくことが大切です。
一方で、こうした深掘りを自分だけで行うのは難しいものです。
だからこそ、IT業界に精通し企業の本質まで把握している『就活エージェント』を活用すれば、志望動機の精度が一気に高まり、ヤプリのような将来性を見極めたい企業への訴求力も強化できます。
あなたの経験を“選ばれる言葉”へ最適化してくれる心強い伴走者となります。
限られた時間の中で、最大限の結果を残したい方、就活で失敗したくない方は、ぜひご活用ください。
✅【完全無料】実績多数で内定率アップ!IT・Web業界特化の就活エージェントおすすめ3選
- 8,000社以上の優良IT企業情報を保有『レバテックルーキー』|大手Web企業から急成長ベンチャーまで幅広く紹介!志望企業に合わせたES添削や面接対策、ポートフォリオの添削を実施し、内定率アップへ導きます。
- オリコン顧客満足度第3位『TECH-BASE 就活エージェント』|利用後の内定獲得実績5.6倍!IT業界に精通したアドバイザーが内定まで伴走。初歩的なことから専門的なことまで何でも安心して相談できます。
- 文系・理系問わず内定まで最短10日『ユニゾンキャリア就活』|Google口コミ★4.8!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが、就活相談~内定後&入社後も徹底的にサポートします。
【対策3】ガクチカや自己PRをIT企業向けに整理し深掘りしておく
ヤプリのようなIT企業を志望するなら、学生時代の取り組みや自己PRを一度しっかり棚卸しして、業界に合った形で語れる状態にまとめておくことが大切です。
というのも、ヤプリの面接では「その経験をどう活かすつもりか」「サービスを通じてどんな価値を出せると思うか」といった質問がよく出ており、表面的なエピソードでは深掘りに耐えられないからです。
実際に、口コミでは「ヤプリで解決できる社会的・企業的な課題について、自分なりに説明を求められた」という声もありました。
例えば、サークルでSNSアプリの企画を担当し、メンバー数を増やした経験があるとします。ただ“工夫して成功した”と伝えるだけでは弱く、IT企業向けの文脈に置き換えることで、説得力が一気に高まります。
他にも、アプリ上のユーザー行動を分析して改善を繰り返した経験があるなら、ヤプリのように企業のアプリ運用を支える仕事とのつながりが自然に語れますし、「ノーコードで企業のアプリ活用を支える仕事に関心がある」とまとめれば、応募理由としても筋が通ります。
こうした背景から、ガクチカや自己PRは“課題を見つけ、どう動き、成果がどう変わったか”という流れで整理し、ヤプリのサービスと重ねながら話せるようにしておくことが、内定へ近づくポイントになります。
【対策4】ケース面接や企画提案などIT企業特有の選考対策を行う
ヤプリのようなIT系の企業を目指すなら、「ケース面接」や「企画提案型」の選考にはしっかり準備しておきたいところです。というのも、近年のIT企業では“言われたことをこなす”だけでなく、“自ら課題を見つけて提案できる人”が求められているからです。
実際、ヤプリの選考では「なぜ自社アプリに興味を持ったのか」「どんなユーザー体験が印象に残っているか」といった、サービスの本質に迫る質問が一例として投げかけられました。中には「実際にアプリを使った上で改善点を考えてほしい」といったテーマを与えられるケースもあります(出典:ヤプリ公式note)。
こうした選考を突破するには、単なる志望動機だけでは足りません。「今ある課題をどう捉えて、どんな切り口で解決していけるか」を、あなた自身の経験や視点と絡めて伝える準備が不可欠です。たとえば「アプリの継続率を上げるために、通知機能をどう工夫するか」といった具体的な提案まで考えられると強い印象を残せます。
一見難しそうに思えるかもしれませんが、日頃からヤプリのアプリやサービスに触れておけば、自然と提案のヒントは見つかります。ユーザー視点を持ち、自分なりのアイデアを言葉にできるようにしておくこと。それが、ヤプリのような成長企業で働くための第一歩になります。
そして、こうした企画提案型の選考対策を着実に仕上げるためには、IT企業の選考基準を熟知した『就活エージェント』の伴走が大きな武器になります。
就活エージェントを活用すれば、あなたの強みをヤプリの成長性と結びつけて言語化し、通過率の高い提案ストーリーへと磨き上げてくれるからです。
自分だけでは気づけない視点が得られ、IT転職の成功確度を確実に高められます。
限られた時間の中で、最大限の結果を残したい方、就活で失敗したくない方は、ぜひご活用ください。
✅【完全無料】実績多数で内定率アップ!IT・Web業界特化の就活エージェントおすすめ3選
- 8,000社以上の優良IT企業情報を保有『レバテックルーキー』|大手Web企業から急成長ベンチャーまで幅広く紹介!志望企業に合わせたES添削や面接対策、ポートフォリオの添削を実施し、内定率アップへ導きます。
- オリコン顧客満足度第3位『TECH-BASE 就活エージェント』|利用後の内定獲得実績5.6倍!IT業界に精通したアドバイザーが内定まで伴走。初歩的なことから専門的なことまで何でも安心して相談できます。
- 文系・理系問わず内定まで最短10日『ユニゾンキャリア就活』|Google口コミ★4.8!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが、就活相談~内定後&入社後も徹底的にサポートします。
【対策5】ポートフォリオや成果物で自分の強みを分かりやすく示す
IT業界を目指すうえで、自分の経験やスキルをどれだけ具体的に“見せられるか”は大きな差になります。とくにヤプリのように、実際のアウトプットが評価につながる企業では、ポートフォリオや成果物の提出が採用に直結します。
たとえば、ヤプリのデザイナー職では「応募時にポートフォリオが必須」と求人票にも記載されています。これはつまり、どんな考え方で取り組み、どんな成果を出したかを形にして伝えることが、選考での判断材料になっているということです。
もし「大学のゼミでUIを改善した」「個人開発でアプリの継続率を20%アップさせた」といった実績があるなら、その背景やプロセスを簡潔にまとめ、ビジュアルとともに示すと説得力が増します。具体的には、画面設計のビフォーアフターや、改善前後の数値データ、使用した手法の要点などを資料にすると良いでしょう。
ヤプリのようにノーコード開発を通じて企業の課題解決をサポートする会社では、「誰に何を届けたか」「どう工夫したか」という視点が特に重視されます。ですから、成果物をただ並べるのではなく、自分なりの考察や学びを添えておくと、より深い理解が伝わります。
ポートフォリオは“第二の履歴書”ともいえる存在です。言葉だけでは伝わりにくい強みを補い、採用担当者の記憶に残るきっかけにもなります。だからこそ、「何を伝えたいのか」「誰に見せたいのか」を意識して丁寧に作り込むことが、結果的に内定への一歩となるのです。
さらに、こうしたポートフォリオ作成を戦略的に仕上げるためには、IT専門の就活支援に特化した『レバテックルーキー』を頼ることで完成度が大きく変わります。
レバテックルーキーならあなたの強みを整理し、ヤプリのような成長企業が求める視点に沿って構成までブラッシュアップしてくれるため、“選ばれるポートフォリオ”へ最短距離で到達できます。
独学では気づけない改善点を示してくれる心強い伴走者です。就活で失敗したくない方は、ぜひご活用ください。
【対策6】IT専門の就活エージェントをフル活用して選考対策を進める
IT企業への就職を本気で目指すなら、就活エージェントの力を借りることは、もはや裏技ではなく定番の戦略です。
特にヤプリのような成長企業を狙う場合、限られたチャンスの中で質の高い準備が求められます。そうした中で、ITに特化したエージェントは強い味方になります。
たとえば『レバテックルーキー』では、IT系の就活生向けにエントリーシートの添削から面接対策、さらにはポートフォリオの見せ方まで、実践的なアドバイスを受けられます。表面的な対策ではなく、「ヤプリのノーコード領域と自分の経験をどう結びつけるか」まで深く掘り下げてもらえる点が心強いです。
実際、こうしたエージェントを通じて、志望動機やキャリアの軸を言語化できたことで、書類選考を突破し、ヤプリのようなIT企業に内定した例も少なくありません。
「一人で対策するのは心細い」「どこから手をつけていいかわからない」と感じているなら、まずは相談してみるのが一番の近道です。プロの視点で、自分では気づかなかった強みやアピールポイントを引き出してくれるはずです。
そして、視点や提案の幅を広げるためにも、就活エージェントは2~3社登録しておくのがおすすめです。比較することで自分に合ったサポートを見極めやすくなり、限られた就活期間を最大限に活かすことができます。
✅【完全無料】実績多数で内定率アップ!IT・Web業界特化の就活エージェントおすすめ3選
- 8,000社以上の優良IT企業情報を保有『レバテックルーキー』|大手Web企業から急成長ベンチャーまで幅広く紹介!志望企業に合わせたES添削や面接対策、ポートフォリオの添削を実施し、内定率アップへ導きます。
- オリコン顧客満足度第3位『TECH-BASE 就活エージェント』|利用後の内定獲得実績5.6倍!IT業界に精通したアドバイザーが内定まで伴走。初歩的なことから専門的なことまで何でも安心して相談できます。
- 文系・理系問わず内定まで最短10日『ユニゾンキャリア就活』|Google口コミ★4.8!IT業界を知り尽くしたキャリアアドバイザーが、就活相談~内定後&入社後も徹底的にサポートします。
ヤプリの将来性に期待して転職したい人向けの転職支援サービス3選

ヤプリの将来性に期待して転職を考える方は、IT分野に特化した転職支援サービスを活用することで、希望に合う求人情報や選考対策を効率よく進められます。
特にノーコード領域が拡大する中で、ヤプリのような成長企業へ挑戦したい方に向けたサポートが揃うサービスを選ぶことが大切です。
ここからは「ヤプリの将来性に期待して転職したい人向けの転職支援サービス3選」として、信頼性の高い支援先を紹介します。
【転職支援1】マイナビIT AGENT
ヤプリのように成長の余地が大きい企業への転職を考えるなら、まず名前が挙がるのが『マイナビIT AGENT』です。IT分野に特化しているだけあって、業界の動きや企業ごとの特徴に明るいアドバイザーが多く、相談していて安心感があります。
マイナビIT AGENTはエンジニアやWeb系職種の支援に強く、求人紹介だけでなく書類の添削や面接対策まで丁寧に寄り添うことで知られています。初めての転職活動で勝手がわからない人でも、段階ごとに必要な準備を示してくれるため、迷わず進めやすい点が大きな助けになります。
たとえば、ノーコード領域の成長を見越して「ヤプリのような企業へ挑戦したい」という相談をすると、同じ方向性をもつ求人を提案してくれたり、志望理由のまとめ方について具体的なヒントをもらえたりします。面接対策でも、自分では気づきにくい改善点を指摘してくれるので、本番に向かう気持ちが軽くなります。
改めて『マイナビIT AGENT』の特徴・利用するメリットをまとめると、
- 国内最大級の転職支援実績を持つマイナビ運営のサービス
- 全国の大手上場企業から人気ベンチャーまで幅広い求人の紹介が可能
- 特に関東エリアの求人を網羅!一都三県の優良企業の求人が豊富
- 応募書類の準備から面接対策まで、親身な転職サポート
- IT業界出身のキャリアコンサルタントがニーズにマッチした転職を提案
ヤプリの将来性に魅力を感じて転職を検討しているなら、まず登録しておきたいサービスです。業界理解の深さが、選考準備の質を大きく変えてくれます。
【転職支援2】レバテックキャリア
「今よりもっと成長できる環境で働きたい」「技術と向き合える職場に移りたい」──そんな思いを抱えて転職活動を始めるなら、『レバテックキャリア』は心強い味方になります。
このサービスは、IT・Web業界に特化した転職エージェントで、企業とのやり取りを年間7,000件以上こなしているという点が特徴的です。求人票では見えてこない社内の雰囲気や、実際の働き方に関する情報までしっかり把握しているので、企業選びに迷ったときの道しるべになります。
キャリアアドバイザーは業界経験者も多く、技術者目線でのアドバイスがもらえるのも嬉しいところです。
たとえば、ヤプリのように「ノーコード」「アプリ開発」「SaaS」といったキーワードにピンとくる人であれば、業界動向に詳しいアドバイザーが、近い業種や職種の求人をピックアップしてくれる可能性が高いです。しかも、ただ紹介するだけでなく、応募書類の作成から面接での伝え方まで丁寧にサポートしてくれます。
改めて『レバテックキャリア』の特徴・利用するメリットをまとめると、
- ITエンジニアが利用したい転職エージェントNo.1
- 求人紹介だけでなく開発現場のリアルな情報も把握可能
- IT・Web業界を知り尽くしたアドバイザーが徹底サポート
- 内定率を上げる企業別の面接対策・アドバイスも実施
- エンジニアとしての市場価値診断(年収診断)も受けられる
一人で動き出すのが不安な方も、相談ベースから始められるので安心です。
転職市場に詳しいプロと伴走できるレバテックキャリアは、ヤプリのような成長企業を視野に入れたキャリアアップにおいて、確実に選択肢の一つに入れておくべき存在だといえます。
【転職支援3】社内SE転職ナビ
「ヤプリのような成長企業に腰を据えて働きたい」「裏方でもサービスの根幹を支えたい」──そんな思いを持つ方にぴったりなのが、『社内SE転職ナビ』です。名前のとおり、自社開発や情報システム系の求人に特化した転職支援サービスで、IT業界を目指す人には心強い味方となります。
実際、社内SE転職ナビでは“社内SE求人数が業界トップクラス”と公式に打ち出しており、IT職に精通した専任アドバイザーが、応募書類の準備から企業ごとの対策まで丁寧に伴走してくれます。
企業へのヒアリングも重ねているため、「その会社が何を求めているか」「どんな雰囲気の職場か」といった、求人票だけでは見えない“内側の情報”まで教えてもらえるのが魅力です。
たとえば、「ノーコード領域でキャリアを築きたい」と考えている方なら、過去にどんなプロジェクトに携わったのか、どんな場面で改善提案をしたかなど、ヤプリのような企業に響くポイントを一緒に整理しながら応募を進められます。
改めて『社内SE転職ナビ』の特徴・利用するメリットをまとめると、
- 10,000件以上の社内SE求人を保有し、多種多様な企業・ポジションから選べる!
- 入社後の定着率96.5%を誇り、求人と応募者のマッチング精度が高い!
- IT業界に詳しいコンサルタントが面談・書類添削・面接対策などを無料でサポート!
やみくもに求人を探すより、狙いたい業界の中で“自分らしい働き方”を叶える企業と出会いたい。そんな方には、社内SE転職ナビの活用が良い一歩となるはずです。
ヤプリとはどんな会社?業績推移や平均年収など概要まとめ
ヤプリの将来性を見極めたい方にとって、「ヤプリの会社概要」は重要な情報源となります。
ヤプリは、スマホアプリをノーコードで開発できるクラウドサービスを提供し、近年注目を集めています。業績の推移や収益モデル、従業員の働きやすさに関する指標を知ることで、企業としての健全性や今後の成長可能性を具体的に判断できます。
ここでは、ヤプリの事業内容から始まり、直近の業績推移、給与水準、労働環境まで、転職や就職を検討している方が気になるポイントを丁寧に紹介していきます。
事業内容
ヤプリが手がける事業の中心は、企業がスマホアプリを短期間で立ち上げ、日々の運用まで進められるようにする“ノーコード型の開発サービス”です。プログラミングが得意でない担当者でも、iOSとAndroidの両方に対応したアプリを自社で作り、更新し、成果を分析できる仕組みを整えています。
メインとなる「Yappli」に加えて、顧客情報の活用を助ける「Yappli CRM」や、社内コミュニケーション向けの「Yappli UNITE」、Web制作に役立つ「Yappli WebX」など、用途の異なる複数のプロダクトを展開している点も特徴です。
すでに700社を超える企業が導入し、累計ダウンロード数も2億件を上回る規模に成長しています。ノーコード領域の需要拡大とともに事業範囲を着実に広げているため、ヤプリの将来性を知りたい方にとって、今後の成長を期待しやすい企業だと言えるでしょう。
業績推移と今後の見通し
| 決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 当期純利益(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020年12月期(実績) | 2,390 | -590 | -633 |
| 2021年12月期(実績) | 3,263 | -929 | -940 |
| 2022年12月期(実績) | 4,142 | -819 | -941 |
| 2023年12月期(実績) | 4,864 | 265 | -74 |
| 2024年12月期(実績) | 5,511 | 551 | 749 |
| 2025年12月期(会社予想・修正後) | 6,200 | 830 | 920 |
(出典:株式会社ヤプリ「決算短信」)
ヤプリは近年、数字の面でも安定した成長を見せています。
たとえば2022年度には約41億円だった売上が、2024年度にはおよそ55億円まで伸びています。営業利益についても、赤字から黒字に転じ、2023年度には約2.6億円、翌年には5億円台まで回復しています。
これは、導入企業が増えただけでなく、継続的な課金モデルがしっかり機能している証拠です。
このような数字の積み重ねは、単なる一時的な成長ではなく、着実なビジネス基盤の上に立った結果だと言えるでしょう。とくにノーコードという分野の広がりに後押しされ、企業のアプリ開発が内製化される流れの中で、ヤプリのようなツールの需要は今後も高まりそうです。
もちろん市場全体の変化や景気の影響は無視できませんが、現時点での実績とビジネスモデルを見る限り、ヤプリは今後も安定して成長できる素地を持っていると判断できます。IT業界でのキャリアを考えている方にとって、有望な選択肢の一つになりうる企業です。
平均年収と新卒初任給
ヤプリの平均年収は、最新の有価証券報告書(2024年12月期)の情報によると『670万円前後』で、平均年齢はおおよそ35歳。これはIT業界の中でも比較的高い部類に入ります(情報通信業:平均給与 約660万円、出典:令和6年分民間給与実態統計調査結果)。
求人や社員の声を見ても、年収は400万円台から700万円台が中心となっており、入社時点のスキルや職種によって幅があることがうかがえます。若手や新卒層は400万円前後からのスタートが多い印象ですが、実力に応じてしっかり評価される仕組みが整っています。
なお、新卒初任給は一律ではなく、職種や役割によって個別に決まる方針が取られています(出典:募集要項)。この柔軟な制度により、スキルを磨いてきた学生や専門性の高い人材にとっては高めの年収でスタートするチャンスもあります。
ヤプリはノーコードアプリ市場の拡大とともに事業も成長しており、業績が安定していれば、今後の昇給や賞与にも好影響が期待できる環境です。給与水準と将来性のバランスを考えると、長く働くことを視野に入れやすい企業だと言えます。
残業時間
ヤプリの残業時間は「働きすぎないIT企業」で働きたい人にとって、ひとつの安心材料になるはずです。
口コミや各種サイトの情報を総合すると、月あたりの平均残業はおよそ17~24時間前後に収まっており、業界全体の水準から見ても短めといえるでしょう。もちろん部署によって多少のばらつきはあるものの、特別な繁忙期を除けば、平日は20時前後に退社しているという声も見られます。
また、給与には「みなし残業40時間」が含まれているという仕組みですが、実際にはその半分程度で収まっているケースが多く、働き方の実態と制度のバランスにも配慮が感じられます。
過剰な残業が慢性化しやすいIT業界の中で、無理のない働き方を重視している点は、ヤプリの将来性を考えるうえでも見逃せないポイントです。自分の時間を大切にしながら、成長企業で挑戦したい人にとって、働きやすい環境が整っていると言えるでしょう。
福利厚生
ヤプリの福利厚生には、働く人を大切にしようとする姿勢が色濃く表れています。中でも注目されているのが、妊活や不妊治療をサポートする「lily制度」。1人あたり最大50万円までの医療費を会社が負担してくれるという手厚さは、IT業界でも珍しい取り組みです。
そのほかにも、出産祝いや結婚祝い金、バースデー休暇、書籍購入補助、スマホ端末の支援など、社員のライフスタイルや成長を応援する制度が揃っています。中でも「育休中も給与をある程度保障する制度」は、家庭と仕事を両立させたい人にとって心強いポイントです。
ただし、住宅手当については「支給条件が限定的」「金額が高くない」という声もあり、福利厚生全体が完璧というわけではありません。それでも「長く働きたい」と思わせる温かみのある仕組みが整っている会社であることは間違いありません。
こうした姿勢が、ヤプリの将来性を支える大きな要素の一つとなっています。
【Q&A】今後の将来性が気になるヤプリに関するよくある質問
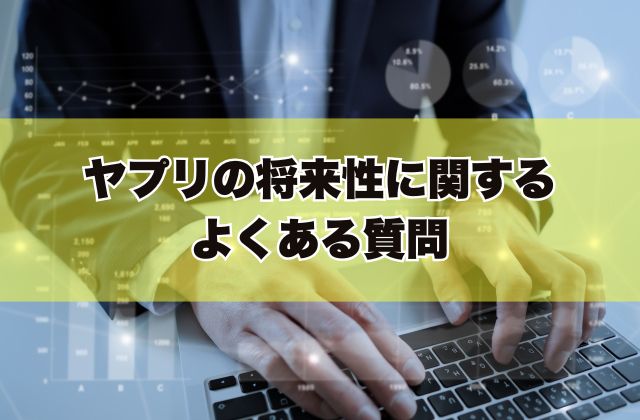
最後に今後の将来性が気になるヤプリに関するよくある質問をまとめました。
ヤプリの将来性や評判に対する疑問を客観的な視点からわかりやすく解説します。企業分析を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
【質問1】ヤプリの経営状況は?
ヤプリの経営面を調べてみると、勢いだけで走っている会社ではなく、数字の裏付けを積み上げている印象を受けます。
直近の決算では売上が約55億円、営業利益は5億円前後、最終利益もきちんと黒字に落ち着いています。事業の中心はサブスクリプション型のアプリ基盤事業で、継続収益を積み上げながら開発投資も同時に進めている形です。
上場市場がグロース区分ということもあり、採用や開発の負担が業績に響きやすい側面はありますが、少なくとも「危なっかしい会社」というより、拡大期にある新興企業らしい経営状態だと感じられます。
【質問2】ヤプリのIR情報はどこで見られる?
ヤプリの将来性を自分の目で確かめたいなら、IR情報を追いかけるのが一番てっとり早いです。
公式サイトには「IR情報」ページがあり、決算短信や決算説明資料、有価証券報告書など、重要な資料がまとめて掲載されています。東証の適時開示情報や証券系サイトでも、業績の細かいデータや決算内容が確認できます。
転職や就職を考える立場なら、売上や利益の数字だけでなく、中期方針やリスクに関する説明にも目を通しておくと、会社の姿がぐっと立体的に見えてきます。
【質問3】ヤプリはいつどの市場に上場した会社?
ヤプリが株式市場に姿を見せたのは2020年12月22日。上場先は当時の東証マザーズで、現在はグロース市場に区分されています。
グロース市場は、企業の成長力を重視するかわりに、業績や株価が振れやすい会社も多い市場です。
つまりヤプリは「成熟した安定企業」というより、ノーコード領域でスピード感ある成長を狙っていくタイプの会社だと理解するとイメージしやすくなります。
【質問4】ヤプリは本当にやばい会社という評判なの?
ネットを見ていると刺激的な表現が目につくことがありますが、客観的な情報を並べてみると、そうした言葉ほど極端な状況ではありません。
口コミでは成長性に対する評価と、スピードについていく大変さの両方が書かれており、新興企業らしい温度差が見て取れます。決算は増収基調を保ちながら黒字化も達成していて、収益構造としての安定性も確認できます。必要以上に悲観するより、IR資料と口コミ、ニュースを総合して判断したほうが現実的です。
ヤプリの将来性を考えるときは、感情的な評価よりも、数字と実績を軸にしたほうがブレずに判断できます。
【質問5】ヤプリの株価は今後どう動くと考えられる?
株価の未来を断言することはできませんが、現在の数値を見ると、投資家がどの程度ヤプリの成長を織り込んでいるかは読み取れます。
2025年11月時点の株価は900円台後半で、時価総額は120億円前後。予想PERは10倍台前半、PBRは4倍台です(出典:(株)ヤプリ【4168.T】)。利益成長やROEの高さにある程度期待している評価水準で、業績が伸びれば上方向に、伸び悩むと調整が入る余地があるレンジと言えます。
ただ、就職や転職の判断材料として見るなら、短期の株価よりも、ノーコード市場がどこまで広がるか、ヤプリがどれだけシェアを維持・拡大できるかに目を向けたほうが本質的です。
まとめ:ヤプリの将来性を強み・競争優位性や事業上の課題から考察
ヤプリの将来性を強み・競争優位性や事業上の課題から考察してきました。
改めて、ヤプリの将来性に関する5つの結論をまとめると、
- ヤプリはノーコードアプリ市場で国内シェアNo.1を誇り、強いブランド力と安心感がある
- 継続率99%以上・導入実績700社超という信頼性が高いビジネス基盤を築いている
- 人手不足に対応できるノーコード開発需要が高まり、今後も市場拡大が見込まれる
- 競合増加や景気悪化のリスクもあるが、安定した収益モデルで堅調な成長が期待できる
- 就職・転職支援ではマイナビIT AGENTやレバテックキャリア、社内SE転職ナビの活用が有効
「ヤプリ 将来性」を総合的に見ると、国内ノーコード市場における確固たる地位と、安定した収益モデルを活かし、今後も成長の可能性が高い企業といえます。
特に、ノーコード開発の需要が高まる中で、同社の提供価値はますます注目されています。今後のキャリア形成においてもヤプリに関わる選択肢は十分検討する価値があります。